011201断想集
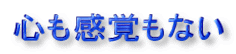
創られた視界 01/12/01.
幻覚が現実のものとして見えてしまうシャルルボネ症候群という病気があるそうだ。原因は白内障などの視野の欠損を脳がおぎなうためらしい。
当人にとっては幻覚だとわかっていながら、じつにリアルに見えるそうだ。こういうことがおこるのは、視界というのは人間の脳によって創造されるからだということだ。
人間は世界の「ありのまま」を見ているわけではなくて、混沌とした世界像を人間に理解できるように「再構成」している。それが人間には「世界」として見えるわけだが、これはあくまでも人間の脳が「創造」したものにほかならないのである。
われわれが見ている視界というのは、人間に理解できるように「創造」された世界なのである。現実をありのままに写しているに違いないとわれわれは思い込んでいるが、これは生物が環境を生きるために適した「世界イメージ」を見ているに過ぎないのである。
こう考えると仏教がいうようなこの世界は「空」や「幻想」であるというのが理解できる。われわれの視野というのは脳や視覚機能による「創造物」にほかならないわけである。この世界は自分の「心」にほかならないというのはこういうことなのだろう。
さらにすすんでそれを「虚構」や「絵空事」として把握することも可能である。世界を「幻想」や「幻」と捉えることによってどうなるかというと、われわれは世界を「まがうことなき現実」や「動かしがたい世界」として圧倒されてきたものの見方から解放されることになる。
「虚構」や「幻」が相手となると、われわれは力やコントロール力を手に入れることができる。世界や現実のありようにひきずり回されずにすむのである。
視界を「虚構」や「幻想」だと捉えることはひじょうに重要である。なぜならわれわれの認識や思考というのはたいがいは視覚情報からもたらされるからだ。
見るものによって、われわれは思考を働かせたり、記憶や思い出をよみがえらせたりする。視界というのは脳や心の発火スイッチみたいなものである。視界を幻や虚構と捉えれば、その発火スイッチは効力をかなり弱める。巻き込まれたり、ひきずり回されたりすることがより少なくなる。
われわれの目に見えるものはすべてとどまることはなく、去ってゆき、変わり果て、消え去ってゆくものである。一瞬にしてなくなってゆくものなのに、人は最悪なことに永久に失われた視覚の記憶にいちばん多くの回想や思考を、金魚のふんのようにつなげてゆくのである。
終わってしまったものにいつまでもしがみつき、とりもどそうという無益なあがきをくりかえてしまうがゆえに人間は多くの苦痛をかかえこむことになった。
この世にとどまるものなど一切なく、そして見ている視覚すら「絵空事」なのである。「幻想」をそうと気づかずに必死にしがみつこうとするのが、人間が根本的に抱えた最大の不幸だといえるのだろう。
視覚は人間の脳によって創り出された「虚構」である。こう捉えることはひじょうに大切なんだろう。「幻」にひきずり回されずにすむからだ。
内なるおしゃべりはエゴの塊 01/12/9.
「われわれが自分自身と呼んでいるものは、単に想像上の存在または錯覚に過ぎない」
こう言い切るのは『グルジェフとクリシュナムルティ エソテリック心理学入門』(コスモス・ライブラリー)のハリー・ベンジャミンである。この本にはたいそう感動した。
「想像上の私」はいつも頭のなかでしゃべりつづけ、自己正当化をおこないつづける。「われわれは非常にしばしば、他人について、またかれらがわれわれを扱う、またはわれわれを軽んずる、またはわれわれを避けるなどの恥ずべきやり方について、自分自身にしゃべっている」
「例えば、われわれは、一定のこと――他人からの敬意など――はわれわれに帰せられる、他の人々は私を好きになるべきだ、われわれは常に幸福であるべきだ、われわれは楽しい仕事、快適な家庭生活、等々を持つべきだ、外部のものごとがわれわれの安楽や楽しみを妨げるべきではない、などなどと思うかもしれない」
「われわれは自分が人生にそのような要求をしていることを意識に気づいていない。しかしながらわれわれは確かにそうしており、で、自分の要求が満たされないとき、われわれは人生および世界がわれわれを正当に扱っていないと感じるので、おしゃべりを始める」
「すなわち、人生はわれわれに一定の便益、一定の恩恵、特典、等々を施すべきだと感じているのである。それらが来ようとしないとき、われわれはいらだちや狼狽を感じ始め、かくして、われわれが話していたあの内なるおしゃべりの絶え間ない流れを始めるのである。内なるおしゃべりの基盤は、どんな形がわれわれに来るにせよ、まさに内なる不平不満なのである」
「要するに、内なるおしゃべりを通じて、またそれによって、われわれは自己正当化と自己賛美キャンペーンをおこない、それによって自分自身を最高度の自己評価価値に保つのである」
「それは自身に何らの真の価値も持たず、基本的にそのことを知っているので、まったくの錯覚に基づいた自分自身についての価値感覚なしには生きることができないのである」
まったくそのとおりである。私の頭も一日中そのような内なるおしゃべりをくりかえしている。自己の価値観が減じたと思ったら、価値観をひき上げるべくずっと自己正当化をおこないつづけている。
あきれたものである。「自我」というのはそうとう醜いものである。人生や世界が私に幸福や便益を絶対に約束しているわけなどないのに、それにあずかれない不満や不幸について、一日中、自分にしゃべりつづけ、自分の心の中を否定的感情や悲観的感情でいっぱいにしている。しかもそれは「想像上の私」のためであり、「偽りのパーソナリティ」のためにである。今度からこんな考えが頭でよぎり始めたのなら、思いっきり嘲笑してやりたいと思う。
さいごにハリー・ベンジャミンおよびかれの師のグルジェフは「パーソナリティはわれわれの真の゛自己″ではないという事実に加えて、それは一個の明確な自己でも存在でもない」といっている。われわれは自分の心身、すなわち身体、精神、感情が自分のすべて、存在の総和だと思っているが、そうではないという。
「東洋心理学は人間を、最も霊的なものから稠密な身体まで、様々な密度の物質から成る七つの浸透体を持つものとして明かす。人間は自分自身のなかの身体しか知らないが、人間の本当の姿はこの七重の姿なのである」
「彼は自己を超えた何か、身体的注視をまったく超え、感覚によって直接触れられることができない何かをあてにしなければならない。東洋哲学が人間の真の組織として明かしているあの七重構造のうちのより精妙で霊的な部分から成る成分をあてにしなければならない」
それには身体、感情体、メンタル体、霊体などあるそうだが、ここまで来るとさすがに信じるのはむずかしなくなる。身体でも感覚でもまったく確かめられないものだからだ。しかし東洋思想や神秘思想は私に確実に安らぎをもたらす知識を――西洋心理学と比べられないくらいに――与えてくれたのだし、このくらいの怪しさを怖れているようでは真の知識を得ることはできないし、人生の苦悩の牢獄からは抜け出せないのだろう。
「心はない」 01/12/11.
心があるというのは、だれがなんといおうと絶対確実にあるものだと思えるものだが――私たちが毎日体験していることだから――しかし、「心はない」ということもいえると思う。
心はあると思えばいくらでも「重み」と「実体感」をもつが、それが「ない」といえば、すっかりと姿形のないものとなる。
頭の中には言葉や記憶、意識などがしっかりとあるように思えるが、それは手に触れられるものでも、目に見えるものでもないし、自分のなかを探してみても確実な物件や証拠があるわけでもない。このような曖昧とした陽炎のようなものをわれわれは絶対確実なものと思い込んでいるのである。
心はあると思う者には絶対確実のリアリティをもつが、いったんないと思いこむとじつに幻のように消え去る。感覚の焦点の合せ方なんだろう。ものをずっと考えつづけるような人間には心の感覚に焦点が合っていて、そこからズラすことさえ思いいたらないから、心の絶対性が感じられるのだろう。体の感覚と同じである。たいがいの体の感覚はふだん感じられない。心も同じようなことができるのだろう。
「心はない」と思いこむとじつに心はそのリアリティや実在感を消滅させてしまう。明澄な意識が残るのみで、「心はない」と言い聞かせることはけっこう瞑想の方法論としてはよいかもしれない。
心理学には行動主義という科学上の必要から意識はないものと見なす学問があって、私はなんて信じられないことをぬかしているんだと思っていたが、たしかに心というのは主観的なもので、客観的にはその存在を確かめることはできないものである。心を信じ、心を愛し、思考や心象に価値をおく人間は、そのことを悟りたくないだけなのかもしれない。
心はないものだと思えば、じつに希薄で、実在性が不確かなものである。それは心だけではなくて、われわれの体の感覚も同じようなもので、体があるのは絶対確実と思われているが、それを感じる感覚自体もじつに希薄なものだと見なせる。感覚もないといえば、ないといえるのではないだろうか。
そうなると、私たちが見ている視野や世界、感じている物の感覚、聞いている音というのも、じつに存在の根拠の薄い、希薄な、あるとは絶対的に言い切れないものかもしれない。知覚の全基盤である感覚自体がそうとう希薄で、根拠不十分なものである。
仏教の基本である『般若心経』では、「物もなく、感覚もなく、眼もなく、心もなく、声もなく、心の対象もない」といっている。じつにわれわれはほんとうは「ない」ものを絶対確実に「ある」と思いこんで暮らしているだけなのかもしれない。
感覚も「ない」 01/12/15.
体があるのは確実なことだと思われている。手で触れてみると確実にあるものだからだ。
しかし体の内部の感覚は、目で見ることもできないし、手で触わることも確かめることもできないし、しょっちゅう感覚は消えているし、確実にあるとはかなり言い難いものである。感覚は「ない」といってもおかしくない。
感覚は姿形のあるものではないし、物体でもない。それがあると確かめられるのは、私の感覚のみである。その感覚自体が幻のようなものであり、煙のようなものであり、蒸気のようなものであり、ほとんど「ない」ようなものなのである。
こういった希薄で、消え入りそうな感覚を大元にして、われわれは世界の「実体性」や「根拠」を感じているわけだから、この世界自体もひじょうに危うい、いまにも消え入りそうなものだといえる。
音もわれわれには確実にあると思われるものだが、はたして音とはなんなのだろうか。目で見ることもできないし、手で触ることもできない。聞こえたとたんに消え去ってしまう。音はあるように思えるが、どこにそんなものが「ある」のかと考えることもできる。
目に見える世界も、映像や写真のように実体のあるものではない。目と脳によって創られた「映像」にすぎない。手で触ることができるのは視界の外側のものであって、視覚自体に触っているわけでもないし、手の感覚自体も先ほどのべたとおり希薄で、幻のようなものである。この世界はほんとうに「ない」ものだといえる。
人間は外界を認識するためにいくつかの感覚器官をもっているが、それはあくまでも人間によって創られた認識イメージであって、それ自体に実体があるわけでもない。蒸気や煙のような幻であって、それによって世界は感じられ、見出されるのである。この世界はひじょうに幻のようなものである。
そのような幻のような世界を絶対的なものとして暮らしているのがわれわれである。あるといえば、あるといえるし、ないといえば、ないともいえる。ただし、絶対確実にあると思う者にはこの世界の実体感やリアリティは崩れることはない。感覚自体に没入しておれば、その感覚の希薄さや幻想性といったものは感じられない。
心もそうである。絶対確実にあると思う者には心の実体性は疑いべくもない。そして実体感をもつ者のみが心の思考や感情に巻き込まれ、ひきずりまわされ、辛酸をなめることになる。心はないものだと知り、感覚の焦点をズラすことを知ったのみが、心や感情の激流から逃れうることができる。
心もこの世界もまことに「幽霊」のようなものである。いると思えばものすごく恐ろしい、いまにも後ろから現れそうな存在に思えるが、そんなものはいないと思う者には怖れも存在も感じられることはない。
要は、信じること自体、「ある」と思うことが、その実在性と実体感をつくりあげ、立ちあげるのであり、いったん「ない」と思えば、その希薄さや根拠の薄さを露にしはじめ、ついには私たちの体の一部の感覚がそうであるように、「消え」はじめるのかもしれない。
といっても世界の実在性や実体感というのは容易に消え去るものではないし、恐れや悲しみのリアリティや迫力はそうかんたんには消え去ってくれないものである。世界の「実在性」を感じつづけるかぎり、われわれは心の悲嘆に巻き込まれつづけるのだろう。
この本はなぜよいのか 2001年版 01/12/16.
ことしの前半は、自分をつくってきたマンガやアニメ、ドラマ、映画などのサブカルチャー分析をしたいと思っていた。それらを心理学的・社会学的・哲学的にいまいちど掘り下げた分析を読みたかった。
しかしこれらのジャンルの満足する水準のものはなくて、映画を精神分析した小此木啓吾の『本当の自分をどう見つけるか』(講談社+α文庫)だけがとくによかった。成功や栄光という「いつわりのパーソナリティ」の悲哀が、強い印象をのこした。
物語分析を深くおこなっているのは、童話の心理学である。ユング心理学、フロイト心理学、歴史学などが入り乱れてそうとうに有益で興味深い分析をそれぞれにおこなっている。童話のワケのわからないお話にはこんな深い意味やテーマが込められていたのかと、ためになることばかりである。
私がとくに気に入ったのは、松居友『昔話とこころの自立』(洋泉社)、ベッテルハイム『昔話の魔力』(評論社)、タタール『グリム童話』(新曜社)、山中康裕『絵本と童話のユング心理学』(ちくま学芸文庫)などである。
ずっと読みたかったマクルーハンの『人間拡張の原理』(竹内書店新社)を古本の百円で見つけて、やっぱり深く感銘した。活字・印刷文化が画一化の大量生産を生み出したという説は驚きだった。また印刷文化が五感のうちで視覚優位の社会をつくりだし、感覚の序列を生み出したということにも感銘した。クラッセンの『感覚の力』(工作舎)が西洋外の感覚世界を豊かに掘り起こしていた。
五感の世界をさぐりだしているうちに竹内久美子のいくつかの著作にであった。遺伝子や繁殖戦略から、男女の関係だけではなく、社会や国家のありかたまでを説明する技法はたいへんに興味を魅かれた。そのなかから一冊あげるとすると『パラサイト日本人論』(文春文庫)がとくによかった。このジャンルを社会生物学といって私はその信憑性や可能性をもっとさぐりたいと思ったのだが、ときすでに私は失業中の金欠状態で、その追究は先には進めなかったのである。
金欠の夏を百円本でしのぐうちに時は流れて金力が回復しだしたとき、三浦展『マイホームレス・チャイルド』(クラブハウス)に出会った。団塊ジュニアに「脱所有」の流れが芽生えはじめていることにたいへん興味をもった。所有の時代はこれから崩れてゆくのだろうか。
諸富祥彦『孤独であるためのレッスン』(NHKブックス)もとくによかった。現代はひとりでいることが悪いことにいわれる時代である。だからいつもだれかと群れなければならず、ひとりや孤独になれば、自分で自分を責める声から逃れられない。こんな世の中ではとくに孤独を肯定したり、ひとりであることを承認する考えがおおいに必要なのであり、孤独をここまで前向きに捉えた本はエライと思う。
『なまけ者の三分間瞑想法』デイヴィッド・ハープ(創元社)は心の澄んだ状態をめざして、実際的な思考を捨てる方法がのべられていて、日々の思考とたたかう私としては重宝した。
ハリー・ベンジャミン『グルジェフとクリシュナムルティ』(コスモス・ライブラリー)は最近まれにない感銘を受けた本である。「想像上の私」や心の「自己正当化」、「内なるおしゃべり」など、まるでふだんの自分の卑怯な頭のなかをそのまま見せつけられているようで、ものすごく感銘した。
これでしばらくはグルジェフ追究の道が決まった。グルジェフは宇宙論を展開して、いままでとっつきがたかったのだ。私はただ自分を苦しめる思考から逃れる知識がほしかったのである。しばらくはニューエイジ系の追究がつづくと思う。
今回は心や身体の虚構性というものもだいぶ感じることができてきたので、かなり怪しい神秘世界までちょっと手を伸ばすかもしれない。自分の存在している感覚自体がソートー怪しいんだから、この世界はもっと怪しくてもおかしくないと思う。
愛と憐れみによる励ましとお便りお待ちしております。
 ues@leo.interq.or.jp ues@leo.interq.or.jp
前の断想集 思考を捨てる技法 01/12/1編集
孤独を責めない心をつくる 01/11/9.
書評集 011202書評集 孤独の肯定 01/12/2.
|TOP|断想集|書評集|プロフィール|リンク|
|