SFのベクトル、歴史のベクトル 01/1/16.
十代のころ私はSF映画ばかり観ていたのだが、なぜ歴史ものではなくて、未来に興味が向ったのだろうかとつねづね思ってきた。答えが見出せたわけでもないし、なぜかそれを考えた文章を見かけたこともないけど、とりあえず考えてみたい。
かんたんにいってしまえば、未来は「希望」であり、歴史は「郷愁」であるといえるかもしれない。希望のある時に未来は夢見られ、郷愁のある時に歴史にいざなわれる。
といっても、SFの未来は必ずしもバラ色ではなく、かなりペシミスティックなものが多かった。「絶望」といってもよかった。絶望から現在は反省されるといった類が多かった。
よく考えれば、私はSFの「異質なもの」に魅かれていたと思う。異質な世界にひきこまれるのがたまらなく好きだった。異質な世界に触れる衝撃というものが、子どものころだれもが感じていたこの世界の違和感と似ていたのだろう。
それに比べて時代劇というのはダサさしか感じさせなかった。なんでこんな泥臭く、イナカっぽいものに人は魅かれるのかてんで信じられなかった。
時代劇というのはだいたい江戸時代か戦国時代の話が多い。サラリーマンが戦国武将の活躍に自分を重ねる誇大妄想が大方だろうと私は見ている。これは歴史の物語なんかではなくて、まさに現代の「出世」物語であり、いささか誇大じみたサラリーマンの思い違いとヒロイックな妄想である。
偉人や評価される人物というのは過去にしか生まれない。未来の偉人、これから生み出される偉人は、現代人には想像できない範疇だからこそ偉人になる。だから賞賛され、評価されるヒーローや偉人は歴史に範を垂れるというわけである。
時代劇のベクトルというのはサラリーマンの名誉欲や出世欲から生み出されたものだといえるかもしれない。
未来は異質性へのベクトル、歴史は評価欲のベクトルが原動力となっていると一応まとめることができた。
時代劇ばかり批判したので公平を期すと、SFというのは現実への拒否や逃避をその原動力としているといえる。現実社会を拒否したり、批判したりするまなざしを増強するものである。
それは科学技術や変革の精神をも生み出すが、逆にいうと、「後ろ向き」の発想でもある。現実を肯定できない精神というのは、ほんとうは未来とよばれるべきものなんかではなくて、現実の拒絶や逃避とよべるものである。
未来のベクトルというのは、「現実の拒絶」といったほうがよいのかもしれない。未来とよばれているが、後ろ向きの発想ゆえに「過去」とよぶべきなのだろうか。
SFも歴史ものも、じつは未来や歴史が問題となっているのではない。現在こそが問題であり、まさに現時点の物語である。未来や歴史なんてものは存在しない。現在の欲望の延長があり、現在の意識があるだけであり、果たされていない現在の願望があるだけである。そして未来や歴史の「仮構」へと向う精神のベクトルがあるだけである。
精神の志向が未来や歴史を虚妄するだけである。「ここではないどこか」「いまの自分ではない自分」という不満が虚構の物語を仮構するのである。現在をすっかり充足しきった者には未来も過去の物語も必要としないのかもしれない。
ツブヤキ断想集

'70年代が抱えていた貧困 01/1/18.
子どものころに見ていたTVやアニメを、オトナになった自分の目からなにが語られていたのか改めて知りたいと思っているのだが、なかなかそういう趣向のよい本は見かけない。
たまたま芸文社から出ている岩佐陽一『なつかしのTV青春アルバム―清貧編―』という本を見つけることができた。この中から驚嘆される出来事をいくつかピック・アップしたいと思うのだが、ほとんど書き写すだけになると思うが、ごカンベンのほどを。
著者がいうには70年代のサブカル作品が支持されるのは、70年代がいちばん貧乏な時代だったからだという。60年代はみんな貧乏、80年代はみんな裕福、だからこそ貧乏が際立って見えたというわけだ。
『あしたのジョー』(69年)も『巨人の星』(69年)もみんな貧乏だった。星飛雄馬の父は日雇い人夫で、四畳半ふた間の長屋暮らし。ひざとおしりに継ぎ当てをしている。ジョーのジムは川辺に建てられている。貧乏ゆえにすさまじいハングリー根性をもっている。しかしいずれも成功の頂点で燃え尽きるように消えてゆく。高度成長時代のひずみと矛盾の顕在化と重ねることができる。
そのあとヒットしたのが『子連れ狼』だ。父と子が乳母車ひとつでさすらう話だが、いかにも悲哀と貧乏にあふれている情景だ。『シルバー仮面』(71年)という怪獣モノは兄弟が帰る家もなし、親もなしといって日本中をさすらう設定になっている。ヒーローがである。
『タイガーマスク』(69年)なんてみなし児を救うためにプロレスで稼いだお金を匿名で寄付する話である。日本の子どもはそんなみなし児のような貧乏な気持ちで暮らしていたのだろう。
『アパッチ野球軍』(72年)も『てんとう虫の歌』(75年)も見覚えがあるが、前者は四国の離れ小島でのケモノのような田舎少年の野球物語、後者は孤児たちがバイトをしながら小学生の兄弟だけでたくましく生きてゆくという話である。東京でない地方の話や生活苦をのりこえる話などが成立していたというのは時代を感じさせる。
カラーの『ゲゲゲの鬼太郎』(71年)は、貧乏や怨念が妖怪というかたちをとったと読むことができるが、やはり企業批判や科学文明批判、公害問題など大人顔負けの問題をとりあつかっていたようだ。ねずみ男は貪欲に儲けを追究する人間のモデルとして描かれているが、そのバツとしてか、いつも貧乏から脱け出せない。
少年マンガとかTVというのはけっこう深刻な社会派のテーマをもっていたりする。いぜん夜中にやっていた『キャシャーン』を見ていたら、これは完全に機械文明批判ではないかと驚いたことがある。思い出せば『仮面の忍者赤影』なんて金目教とか出てきて、宗教批判とか盲従する民衆への批判とかがくり広げられていたように思う。ほんとオトナ顔負けの社会批判である。
時代はすこしさかのぼるが、『砂の器』『飢餓海峡』『人間の証明』といった映画には成功間近になって貧困時代の過ちのせいで没落する話が出てくる。日本人は戦後の貧困をくぐりぬけるなかでこのような重荷を背負わなければならなかったのである。
そして80年代に入るとトレンディ・ドラマの走りである『ふぞろいの林檎たち』(83年)がはじまる。もうこの時代には貧乏という言葉は死滅しつつあったのだが、「モノはたくさんあるのに、なにか物足りない」ことを若者たちは感じはじめる。「なにが物足りないのだろう?」
「つまんねえよ。仕事ばっかりなんてよう。つまんねえよ」―これは団塊の世代のひとりがいうセリフである
このとき発せられた「物足りなさ」はいまだに解決を見ずにいまもずっとつづいている。いったいわれわれはなにを求めたらいいのだろう……?
このような時代にいたって、あらためて70年代や戦後の貧乏とはいったいなんだったんだろうと考えたくなる。貧乏とは絶対に脱出されるべき何かであり、金持ちとはだれもが目指さなければならなかった何かであったのだろうか……。
栄光といつわりの自分 01/01/22.
小此木啓吾『「本当の自分」をどうみつけるか』(講談社+α文庫)は、サブタイトルにあるように名作映画を精神分析で読み解く本である。十年分の映画をまとめて観終わった気分だ。この本は電車で読んでいたのだが、思わず感極まって何度も涙がこみあげてきて困った。
どれも名ストーリーぞろいなのだが、個人的に感動した作品を何作かとりあげる。
まずは『太陽は夜も輝く』、イタリアの90年の作品だ。原作はトルストイの『神父セルギイ』。貴族で挫折した男が、こんどは聖者として祭り上げられるが、栄光や賞賛を捨てられない自分が潜んでいた。その対比として、ともに死ぬことを願った無名の老夫婦の素朴な生き方が描かれ、栄光をもとめた男の欲望が浮き彫りにされる。
『トト・ザ・ヒーロー』(91年フランス)の愛称トトは隣近所の裕福な家庭にあこがれ、自分はそこの子どもなのだと思いこむ。生涯ずっとこの羨望と復讐心を抱えたまま老年まで生きてゆくのだが、その相手からじつは君が羨ましくて仕方がなかったと告げられる。生きがいを失った主人公は殺し屋に狙われる相手の身代わりになって殺される。
『黒い瞳』(87年イタリア)はマルチェロ・マストロヤンニ主演、チェーホフ『小犬を連れた奥さん』などが原作の映画である。富豪と結婚した男が中年になってロシア女性に恋するが、彼女への想いもとげられず、家庭も失って、定期船のウェイターとなってしまう話である。皮肉なことにこの思い出話をつげる相手の妻になる女性がその愛したロシア女性だった。
人は中年になると、それまでの成功や地位、家庭などの意味がゆらぐことになるようである。社会的体裁や世間体のためにつちかってきたこれまでの自分が偽りであり、愚かしく、欺瞞的に感じられるようになる。人生をやり直したい、偽りの仮面をはぎとって、本当の自分になりたい。もうチャンスがないと思う。これは中年の「上昇停止症候群」や「里帰り願望」とよばれるそうである。
同じ主題をあつかったものとして、30年ドイツの『嘆きの天使』は教師が踊り子に魅せられ、破滅の道をたどり、55年フランスの『ヘッド・ライト』では生活に疲れ切った中年男ジャン・ギャバンが冷え切った家庭と人生半ばを過ぎて希望のない日々に戻らざるを得ない結末を迎えている。
しかし69年アメリカの『アレジメント』(カーク・ダグラス主演)は成功した広告業と大会社令嬢の妻を捨てでも、愛した女性といっしょになり、もとの貧しいギリシャ移民にもどったことで、このうえもない心の安らぎを得ることが描かれるようになる。そのあとの84年『恋におちて』や95年『マディソン郡の橋』では離婚社会を背景にして第二の恋が肯定的に描かれている。
いずれも「ほんとうの自分」とはなにか、青年期にめざした社会的成功や栄光とはなんだったのかと深く考えさせられる物語である。人は金持ちや栄光に憧れる。がむしゃらに走りつづけ、そしてそれを手に入れる。しかしふとした瞬間にぽっかりと心に空隙が空いていることに気づく。
ほんとうに自分がほしかったものはなにか、自分はなにを求めているのだろうか。『黒い瞳』はそれに気づいたあとでも、すべてを失ってしまう物語であったから、強く印象に残った。あるいはすべてを失ってでも、貧しい自分に戻りたかっただけなのかもしれない。それこそが、ほんとうの自分が求めていたものかもしれない。
これらの物語は戦後日本の姿に重ねられることもできる。がむしゃらに追い求めてきた富や栄光を目の前にしていいようのない閉塞感や虚無感にむしばまれている。われわれはこれらの映画のどの主人公のような道をたどることになるのだろうか。
全共闘の反動としてのポップ・カルチャー 01/1/23.
80年代、ワケもわからなく「ネアカがよい、ネクラは悪い」といった風潮に、中学生だった私は巻き込まれた。思索や文学することはネクラなことで、ブームだった漫才師のようなネアカな人間にならなければならないという強迫観念が押し寄せてきた。
このころの私はそんなに思索好きでも、深刻な人間でもない、マンガとかSF映画とかを好むちゃらんぽらんな人間だったのだが、このネアカ・ブームにはやっぱり腹を立てた。なんでマジメに考えたり、思索することが悪なのか、歴史を知らない、時代に閉じ込められていた私は思っていた。
のちになって60年代後半の学生運動や全共闘などの経過や挫折の結果であることを知るようになるのだが、これは書物や活字などからの情報によるもので、どうも時代や歴史の流れとしての実感がとぼしい。その当時の雰囲気や人々の意識といったものをもう直に感じることはできないからだ。
このときの挫折とショックがよほど激しかったのだろう、当の団塊世代たちはばりばりの順応主義と現状維持主義、会社中心主義や消費社会の世の中をつくっていった。政治とか思索とか、権威とかをぜんぶ捨て去っていって、現在のカネだけの世の中をつくった。
変革思想の失敗や反省から、のちに育った世代はファッションやポップ・カルチャーの奔流のなかにもまれることになる。もう政治や変革に希望をかけるのはよそう、小市民的な幸福を断固として求める、という時代になってゆく。TVやマンガ、映画、音楽、ファッションといった享楽的なサブ・カルチャーがのちの世代に、ラディカルな思想を排斥したかたちで、押し寄せることになる。
現在の自閉的で自家消費的なサブ・カルチャーの奔流というのは、変革思想に希望をもった世代の反省や挫折、反動としてもたらされたものなのである。政治や社会との関わりを断ったその流れは必然として、自閉的なオタク・カルチャーにゆきつく。
この社会は極端から極端に走ったワケだ。社会や政治を変えられると世界相手に闘った時代から、それらをすべて排斥したうえで、マンガや音楽のみにある夢想的な幸福を追い求める時代になった。ネクラ排斥はそのミニマムな幸福が完成する過程においておこったというわけだ。
さて、そのような狭く閉じ込められた幸福の流れは現在もずっとつづいている。変革もほかの可能性も失われたポップ・カルチャーの幸福のみがひたすら追求されている。人々はかつて抱いたような変革や改革といった発想を一向に持たないまま、この狭い世界のなかで息苦しさや虚無感を感じながら、家庭や学校などの狭い閉鎖的な空間で暴力をふるったりして、なんとか計画人生をやり過ごそうともがいている。
なにが必要なのか。もう世界相手の変革の思想はとうぶん生まれないだろう。息苦しさや閉塞感はどのようにしたら、払拭できるのだろうか。極端にゆれすぎた針をもう少し中間のところにもってゆく必要があるのだろう。ポップ・カルチャーはたしかに魅力的であり、楽しいものであるが、自閉的な慰めだけを楽しみに人生を生きてゆくというのは少々情けなさ過ぎると私は感じるのだが。
アンチ労働主義は、ジェンダー問題でもある 01/1/27.
仕事と会社だけの人生を送りたくないとずっと私は思ってきたのだが、これってジェンダー問題からも光を当てなければならないと改めて思う。つまり男が稼ぎ、女が家庭を守るといったしくみである。
私はとにかく仕事と会社だけに終わる人生なんてまっぴらだとずっと思ってきた。そんな人生なんて生きがいも、生きている意味も価値もないと思ってきた。こういう価値観をもっていると、必然的に男に食わしてもらおうと思っている女性たちのジョーシキとぶつかることになる。
女は当たり前のように男が稼ぎ、男からプレゼントをもらったり、食わせてもらえるものだと思いこんでいる。私のアンチ労働主義の気分には、そういう女性たちにたいする反逆や拒絶の気持ちが潜んでいるのかもしれない。
なんで男だからといって馬車馬のように働き、女や家庭のための「人柱」のような生き方をしなければならないのかと思っている。しかしこういう考え方は、あまりにも自分主義すぎたり、利己主義的すぎたりするので、あまり明確に意識したことはないまま、あいまいにしてきたけど、やっぱり心の奥底にはそういう漠然とした不満をもちつづけていたように思う。
まあ、私は親の離婚問題で女側の功利的な視点ばかり与えられたから、男としてよけい反発する気持ちが強いのかもしれない。個人的な母への恨みなのだろうか。
キャリア・ウーマンやフェミニズムなどで自立した、男に頼らない価値観もたしかに増えてきた。といってもまわりの現実はやっぱり男が稼ぎ、女は守られるといった常識が、恋愛や家族を基軸にしてまかり通っている。男と女の関係として、あらがたいがたい、あるいは当たり前すぎて問題にされることもない常識として、世を覆っている。
一部の女性たちは女の差別や搾取を撤廃しろと声をあげている。女は差別されている、劣位におかれているといっているが、その見返りとして男に保護されてぬくぬくしている女性もたくさんいる。
共犯関係である。女は差別される代わりに男の労働を搾取し、男はその見返りとして支配欲や権力を満足させられているのである。そういう関係を無視して、サベツだのサクシュだのだけを叫ぶのは、あまりにも一方的だと思う。
私としては、女の差別や搾取をうんぬんする前に、仕事と会社に人生を奪われる男を救け出してほしいと思う。まずこっちの悲惨や疎外に焦点を当てるべきではないかと思う。男はほんとうに女を支配し搾取する立場ばかりなのだろうか。男はほんとうに強者で、女をかしずかせる権力者で、そして心から幸福だと思っているのだろうか。
朝から晩まで会社に奪われ、そんな一生が間断もなくつづく男の一生がはたして幸福で、これが権力者の姿だといえるのだろうか。私はこんな一生にずっと疑問を抱いてきたが、そういう生涯に追い込む男女関係や社会のあり方をあらためて問い直さなければならないと思う。
男を労働機械にしたもの 01/1/30.
男の人生を仕事と会社だけに奪われる生涯にしたのは、ある意味では、女性である。あるいは女性との関係である。または男がソトで働き、女がイエを守るといった社会的常識である。
こんな常識はだれが求め、だれが必要としたのだろうか。男だろうか、女だろうか。どちらが先に求めたのだろうか。どっちがトクをしたのだろうか。戦後の女性の言い分では男である。女性には選挙権や職業の平等がなかったからだ。
トクをしたはずの男は働き尽くめの生涯を余儀なくされ、会社に生涯を縛られる。過労死の危険も男につきまとう。自由な時間や消費、娯楽の享受といった面では、男のどこがトクなのかと聞きたくなる。
このような性別役割の分業をもくろんだのは、国家か企業のどちらだろうか。国家の税制は主婦のパートの105万円までの税控除と、専業主婦の年金・保険の控除といううしろだてによって女性の社会化を抑えてきた。
出産や育児の仕事は国益だからだろうか。女性の育児一本化によって、男は家庭や育児から切断されて、さあ企業の前で丸裸である。24時間どう扱きつかおうが、国家の労働力は主婦によって再生産される。性役割分業は男の企業戦士化にじゅうぶんの効果をはたした。
家庭や育児は男にとっても企業戦士化の防波堤ではなかったのか。専業主婦の登場によって男は言い訳を失ったのではないか。国家と企業は手をたずさえて、男の企業戦士化と労働力再生産の両方を手に入れたわけである。
国家と企業のたくらみといっても、ではなぜ民衆はその役割を喜んで受け入れたのか。シンデレラ・ストーリーのプロパガンダが国家と企業によって流され、それが効を奏したというのだろうか。女は男に養われるのが幸福のゴールというのは政府と企業による洗脳なのか。
でもそれは強制というよりか、一部の者をのぞき、みんなが喜んで受け入れているものである。恋愛至上主義はマスコミや娯楽産業の一大産業である。われわれは国家や企業にころりとだまされるほど、バカなのだろうか。
企業のなかでは女性も適齢期を過ぎると、企業のリストラの対象にされることもあるし、ふつうのオッサンたちもいい目で見ないようになる。会社とふつうのオッサンがグルになって社会的圧力をかけて、女の居場所をなくすようにしている。首謀者はだれなのか。
戦後のがむしゃら経済システムはもう絶対に見直すべきだ。性分業をもたらす税制は検討する必要があると思うし、性分業の社会的意識も改めてゆくべきだろう。
女が政治や経済の分野で(タテマエの)平等を手に入れたのなら、こんどはぜひとも企業に囚われた男を救って!ほしいものだ。男の悲惨や不公平にも目を向けてくれということである。
悪役とは、「だれ」のことだったのだろう 01/1/31.
子どものころに観たTVマンガや特撮モノというのは必ず「悪役」が出てきて、「正義の味方」がかれらを倒してゆくという単純明快な空想物語だった。
しかし空想物語だといっても、現実になんらかの脅威や怖れがないことには子どもが好むものとはならない。悪役とはいったいだれのことだったのだろうか。
悪役はたいてい地球を支配しにきたり、侵略しにきたり、人類を殺しにきたり、悪の世界に変えるといったものだ。つまり国家戦争を教えられていたのだろうか。
敗戦後まもなく力道山がヒーローになった。外人レスラーをばたばたと倒してゆくカタルシスに酔ったわけだ。子どものヒーローものも、あいかわらずそういった国家イデオロギーをくり返していたのだろうか。
子どもに限らず大人も正義と悪がきっぱりと分けられた単純な図式が好きだ。目的や規範が明確になるうえ、人々の結集も得られる。そしていつも自分たちが正義である。イラクとアメリカがおたがいに正義だと信じたように。
しかしヒーローものは戦争アレルギーの戦後社会においてずっと戦争プロパガンダをしていたとは考えにくい。あるいは政治レベルではない、商業ベースにおいて人間の本能たる闘争本能はずっと駆り立てられていたのか。
ショービジネスの力道山のように満たされないカタルシスを空想物語で満たすのは無害なことである。虚構が現実にはみ出そうとしないかぎり、敵をたおす虚構は現実のいやな気分やつらい気分を吹き飛ばしてくれる。そういう機能なのだろうか。
悪役とは、心理的にいえば、困難や逆境のことともいえるかもしれない。そういった境遇に追い込まれたときの心の持ちよう、脱出法、勇気や奮闘といったものを教える。励ましである。現実に敵国がいない以上、困難な状況での心理的な勇気を子どもマンガは教えていたのかもしれない。敵とは、われわれを脅威や困難に追い込むものの具象である。
悪をやっつける単純なヒーローものでは、困難は絶対的な悪であり、力でねじ伏せなければならないものである。しかし子どもモノといっても、すべてが悪ばかりではない、グレーの部分もちゃんと描いている。『デビルマン』や『タイガーマスク』は悪からやってきたものであり、『キャシャーン』は悪の部分に入ってゆき、『キカイダー』は悪になったりした。必ずしも悪役をすべてやっつけ、困難に打ち克つだけのヒーローが描かれていたわけではない。
困難や逆境と融和する、あるいは理解する方向も呈示されている。敵に打ち勝つだけのヒーローでは敵を悪一色に染める単純な認識レベルしかもちえないだろう。
まあ、われわれは子どものころ敵や悪(家族や子どもがいるかもしれない者)を容赦なく倒してゆくヒーローものを見て興奮を覚えたわけだが、同時に悪役が全面的に悪でもないことも学んでいったはずである。それは現実のさまざまな人たちや世界の各国にも適用できることである。
正義とか悪、上下とか優劣とか一面的な単純なものの見方しかできない人はもう一度TVマンガを復習する必要があるのかもしれませんね。あるいは一面的な悪しか提示できなかった作品も多かったかもれしないし、そういう作品こそもっとも胸がスカっとして人気が高かったかもしれないし、権力や成功を得るにはこちらのほうが有利なのかもしれないが、たぶんそんな単純な世界にだれひとりとして、いつまでも憩うことなどできやしないと思う。
ツブツブツブツブツブツブツヤキ断想集

怠け者の不覚 01/2/2.
私はほんと怠け者だと思う。ちょっと休みがあったら、ふとんにもぐりこんだまま何時間でもだらけていられる。あ〜、こういう時間がいつまでもつづくのならば幸せなのにと思ってしまう。
現代というのは「怠けること」が禁止された世の中である。たぶん人々の怠け者に対する憎悪や憤懣というのは相当なものである。じつは憎悪なんて近親憎悪か、怠けられない自分に対する怒りにほかならないわけだけど。自分にフタをしているがゆえに他人にもフタをしないと気がすまないというやつだ。
日本人というのはいつからか強迫的に怠けることを禁欲してきた。もうほとんどキョーハク観念である。地球上の多くの土地では電車が何十分も何時間も遅れる国があるということすら思いもつかない。そういうおおらかで、社会全体で怠けているような国はいくらでもあるのにである。
ヨーロッパが工業化するときには貧民救済という美名のもとに怠け者を収容所に送りこんだ。怠け者は路上にたむろするような貧困者だったからだ。ヨーロッパは怠け者を強制的に排除しないと、奇怪な鉄ブリキ帝国を築けなかったわけだ。
日本人はなぜだかヒジョーに勤勉な人間になった。幕末の日本人は西洋人の目からみるとなんてのろのろしているんだと牛のように見えたそうである。たぶん日本人は西欧文明の魅力にとりつかれてしまったのだろう。みんなが西欧のモノやカネを見せびらかすようになると、稼ぎの悪い怠け者は淘汰されていったのだろう。女には見向きもされない。
多くの日本人が地方や農家から都市に出てきてサラリーマンになってゆくころには欲しいモノがたくさんあった。自動車にTVにマイホームにといった具合に。ほしいモノがたくさんあったから馬車馬のように勤勉に働いた。
ふっと気がついたらほしいモノがなにもなくなっていた。消費なんかつまらないものになっていた。だから80年代にはブランド品や高級品に人々が群がった。バブルが弾けると、もとの時代に戻っただけだ。
それなのにカイシャと仕事だけは勤勉の倫理をずっと押しつけている。ひとまわり時代が遅れている。経営者や管理者にとってはコキ使う方がオトクだからだろう。だからわれわれも勤勉の牢獄のなかにずっと閉じ込められなければならない。
じつはわれわれは怠けたいのではないかと思う。でもあまりにも長く抑圧され、禁欲されたものであるから、それを名づけることも、明確に意識することもできなくなってしまっているのではないだろうか。生活リズムや生活スタイルがあまりにも勤勉な時間割に慣らされてしまったため、ゆったりと怠けるという時間リズムさえ思い出せないのだ。
ほしいモノがないのなら働く必要はない。でもガッコを卒業したら就職しなければならないという常識からなかなか頭を抜け出せない。マジメに働かないと、老後保障や健康保険、ローンを払う金がなくなると、あとから追加されたゼイタク品のために、身動きがとれなくなってしまっている。
また金持ちと貧乏人のヒエラルキーや蔑視、権力者と下層民の恐れなどがついてきて、てんで強迫多忙社会から降りられない。
勤勉に働かせたい者たちはもっとほしいモノや必要不可欠のものを増やして、エサでわれわれを釣ろうとするだろう。そこで怠け者は気づかなければならない。ほしいモノをたくさん手に入れるより、もっとだらだら怠けていたいだけなんだと。
将来の不安をエサにして、人々はもっと働かせようとするだろう。怠け者は知らなければならない。怠け者は貧乏が必然であり、カネもモノも保証もないんだということに。さもないと怠け者はいつまでたっても、郷愁のふるさとには帰れない! 怠け者は人生観も死生観もごっそり入れ替える必要がある。
社会の片隅と中心 01/2/3.
社会の片隅に埋もれてゆく人生が恐ろしくて、むなしいことだと思ってきた。中心になりたいという気持ちと裏腹に、社会の片隅にどんどん埋もれてゆくジレンマに悩まされてきた。
なぜ自分はこんなに社会の片隅に埋もれるのが怖いんだろうと思ってきた。たぶんこういう気持ちに悩まされる人は多いのだと思う。有名になりたい人やタレントに憧れる人というのは、このマスコミ社会ではそうとういると思われるからだ。
どうやら存在の二重性がその原因にありそうである。つまりこの世界というのは自分が存在してはじめて意識できるものであり、自分が死んでしまったらこの世界は消滅してしまう。自分はこの世界の主役であり、中心であり、自分がいなければこの世界は存在しない、かけがえのない存在である。
しかし他人にとっては自分はただの見知ラヌ人であり、生きようが死のうがまったく関わりがないちっぽけな存在である。他者にとっての自分は無意味で、無価値で、顧みるに値しない存在なのである。
この落差と断絶が根源的不安となって、他人に認められたり、有名になって人に知られようとする認知欲望を生み出すのである。つまり他者の認識世界においても自己の存在が無ではなく、中心でないと耐えられないというわけだ。(瀬古浩爾『わたしを認めよ!』洋泉社新書)
う〜む、自我の世界と他者や社会の世界が錯綜しているというコトか。自分の世界での中心としての自分と、社会のなかでのポジションの中心の同一性を願ってしまうというワケだ。
これは世界が混乱しているということになるのだろうか。自己が認識する世界と社会が認識する世界の混同である。自己世界においては自分は中心かつ絶対根拠にほかならないわけだが、社会のほかの人々にとっては無に等しい。この世界の二重のあり方がどうも納得できていないというか、どうしても承認できないのである。
認識の失敗なのかもしれない。自己の認識と他者の認識が同一視されている。つまり自分が認識しているものは他者も同じに認識しているはずだという思いこみがあるのかもしれない。
自己と他者の認識の分離や隔離ができていない。そのために他者の認識においても、自分は中心に座らなければならないというわけか。(この自我問題はここで腰を折る。これ以上やったら無謀な断言をしそうだから。ただこの認識問題をきっちりと理解しないことには片隅の恐れはかんたんには去らないだろう)
不安を遠ざける方法を提示してみたいが、他者から無意味や無価値と思われることに耐える、あるいは慣れることである。他人にとっては自分はちっぽけで、とりに足らぬ存在であるのは当たり前であり、それが人間の認識の構造の常態であると理解することだ。
人間は自分が認識する世界しか認識できない。他人は永久にこの世界の主観や意識として現われることはない。不可能なのである。他者にとって自己は無意味や無価値でしかありえないのである。どうやら他者にとっての自己の無価値さというものにじっくりと馴染み、たっぷりと身に染みて理解することしか、不安から解き放たれることはないのだろう。
それは同時に他者に認知されないでも十分に安らかになれる自分の発見でもある。
ペルソナとアニマ・アニムス 01/2/8.
ペルソナというのは社会的な役割や立場の仮面であり、この仮面を被っているとき、人は真に個性的な存在とはいえず、集合的な存在となり、社会の期待に合せて生きているといえる。
そういう仮面をつちかうさいに削ぎ落としてきた側面――男ならとくに女性性、女なら男性性を――それぞれアニマ・アニムスという。
人はそれを生身の異性に投影する。映画『ぼくの美しい人だから』(アメリカ90年)はその対比を見事にうきぼりにしている。ハンサムで高収入な男が、16も年上のどうしようもない堕落した女に魅かれる話である。この男は成功する途上において、自分のそのようなだらしのないアニマを切り落としてこなければならなかったわけだ。(山中康裕『シネマのなかの臨床心理学』有斐閣ブックス)
この本のおかげでユングのいっていたアニマ・アニムスにひじょうに興味を魅かれた。さいきん私が興味を魅かれた映画というのも、中年になって女性に夢中になり、それまでの成功や地位を投げ捨てる話だった。これはまさにペルソナとアニマ・アニムスの関係を語っているということに気づいた。
映画では生身の異性に魅かれる表面的にはただの第二の恋の話になっているが、ユングのテーマである無意識の影やアニマ・アニムスとの統合を試みているのだと読むことができる。
ユング心理学のいっていたことはこういうことなのかとはじめてわかった気がする。ペルソナが削ぎ落としてこなければならなかったほんらいの自分――男ならアニマを統合しようとする心の成長を試みていたというわけだ。
しかし私には自分の中にそのようなアニマ像があるのかわからないし、感じたこともない。それに私はあまり男らしい男ともいえないし、男らしくありたいともほとんど思わないし、男の社会的役割を嫌っているようなところもある。そういう人間にはまたそういうタイプの逆の影やアニマ像があるんだろうな。
いったいどんなのだろうと思う。影とかアニマというのは、意識に現れる自分とまったく正反対の人格と考えればいいのだろうか。狂暴で凶悪で、また女性的である自分が、無意識のなかに生きられなかった自分としてうごめいているのだろうか。
無意識なんかわからない。言葉であまりにも「無意識」という枠組みを与えられたために頭でしか無意識を理解していないし、そのような知識のうえではやはり無意識の存在自体が怪しいものに感じられてしまう。
ともかくおかげでユング心理学の導入部がつかめた。ユングってどうも神話とか神秘的な側面が前に表に立ちふさがってどうも読み進む気になれなかった。私はその先のトランス・パーソナル心理学にはだいぶ興味を魅かれていたのにである。
私にとってのそれへの興味は、意識上における思考や感情、認識のとりあつかいにあった。つまり意識内の問題である。これで無意識を探る必要性というものにようやく気づいたのだが、無意識とかアニマ・アニムスってほんとうにあるのかなぁ。。。
「感情商品」とマスメディア 01/2/12.
自分の感情や感じ方というのは自分の思い通りにならないことがままある。ときには自分の思っていることを裏切って、不安や悲しみに射すくめられてしまうこともある。
ではこのような感情や感じ方をかたちづくったのは何かというと、やはり子どものころに見たマスメディアが大きく作用しているのだと思う。私の感情の反応の仕方を大半影響づけているのはおそらくこれらのマスメディアだろう。
だから子どものころに見たマスメディアを見直すということは、自分を規定づけているものとふたたび対峙し直すということになるだろう。あるいは「他人によってつくられた自分の感情」をとりもどすきっかけになるかもしれない。
現代のマスメディア社会において感情はすでに「感情商品」や「中古品の感情」として大量に出回っている。われわれはすっかりその感情商品のパターンにはまり、無条件に反応づけられてしまっているというワケだ。
子どものころに見たマンガやTV、映画は自分にどのような作用を及ぼしているのだろうか。たとえば私にとって印象深いのは『ポセイドン・アドベンチャー』や『エアポート××』といった一連のパニック映画である。これらでは極限状況における自己犠牲を描いていて私はえらく感動したものだが、思いやりといった感情はこんなところでつくられたのではないか。
私には人より優越しようと見せたり、上下関係を誇示したりする気持ちに抑制が強いが、TVアニメなんかではけっこうエラそうにする人を批判するような場面があったように思う。冷酷であったり、鼻持ちならない役柄として叩かれていた。
逆にどんくさくて、デキが悪いほうがみんなの主人公である方が多く、はたしてこのような道徳律を組み込まれたわれわれは、この競争社会で足カセになるのではないかと思わなくもない。デキの悪い、ダメな人間の方が愛らしいが、そんな人間により同一化してきたことはよいことだったのだろうか。
自分の感情に抗えない最たるものは恋愛感情である。われわれは恋愛感情こそ自分の自分たるゆえんだと思っているが、はたしてそうなのか。「感情商品」によって刷り込まれたものではないのか。
この社会では「恋愛感情の商品」にはまず事欠かない。音楽であれ、マンガであれ、TV、映画、これらはほぼ恋愛感情を大量に売っている。この商品は今世紀の陰の最大のヒットだろう。はたしてこの恋愛感情の起源は子どものころに見た恋愛もののマンガではなかったのではないか。思い出せば、『キャンディ・キャンディ』――。
スポ根ものや学園ものはどのような感情や規範をわれわれに組み込んでいったのだろうか。『巨人の星』や『あしたのジョー』、『ゆうひが丘の総理大臣』『俺たちの旅』。情熱や感動――? あるいはカイシャでガムシャラに扱き使われるためのバッテリーみたいなものか?
『ウルトラマン』や『仮面ライダー』、『ガッチャマン』『ガンダム』のような勧善懲悪的なものはどうなんだろうか。ユング派によるとどうも「悪」は「自我」がなりたつために必要な過程であったといわれているが、われわれはおかげで立派な自我をもつにいたったのだろうか。
感情というのは自分独自のほかにはありえないものという感が強いが、じつは大半はマスメディアによってインプリンティング(刷り込み)されたものだといえる。ハイジャックされたようなものである。そしてそんなことをつゆとも知らず、刷り込まれた感情を自分独自のものと思いこみ、人生の判断をおこない、暮らしているともいえるのである。
マスメディアに操縦された感情のまま生きるのもそれはそれでいいだろう。それは商品であっても自分の好き嫌いで選びとってきたこと事実もあるからだ。
ただ自分の考えが変わったのに気持ちや感情がついてこないと感じたときには、自分のつちかわれてきた感情の起源や生成要因といったものを検討してみなければならないのだろう。慣習や規範、過去のメディアのドレイになるか、自由になるかは、自分の判断しだいだ。(そんなにかんたんには刷り込まれた感情や規範から自由になれるとは思わないが)
悪役と投影 01/2/15.
悪役とはどうも自分のなかの悪い性質が投影されたもののようである。それは自分のなかの攻撃性であり、不安であり、欲望であり、その他社会規範などに抵触するものなどもろもろの悪い性質がひとまとめにされたものである。
子どもマンガに出てきた怪獣なり悪役なりというのは、自分のなかのそのような部分というワケである。だから子どもたちはその悪役をこてんぱんにやっつけ、そして勝たなければならないのである。憐れんでやったりしたら、悪に呑みこまれてしまう。
しかしやっかいなことに多くの人はオトナになっても同じ機構から抜け出せない。他人を叩いたり、嫌いたり、攻撃したりする。それがもしかして自分の中にある性質を投影しているということに気づかずに。
私はかろうじて母への反抗期のときに非難している言葉がそのまま自分のことじゃないかと気づくことができた。批判する構図がそのまま自分にあてはまることに気づいたときに、「あ、こりゃあ、口に出していうのも恥かしい」と思った。
といっても、「投影」はむずかしい。現実と投影の区別なんかなかなかできるものではない。ぜんぶ投影だったら、現実や外界のことはなにひとつ分からずじまいだ。もしかして人間なんて自分の心の投影でしか物事を見れないのかもしれないな。しかも自分の悪い部分はぜんぶ他人に押しつけてしまったりして。
他人のある所が嫌いになったり、不快になったり、腹立たしくなったりしたら、たぶんそれは自分の中にある共通の部分に向けられているということである。他人のことじゃないよ、アンタ自身のことだよ。ということだ。
自分と他人の区別ができていないのである。といっても主観のなかでは自分と他人の区別なんかできない。並行している。あるいはごちゃごちゃである。自分のいやな部分は、他人の行動によってよりいっそうはっきりと見えるだけだ。だから他人を叩く。
それが自分の中の心だと気づいた人はどうしたらいいのか。悪や敵はまるごと愛したり、肯定したりはしないほうがいいそうである。自我の価値体系が崩壊してしまうそうだからだ。
まあまったく排斥せずに悪の居場所を見つけてやることが、ユングのいう「統合」であったり、「個性化」であるということである。
なんだかどういうことかよくわかりかねるが、他人の悪が自分の中にあるとあると気づくことは人格の成長でもある。いやな部分、嫌いな部分は他人ではなくて、自分にもあるんだと気づくことができたのなら、まあ自分の中のそのような部分とのつき合い方を新たに模索できるだろう。
子どものときにはともかく悪役は排斥するばかりでよかったかもしれないが、いい大人になったのなら、自分の心は自分の問題として処理すべきである。悪い、いやな部分はどんな善人やいい人にも含まれているものである。それにフタをするばかりでは解決しない。自分のものとしてふたたび統合しなおすことが必要だということである。
攻撃欲と投影 01/2/17.
投影ってわかりにくい。たとえば、他人の恐れは自分の敵意だとか、人からの拒否は自分の拒否する気持ちのすりかえだとか、自意識過剰は自分の他人への強い興味だとか、逆転した関係が示唆されている。
いまいち納得しづらかったのだが、投影に関してのよい本を見つけられないこともあって、そのままにしておいたのだが、さいきん童話分析とかユング心理学に近づく機会があって、ちょっと理解が進んだ。
敵意とか攻撃、拒否とか批判とかいうのは意識上では受け入れにくい。自分はそんな攻撃的な人間ではないと思いこみたい人はとくにそうだ。そういう攻撃欲が否定されるには、ぜんぶ他人のせいにしてしまえばよい。子どもマンガが自分の悪い部分をぜんぶ怪獣や悪魔などの悪役に背負わせたように。
でもその他人のせいは、なぜか自分のほうに矢面を向けてくるんだな、コレがおかしなことに。怒りや否定や拒否が、ぜんぶ自分めがけてふりかかってくるのである。なぜなんだろう。
まあ単純に感情のベクトルは自分と他人しかいないからだろう。自分ではないのなら、他人から向ってくるしかいない。ほんとに単純な二分法だ。攻撃のベクトルは自分に向ってきているものだと思いこむだろう。
浮遊する否定された攻撃欲は、頭を失って、他人という頭を得て、自分めがけて攻撃をしかけてくるように思えるというわけだ。自分の攻撃欲を否定したばかりに、他人から総攻撃を食らってしまったように思うというのは、なんとも皮肉な話だ。
意識が拒否したばかりに攻撃欲は復讐するのである。受け入れたくない自分の一面は排斥したり、拒否したいものだし、社会や親もそれを期待するだろう。それは怪獣や悪魔、身近な友人や他人などになすりつければいいものだ。
しかしそれがうまく立ち行かなくなったときに、不安や恐れ、悲しみなどの負の感情に押しつぶされることになってしまう。たいがいの人は他人や悪人のせいにして叩けば、すむみたいだが、それを失敗した人は神経症とかに悩むことになる。
そういう人は仮面と影の分裂から統合の機会が訪れているということである。つまり投影のとりもどしである。悪役の統合である。悪役は他人ではなく、自分の一部であるということを自覚する段階に達したというわけである。かつては自我を形成するさい、必要だった切り離された悪をもういちど統合する時期にきたということである。
注意深く他人の感情と思われているものを照合することだ。これは自分の感情なのである。自分の心のなかのことである。悪役や否定された感情・他人の性格は、たいては自分の否定したい一面だろう。他人の仮面をかむっているだけだ。
自分の感情として引き受けること。それは他人やまわりの感情ではなく、自分の心であり、頭をすげかえられた自分の感情である。自分に向ってくる怒りや攻撃や否定は、抑圧された自分の一面かもしれない。他人の感情と思われていたものを統合したときに心はひとまわり成長することになるのだろう。
――参考文献 ケン・ウィルバー『無境界』(平河出版社)「7 仮面のレベル/発見のはじまり」
感情の読み違い、心の線引き 01/2/18.
投影とか影の問題というのは感情の読み違いなのだろう。たとえば不安は興奮であり、恐れは自分の敵意であり、悲しみは怒りであり、引っこみ思案は他人の拒否といったように。(ケン・ウィルバー『無境界』平河出版社)
自分のほんとうの感情を否定するがゆえに他者からの敵意や攻撃に必要以上にさいなまされていると感じるのである。それは他人が攻撃しているのではなく、自分の攻撃欲がブーメランのように自分めがけて返ってきているだけである。
怒りや敵意、攻撃欲はとうぜん回避しなければならないだろう。それを回避するには悪役や敵役になすりつければいい。心の線引きを狭く引くわけである。
それに失敗すると他者からの脅威にさらされることになる。自分の否定された攻撃欲は他者からの攻撃になってしまう。
ということで投影のとりもどしには心の線引きをふたたび広げなければならないわけだ。悪役になすりつけていた悪感情を自分のもとして引き受けることだ。
他人の感情と思っていたものは、じつは自分の感情なのである。あるいは模造である。これはすべて自分の心の中のことである。全部自分の心である。他人ではない。
他人やまわりの人の感情と思っていたものは、自分の心にほかならない。心の片割れや投影が、もっともらしく他人の顔をしているだけである。自分の感情である。そもそも他人の感情などいちども感じたことはないのだから、自分の感情の推測や投影でしかありえない。
他人の感情は私の感情である。そして私自身が感じていた感情はその対立や片割れとしての感情である。だから他人におあずけされた敵意や怒りは、自分の恐れや悲しみとなって返ってくるわけである。ひとつの心がふたつに分けられると対立のメカニズムが働き、強い敵意は自己役に勝るわけである。
同じ自分の心を、他人役とか自己役にふりわけるのである。そして折半された自己役の感情は見たくないものを他人役になすりつけるかわりに、他人役からの脅威に脅かされるということである。
他人の感情と思っていたものは自分のものとして引き受けるのが必要なのだろう。全部自分の心の中のことだ。他人の悪意は自分のものとして確かめる必要がある。そうして折半としての自分の感情の読み違いも改めることができるのだろう。まだまだわからないこともたくさんあるけど。
他人の感情は自分の感情 01/2/19.
影や投影ってわからないことがまだたくさんあるが、他人の感情は自分の感情であると認めればわかりやすいのではないかと思う。自分と他人の関係をひっくり返してしまうのである。つまり他人の感情や世間からの目といったものはぜんぶ自分の感情であると見なせば理解しやすい。
ふつう他人の感情と自分は切り離して考えられるけど、これは切り離すことができない。それはあくまでも自分の感情で推測したものであったり、敷衍したり、あてはめたりするものである。つまり自分の感情のネガである。
私たちはじっさいにいちども他人の心の中をのぞけたわけではないので、他人は自分の感情やその経験によって推測するしかない。しかしいつの間にか、その解釈を「現実」だとか「絶対」だと思いはじめて、他人と自分を切り離すようになる。自分の「外」のものになるのである。
その解釈はある程度は当たっているかもしれないし、現実に近いものであるかもしれない。だが、やっぱり「自分の感情」なのである。
したがって感情の読み違いなんてものはしょっちゅうである。私たちはそれをたしかめないで、ひとり合点して、悩んだり、悲しんだりしてしまうのである。
やっかいなのは影の投影である。自分のいやなところを他人や悪役に押しつけて自我を形成するプロセスがわれわれにはあるみたいで、こうなったら他人の人格は実際を離れてとんでもない人格像となってしまう。
攻撃欲や怒りが他人や世間に投影されると、これまた困ったことになる。その人は必要以上に他人や世間に責め立てられ、脅かされているように思えてしまうことになる。恐怖症や被害妄想にはこのようなメカニズムが働くのだろう。
他人や世間がやたらコワイという人は、自分の攻撃欲や怒りが投影されたり、または自分の感情によって推測された他者の怒りに脅かされているわけだ。ほんとうは他人や世間が怒っているのではなく、自分が怒っていることを見たくない、見られなくなっているだけだ。
他人や世間が自分に思っていることというのは、じつは自分自身の思いにほかならないということだ。他人と自分を切り離してしまったから、他人の思いというものが、自分の心中や、感情だということになかなか気づかなくなる。
なんだ、他人や世間の思いっていうのは、自分自身がつくりだしたものなんだ。てっきり他人や世間が思っているものだと思い込んでいたけど、じつは自分が推測したり、敷衍した思いや感情にほかならないわけだ。
他人や世間の思いや感情を、自分の心の中のことだとしてとりもどすこと。それは自分の心であり、感情なのである。そうすれば、不必要に脅かされたり、悩まされたりすることはすこしは減ることだろう。自分のものだとわかるようになれば、それをコントロールすることも容易になるだろうからだ。
他人の感情は自分の感情であり、心なのである。他人がじっさいに思ったり、ほんとうに感じているように思えるかもしれないが、あくまでも自分の心や感情がつくりだし、推測したものにほかならない。しばらくは他人やまわりの人の思いや感情をじっくりと観察・検討してみる必要があるな。
 01/2/13編集
01/2/13編集
社会的コントロールとしての感情 2000/3/13.
感情というのは、人を悲嘆のどん底に追いやったり、あらぬ心配に駆り立てたりして、ときには個人を必要以上にさいなむものである。感情は害悪をもたらすほうが多いのではないか。では、なんのためにあるのか。
社会規範を守らせるためにあるのではないだろうか。人々の行動を統制するには感情というのは有効な道具である。怖れや恥ずかしさ、いたたまれなさ、居心地の悪さといった感情は、じつに人々の行動を規範に合わせるために適した道具である。
こういうすごいことを「感情社会学」という新しい社会学はいっている。感情というのは、近代社会にとっては理性的・合理的に行動できない要因としてかなり排斥されてきた。感情は合理的人間にとっては原始的で、野蛮で、封建的なものだったはずである。
しかし喜怒哀楽のない人生はつまらないといった言葉が世間で交わされることは多い。感情は自然に発生するものであり、コントロールできない、という思い込みを多くの人はもっており、だからこそ「自分らしさ」や「個性」があらわれると人は思っている。
不思議なものである。感情は原始的で野蛮なものだったはずが、いっぽうでは自分らしさや個性をあらわす重要なアイデンティティになっているのである。そして同時にその感情は社会規範に合わせるためのコントロール装置でもある。
自分らしさをあらわす感情(好き嫌いなど)が社会のコントロール装置になっているとは皮肉なことである。だからこそ感情は合理的でない野蛮なものとしてかたづけられ、学問にもかえりみられなかったのだろうか。社会コントロールの道具として感情は隠蔽される必要があったのだろうか。
わたし自身の経験からいって、社会趨勢に反抗的・批判的な行動や態度をとるようになると、悲しみや怖れなどの感情をより強く感じる経験をしてきた。だから感情というのは社会にコントロールされるための道具だという思いを強くしてきた。
頭で考えた新しいことは感情という古い規範によくうちのめされるのである。頭でおかしいと思いながら、社会規範や社会コントロールに従わされるのはあまり愉快な経験ではない。だからわたしは規範による感情はできるだけコントロールできる知識を身につけたいと思う。
論理療法などでは感情は自然に発生するものではなく、考え方や思考スタイルによって生み出されると考えている。だから感情はコントロールできるものなのである。ストア哲学や仏教などでも思考を虚構ととらえ、無思考にすることによって感情のコントロールを説いている。感情はコントロールできないものではないのである。
ただし感情のコントロールはかんたんなものではないし、幼少期からつちかわれた感情の自然的な規範はちょっとやそっとでは動かせるとは考えにくい。新しい感情社会学といったジャンルがその感情規則から解き放たれる知識を提供してくれるよう期待していたいと思う。
参考文献:山田昌広『感情による社会的コントロール』/『感情の社会学』世界思想社
規範感情は解体できるか 2000/3/16.
感情というのは自然に発生するものだと思われている。悲しいときには悲しくなり、さみしいときにはさみしくなるといったように。
しかしこの感情を客観的にみると、規範や慣習にしたがっていない場合にそのような感情がわきあがってくることがわかる。つまり規範や慣習に従わない罰としての感情である。
いぜんわたしはいろいろな慣習や規範といったものにことごとく反抗していた。大衆の画一的行動といったものにもかなりの目くじらをたてていた。しかし慣習に従いたくないとつっぱねても、どうも感情がいうことを聞いてくれない――慣習に沿わないと、悲しさやさみしさの感情にいつも襲われたのである。
頭で考えたことに対して心(感情)はついてこないのである。ということでわたしは感情というのは規範や慣習を守らせるためにある道具だという思いを強くしていったわけである。(カミュの『異邦人』はそういうところをついているのだと思う)
だから規範や慣習に流されないためには感情の解体というものが必要になる。また、たぶんこの規範感情というものから解放されることが、人間の究極の自由というものではないのかと思う。感情の奴隷になった人間はおそらく自由から程遠いのだろう。
それにしてもわれわれは感情というものを客観的に見ることはまずないし、感情こそが自分自身となってしまって、感情に支配されるのが多くの人のありかただといえるし、そもそも感情に対する知識や追究すらほとんど手つかずといった状態だ。
なんでもわれわれの一般的常識からすれば、感情は原始的なものであり、人間は近代化ととも合理的な行動をするようになるそうである。それにしてもわれわれの身のまわりの人が感情を捨てて合理的に行動していっているようにとても見えないし、わたし自身も感情の怒涛のような毎日を経験しているし、世間一般では好き嫌いという感情が自分らしさや個性を表わす指標になっているのはどう説明するというのか。
合理的行動どころから、感情に支配され、のっとられた道具になってしまったのがわれわれポスト近代人ではないのか。そして感情というのは人間を規範や慣習に従わせるための装置である。われわれは感情の奴隷であり、そしてそれによるコントロールを通しての社会規範の奴隷となっているわけである。二重に奴隷となっているわけだ。
そこで感情は解体していったほうがいいと思うのだが、しかし感情がなければどうやって対人関係や世間との処し方を実行していったらいいのかと疑問に思わなくもない。感情はいろいろな状況に即座に対応するすべを教えてくれるひとつの指標ではないのか。これがなければ、われわれは状況への対応のしかたを誤ってしまったり、状況を読みまちがってしまうのではないか。
しかしそんなことより大事なことは感情の支配から自由になることである。感情の奴隷になれば、規範や状況の囚人と化してしまう。われわれはまずここから自由になる必要がある。
感情をコントロールする方法としては認知療法や論理療法、仏教の思考の消去などの知識がある。心理学やセラピーは社会順応の方法を説いているが、体制離脱の方法としても使用可だろう。
感情支配からの自由 2000/3/17.
感情から自由になる方法はいったいどのようなものがあるだろうか。感情に支配されることの多いわたしが知っている限りでは、感情を相手にしない、無視する、放っておくという方法がある。感情を客観的にながめて、それと同一化しないこと、また感情的になったところでなんの問題の解決にも解消にもならないと知ることである。
わたしたちが感情的に激昂するのはそれがなんらかの解決をもたらすと期待しているからである。感情というのはじつのところ赤ん坊が母親に注意を向けさせるメッセージの道具だったのであり、大人になっても同じ用法で他人へのメッセージとして使用している。つまり「わたしは怒っている、悲しんでいるから、あなたは〜しなさい」というメッセージをもっていることだ。
こういうメッセージの用法としての感情という側面を忘れると、怒りについてサルトルがいったように「魔術的試み」の効用を信じてしまうことになる。感情にはなにかの力があると思いこんだり、万能的な力があると思ったり、はては超能力的効果まで妄想されることになってしまう。
感情というのは自分を怒りや悲しみの激昂手段として用いて、他人にメッセージや行動の悔い改めを迫るものである。いわば、自分の身体まるごとをもちいて怒る広告塔や悲しむ広告塔と化すわけである。広告塔の維持費や苦痛というのは自分にとってひじょうに高くつくので(ぴかぴかのネオン・サインみたいなものである)、安く抑えるに越したことはない。
人が感情的になるのはやはりその効果を信じているからということになるのだろう。あまり解決も解消にもつながらないと理解するのなら、感情への期待も使用頻度もそう多くならないというものである。
もうひとつ忘れてならないのは、喜怒哀楽のない人生はつまらないと思い込んでいることである。楽しんだり、喜んだり、悲しんだりしてこそ、人生は楽しいし、うるおいがあるものであり、自分らしさや自然体を生きられているという「感情信仰」をもっているのなら、われわれはよりひんぱんに感情的に生きようとするだろう。
近代人の常識として合理的に生きることが人間の進化の道標であるという考えがあったはずなのだが、いつの間にか野蛮や動物的であると思われていた感情が、自分らしさや生きがいの指標となってきたのは意外なことである。
合理的な生に対する反抗として60年代あたりから「セックス革命」とかともに「感情革命」がおこった影響のようである。そしていまでは感情や好き嫌いがすっかり自分らしさや個性を表わす指標になっているという断絶がおこっている。
感情や好き嫌いが自分らしさ、個性だと思い込むようになると、人は感情的な価値を高め、その力を過信するようになるだろうし、その結果感情の奴隷となったり、自己は感情の荒波にほんろうされる小船になったり支配されてしまうだろう。感情にハイジャックされる人生が待っているということである。
感情を批判的にながめるようになると、テレビ・ドラマや映画、小説などは驚くほどメロドラマ――つまり感情の埋没や没入を讃歌していることに気づく。感情の讃歌と感情的になるススメである。
おそらくこれは商業主義や消費主義と関係があるのだろう。好き嫌いや好み、感情的に生きることによってもっと消費や贅沢をしなさい、モノやサービスを買いなさいという商業論理の要請なのだろう。われわれがより感情になり、感情が自分を表わす指標になったのはそういう事情があるからだろう。
どうやらわれわれがより感情的になったり、感情の荒波にほんろうされたりする理由は、感情にこそ人生の生きがいがあり、およびそれこそが自分なのであるという「感情信仰」とでも呼ぶべき現象があるからなのだろう。感情を信仰し、崇拝されるがゆえにそれに同一化し、支配され、ふるまわされるというわけだ。
こういう信仰を捨て去ったところに感情からの自由があるのだろう。しかし「感情のない子どもたち」といった本のタイトルがあるようにわれわれは感情がなくなることをロボトミーや病的形態と感じるような傾向ももっている。感情のない人生は死人の生であり、生きるはりあいや活力がなくなることなのだろうか。
しかし老荘思想や仏教には枯木死灰の状態を理想とする思想もないわけではない。感情や欲望は人生を苦しまさせる要因だと考えられているからである。
「感情信仰」の時代に生きているわたしとしてはどちらの立場のほうが正しいのかは早急には判断を下せないが、社会規範や慣習に盲目に支配されたり、感情の荒波に苦しめられるようなら、感情というのはできるだけ捨てるほうがいいのではないかと思う。感情から自由になることができたのなら、われわれはどんな幸福の地平を手に入れられるかわからない。
感情信仰の時代 2000/3/18.
感情に生きる喜びやはりあい、生きがい、自分らしさを求める時代である。楽しさや喜び、うれしさ、といった感情の経験をひじょうに大切にする時代である。
そのようなすばらしい経験はぎゃくに、皮肉なことにそれらを得られない苦悩や疎外感、自責感をもたらすものである。「わたしはほかの人のように楽しんでいない、喜べない、うれしくない毎日を送っている」といって嘆くわれわれの苦悩をも生み出した。
また喜びや楽しみを求める精神は、感情に支配され、ほんろうされる人たちをも生み出した。感情経験を自分の大切な目標や生きがいとするのならば、自己は感情の荒波にほんろうされるだけだろう。
感情に生きがいをもとめる人生は感情のコントロール能力を失うことでもある。感情を崇拝してしまえば、自己は感情に支配され、操られることになってしまう。感情を経験することが唯一の楽しみになるということは、感情の生成に手をつけないということである。コンロール不能になる。
テレビ・ドラマや映画はほんのささいなことで感傷的、メランコリーになる人たちばかりを出演させている。そういうムードや気分になることを推奨するかのようである。感情的に深く没入することがより深く意味のある人生を送れるかのようである。
こういう思い込みをもつために人はより感情的になり、そのためによけいに感情のコントロール不能に冒される。感情を自己と思いこみ、同一化してしまうと、もはやコントロールできなくなってしまう。主体は思考や理性的な自分ではなく、感情となってしまうからだ。
かつての時代はこんなに感情をもてはやしはしなかったのではないか。立身出世や合理的な人間、理性的になることが人々の目標であり、栄達や名誉であったのではないのか。
それがいまでは瞬間的な楽しみや喜びの経験をもとめる時代になっている。べつに非難するつもりはないが、なぜなら長期的・将来的な拡大成長が見込まれる時代ではなくなったのだから、とうぜんの対応、適応であるわけだが、感情経験だけに喜びをもとめるようになると、感情にふりまわされる危険があることを指摘したいだけだ。
それとやはり根本的に感情信仰は幻滅に終わるのではないかということも指摘しておきたい。感情を人生の目標や生きがいとしたって、感情なんてものは瞬間的・刹那的にしか味わえないものだから、ぜったいに永続的・持続的な喜びは得られないのに決まっている。こんな瞬間的なものに喜びをもとめるのはあまりにも苦しい、見返りのない選択ではないだろうか。
現代はいつの間にか感情信仰の時代になっていた。このことに気づくことは大切なことだろう。無自覚に求めていたものは、すぐに幻滅に終わる性質のものであるかもしれないからだ。また喜びの裏面にはかならず悲しみがついてまわるものだということをわきまえておくことだ。ついでに感情にふりまわされる危険もついてまわる。
「楽しさ」の感情強制 2000/3/20.
バブル時代というのはレジャーや高級品の消費がものすごくさかんだったのだが、わたしはこの時代にひじょうに腹を立てていた。画一化や商業主義の強制というもっともらしい理由づけもできるのだが、「感情」という側面に注目してみると、「楽しみ」の強制があったからだということがわかる。
バブルに狂奔した時代というのは「だれもがみな楽しまなければならない」という感情強制がまきあがった時代でもあったのだ。むりに楽しんだり、楽しいふりを強制されるのはものすごくだるく、うっとうしいものだ。だからこの時代、わたしは腹を立てていた。
80年代は「ネアカ」と「ネクラ」という言葉が流行り、「だれもが明るくならなければならない」という感情強制がはびこった時代である。「ネクラ」は「犯罪者」なみのあつかいをうけ、だれもがバカみたいにはしゃぎ、うかれ回り、明るくふるまわなければならない時代だったのだ。
90年代は打って変わって大不況になり、いたって平和で穏便な時代になった。「楽しさ」の感情強制への反動と非難がまきおこったのだといえなくもない。
このように感情というものに着目してみると、わたしというのは、よそからの感情強制にひじょうに反抗していることがわかる。日常のいろいろな場面でもそうだし、社会的な選択や行動においても、感情強制のにおいをすこしでも嗅ぎとると、いっせいにかたくなな自分の感情に固執しようとする。
日常の場面や社交では「つまらないのにおもしろいふりなんかしたくない」とか「しょうもないのに楽しいふりなんかできるか」と、楽しみを強制する場では、むりに楽しく装うのを極力避けている。会社なんかでは「やる気がないのにやる気を出せ」とか「忠誠心なんかないのに忠誠を尽くせ」とかをいわれるのがとてつもなくいやだから、なんとか会社から距離をおこうとしているのだと思う。
テレビドラマなんかではある感情――悲しみや楽しさを作為で産出させようとするのがわかっているから、醒めた目で、感情を踊らされないように半ば白けながら見ている。
このようにわたしは人や状況から特定の感情を強制されるのがとてつもなくいやなのである。他人からある感情に乗せられたり、そういう感情にもっていかれるのが、たまらなくいやなのである。
こういう感情拒否がなせ起こったかと考えてみると、おそらく新興宗教批判やファシズム主義(集団主義)批判などのマスコミの影響によるところが大きいのではないかと思う。「崇拝や熱狂、陶酔などの感情には気をつけろ」というメッセージが戦後くりかえし流されてきたのではないのか。この影響は無視できないだろう。
わたしのなかにある感情強制への拒否感というのはよいことなのか、よくないことなのかはいまのところ判断しにくい。ただ、自分の感情にこそ「自分らしさ」や「自分としてのアイデンティテイ」があると考えて固執しているとするのなら、わたしは感情により多く支配され、ほんろうされることになってしまうだろう。
自然な感情こそが自分なのだと思うと、感情を崇拝してしまって、その聖なるものに手をつけられなくなってしまう。コントロール不能ばかりか、わたしは感情に首輪をかけられてひきずり回されるようなものである。悲しみやつらさに悩まされるのはあまりよい経験ではない。
この感情拒否についてはどう考えればよいのだろうか。戦後の人たちは感情を拒否し、その感情を守ることで「個人の尊厳」や「自分らしさ」を守ろうとしてきたのではないだろうか。でも感情に自分のアイデンティティを賭してしまったら感情の苦悩にふり回されることになるし、けっきょくのところそれは、商業主義や消費主義の要請や必要ではなかったのではないだろうか。
いまのところなんとも判別しかねるが、この感情の強制と拒否という捉え方はなかなかの鉱脈ではないかと思う。もう少し考えてみたい。
感情の経済学 2000/3/9.
ある感情を相手から受けたら、お返しをしなければならないというのが人間関係の暗黙のルールとしてある。これは貨幣や商業、取引き、交換関係と同じものである。この貨幣関係をベースにして人間関係はだいたいなりたっている。
たとえば、ある人から心を傷つけられたり、心ない仕打ちをうけたら、報復や復讐をしなければならないと多くの人は思っていたりする。またある人からお世話や恩義をうけたりしたら、恩や義理をお返ししなければならないと人は思うものである。
さまざまな感情というのは貨幣のように人間のあいだを流通しているのである。感情の買い手は売り手に恩義であれ、報復であれ、お返ししなければならないということである。
刑罰というのも、ニーチェが指摘するとおり、損害や被害をうけた感情はどこかに等価物があり、相手側にその苦痛分をあたえることによって報復が可能だと思われているものである。
さまざまな感情や苦痛、損害、恩義といったものはどこかに必ず等価物があるはずだという考え方がわれわれの人間社会の根本的なベースになっている。商業の関係が金銭関係とまったく関わりのない人間関係においても貫徹しているというわけだ。
だが、この感情の貨幣というのは混乱をきたしているというのが実状だろう。カネのように数字で割り切れるものではないし、一方的な取引き成立の思い込みだけで成り立っている売り手もいるし、主観的な思い込みやモノサシによってひじょうに雑多で多様な売買関係が交錯していたりするからである。
この交換関係の失敗や読みとりミス、勘違い、一方的な思いこみ、無知といったものがさまざまな人間関係のトラブルをひきおこしているのだろう。感情の貨幣というのはあまりにも一方的な思いこみ、一方的な取引関係というものが多いのは人間関係のさまざまな行き違いや錯誤からうかがい知れるものである。
われわれはこの取引関係の捉え方や行ない方を、その人の性格や人格、あるいは心理だと思い込んできたのではないだろうか。性格なんてものではなくて、感情の取引き形態をどのように認識しているかによって、その人の表われ方が異なってくるといえるかもしれない。
他人に期待した感情の取引きのありかたは、そのまま自分の心の基準である。この基準からズレたり、もれたり、予想外の行為が返ってくるのなら、われわれは悲しんだり、怒ったりするわけだ。「わたし」という人格は感情という貨幣をとおしたいっしゅの「個人企業」や「個人商店」そのものであるといえるかもしれない。
われわれはこの社会に生まれ落ちたときから、この感情のとりひき――人に苦痛を与えたら苦痛を与えられるものである――というルールを徹底的に親からたたきこまれる。親に怒られた子どもは、あやまったり、反省したりして、苦痛や苦悩という感情を末永く「所有」するように仕向けられる。こうしてわれわれは感情の取引関係に参入してゆき、個人商店の看板をかかげるようになってゆく。
しかしながら、感情の取り引き形態はさまざまな人間間のトラブルや苦痛や苦悩をひきおこしてきた。多くの宗教では感情の取引関係を否定している。つまり感情にはどこにも等価物なんかなく、また時間とともに消え去る虚構であるといってきた。感情は取り引きできるものではなく、また時間がすぐに消し去るものなのだということを諭してきた。なるほどまったくそうである。
心の平安、また人との平和な関係を築くには、感情貨幣の「個人商店」はたたんだほうがいいようである。だれかからうけた苦痛を報復や復讐というかたちで帳簿にのせておくのは、自分の苦痛の継続に一役買うだけだし、相手のトラブルをこじらせてよりいっそうの苦痛の拡大に加担するだけになるだろう。
ただ、被害や虐待を含むような不平等関係において、どれだけ取引関係を発動させないでおけるかはむずかしいところである。流れる川は同じ水ではないといわれても、この取引関係が今後も継続するとするのなら、わたしはどうしたらいいのだろう? ねえ、おシャカさん。
「感情商品」とマスメディア 01/2/12.
自分の感情や感じ方というのは自分の思い通りにならないことがままある。ときには自分の思っていることを裏切って、不安や悲しみに射すくめられてしまうこともある。
ではこのような感情や感じ方をかたちづくったのは何かというと、やはり子どものころに見たマスメディアが大きく作用しているのだと思う。私の感情の反応の仕方を大半影響づけているのはおそらくこれらのマスメディアだろう。
だから子どものころに見たマスメディアを見直すということは、自分を規定づけているものとふたたび対峙し直すということになるだろう。あるいは「他人によってつくられた自分の感情」をとりもどすきっかけになるかもしれない。
現代のマスメディア社会において感情はすでに「感情商品」や「中古品の感情」として大量に出回っている。われわれはすっかりその感情商品のパターンにはまり、無条件に反応づけられてしまっているというワケだ。
子どものころに見たマンガやTV、映画は自分にどのような作用を及ぼしているのだろうか。たとえば私にとって印象深いのは『ポセイドン・アドベンチャー』や『エアポート××』といった一連のパニック映画である。これらでは極限状況における自己犠牲を描いていて私はえらく感動したものだが、思いやりといった感情はこんなところでつくられたのではないか。
私には人より優越しようと見せたり、上下関係を誇示したりする気持ちに抑制が強いが、TVアニメなんかではけっこうエラそうにする人を批判するような場面があったように思う。冷酷であったり、鼻持ちならない役柄として叩かれていた。
逆にどんくさくて、デキが悪いほうがみんなの主人公である方が多く、はたしてこのような道徳律を組み込まれたわれわれは、この競争社会で足カセになるのではないかと思わなくもない。デキの悪い、ダメな人間の方が愛らしいが、そんな人間により同一化してきたことはよいことだったのだろうか。
自分の感情に抗えない最たるものは恋愛感情である。われわれは恋愛感情こそ自分の自分たるゆえんだと思っているが、はたしてそうなのか。「感情商品」によって刷り込まれたものではないのか。
この社会では「恋愛感情の商品」にはまず事欠かない。音楽であれ、マンガであれ、TV、映画、これらはほぼ恋愛感情を大量に売っている。この商品は今世紀の陰の最大のヒットだろう。はたしてこの恋愛感情の起源は子どものころに見た恋愛もののマンガではなかったのではないか。思い出せば、『キャンディ・キャンディ』――。
スポ根ものや学園ものはどのような感情や規範をわれわれに組み込んでいったのだろうか。『巨人の星』や『あしたのジョー』、『ゆうひが丘の総理大臣』『俺たちの旅』。情熱や感動――? あるいはカイシャでガムシャラに扱き使われるためのバッテリーみたいなものか?
『ウルトラマン』や『仮面ライダー』、『ガッチャマン』『ガンダム』のような勧善懲悪的なものはどうなんだろうか。ユング派によるとどうも「悪」は「自我」がなりたつために必要な過程であったといわれているが、われわれはおかげで立派な自我をもつにいたったのだろうか。
感情というのは自分独自のほかにはありえないものという感が強いが、じつは大半はマスメディアによってインプリンティング(刷り込み)されたものだといえる。ハイジャックされたようなものである。そしてそんなことをつゆとも知らず、刷り込まれた感情を自分独自のものと思いこみ、人生の判断をおこない、暮らしているともいえるのである。
マスメディアに操縦された感情のまま生きるのもそれはそれでいいだろう。それは商品であっても自分の好き嫌いで選びとってきたこと事実もあるからだ。
ただ自分の考えが変わったのに気持ちや感情がついてこないと感じたときには、自分のつちかわれてきた感情の起源や生成要因といったものを検討してみなければならないのだろう。慣習や規範、過去のメディアのドレイになるか、自由になるかは、自分の判断しだいだ。(そんなにかんたんには刷り込まれた感情や規範から自由になれるとは思わないが)
呟き断想集

答えのある生き方、答えのない生き方 01/02/25.
学校で習った知識にはかならず答えと正解があった。問題もはじめから用意されている。答えや正解はどこかにかならずある、大人や専門家が知っているとされていた。
こういう思い込みを、大人になってもずっともちつづけている人はことのほか多いそうだ。なにかわからないことがあれば、答えと正解をだれかに問えばいいと思っている。
しかし、そんなことがあるわけない。世界や人生には正解も正しい答えなんてものもない。わからないことだらけであり、そもそも正解や答えがあるのかすら疑わしい。はっきりいえば、そんなものはないのだろう。
答えや正解があると思っている人は、たんに他人がつくった既成の生き方や役割に慣らされてゆくだけである。答えや正解を真に受けるというのは、じつのところ、生き方を既成のパターンにはめこんでゆくことである。
いまの世の中には安定した会社に入ったり、サラリーマンとして勤勉に生涯を過ごすのが「正解」であるという考え方が確固としてある。世の中には「正しい生き方」があり、そこから外れたり、落ちこぼれたりしたら、「間違い」であると赤バツをつけられると信じられている。
戦後日本人の画一的な生き方は、正解と答えがあるという民主教育の結果でもあるのだろう。既成の正解と間違いが厳然とあると人々は信じてきたから、ひじょうにつまらない、小粒で、「正しい」人たちを大量に生み出してきたのだろう。
でも人生や世界には正解も間違いもない。そもそも人生に正解や間違いなんてあるものなんだろうか。世界や社会についての正解も、むかしの人々が考え出したひとつの解釈や考え方に過ぎない。世界や人生なんて無数に何相にも解釈できるし、人それぞれの価値観によって天と地ほども違う。
そういうことを伏せて、正解と答えを教えてきた教育やマスコミの功罪は計り知れないほど大きい。正解や答えを教えるということは、ひとつのものの見方に過ぎないものを、絶対や正統の名のもとに押しつける謀略である。
人生や世界には正解も答えもない。そもそも問題すらどこにもない。われわれの人生の途上というものは、いつでもナゾや未知に満ちたものである。答えや正解があると思った者は社会や慣習の都合のよい生き方にはめこまれてゆくだけである。
答えや正解はだれかに教えてもらうのではない。また問題もだれかに考えてもらうのでもない。問題は自分が感じ、発見し、生み出してゆくものである。
マスコミや教育に教えてもらおうと思っている人たちには、正解や答えはいくらでも与えられるだろうが、たぶんそれは自分ひとりだけのための問題でも解答でもないだろう。
人生というのは自分自身で問題を見出し、答えを切り開かなければならないものである。問題や疑問を感じ、解決しようとする力こそが人生に求められるものである。
失業は地獄か、楽園か? 01/3/1.
3月からまた失業です。今回は自分から辞めたのではなくて、事業所移転のためだから、なんとなく気持ちの整理がついていない。しばらくはのんびりしそうだ。
私にとっての失業は、なにものからも解放される気持ちのいいものだ。いつまで寝ていてもいいし、どこに行こうにも自由だし、だいいちしんどい目にもツライ目に会わなくてもすむ。最近は貯金がちょっと貯まることもあって、休暇は長期のものになりがちだ。
でもほかの人には切羽つまったものになるみたいである。生活できなくなるとか就職できなかったらどうしようとか心配がまず立って、いてもたってもいられなくなるみたいだ。
もちろん私もそういう気持ちになる。だけどそういうときにはなにも考えずに頭を空っぽにすれば、追いつめられた気持ちは去ってゆく。心のテクニックである。そのことを考えなければ、心はいつもどおりの平安を保っていられる。
マスコミでは山一証券とかそごうの失業者には決まって暗い影をまとわす報道をする。これらマスコミとか大企業の人たちは終身保証が当たり前の一本道の生き方が頭にこびりついているから、そこからの脱落は恐怖以外のなにものでもないと思い込んでいるだけだ。
中小企業とか転職を経験した人は失業はそんなに恐れることはないと知っているだろう。中小企業では中途入社や転職を経験した人が比較的多くいるからだ。まあ、そんなには珍しいことではない。
失業というのは心の持ちようしだいだ。地獄になる人もいるだろうし、楽園になる人もいるだろう。「あなたがたの心の中に地獄があり、天国がある」ということである。悲観とか先行き不安を心に抱かなかったら、こんなに自由で解放された長期休暇はないと捉えたほうがハッピーである。
解放されて、しばらく寝袋を抱えて紀伊半島でもチャリンコで一周してこようと考えていたのだが、3月上旬はまだあまりにも寒いし、天候もかんばしくない。寒空の下の野宿はちょっとこたえそうだ。読書でだらだらしようかなぁ。
ところで3月下旬にユニバーサル・スタジオが桜島にオープンするが、私はこの二、三年ずっと桜島に通っていた。西九条からの桜島線は昼には一時間に二本の電車しかなかったローカルな線路だった。ガイジンを多く見かけたり、がらがらだった電車が座れなくなったローカル線とももうお別れだ。
ここしばらくは仕事のことは考えないつもりだ。スクールに通おうとも思ったが、職が絶対に得られるわけでもないし、これから貯金で食いつなぐ身には痛すぎる出費だ。また、肉体労働とかバイトの職しか見つからないかもしれないが、まあそれもそれでいたしかたないだろう。仕事に生涯を捧げたくないと思った私が選んだ道なのだから。
海岸沿いのちゃりんこ野宿旅 01/3/5.
失業して長期休暇がとれたので、ちゃりんこで紀伊半島の海岸沿いを野宿しながら一周まわってこようと思っていた。寝袋だけなら、旅費はてんでかからない。ちゃりんこで10キロ程度は平気だ。和歌山の海岸線沿いの風景を楽しんで、串本と熊野あたりまで行けたらいいなと考えていた。
大阪の海岸線沿いはぜんぜんおもしろくない。コンビナートとか工業地帯ばかりで風景はなにひとつ楽しめない。浜寺公園は昭和のはじめころまでは海水浴のリゾート地だったらしいが、いまは工業地帯だ。海水浴ができるのは二色の浜以南だ。電車でしか行けないと思っていたので、ちゃりんこで到達できたときはちょっと感激。
関空のとなりにはマーブル・ビーチ(?)とかいって、コイの池に使うような真っ白い石をしきつめた人工的な海岸ができていた。趣味が悪い。だれが喜ぶんだろう。
大阪から岬公園まででだいたい40キロくらい。ちゃりんこで来れるとは思ってもみなかったところだ。5、6時間かかったのかな。子どものころに来たことのある加太の海岸線沿いをちゃりんこで疾走できたのはうれしかったが、アップダウンの激しい山道にはたいへん疲れた。
そろそろ日が暮れるころなので、今夜の寝床は和歌山市街に見つけることにした。寝袋で寝るのははじめてだ。寝袋で寝るのはけっこういろんな感情がいったりきたりするものだ。みじめさや気恥ずかしさもちょっとある。勇気がいる。
和歌山城の石垣のうえにいいところを見つけて、そこで寝ようとしたのだが、なかなか寝つけなかった。人に見られたりしたらいやだなとか、突風にひっぱられてびっくりしたり。こういう時ってけっこう大事なことが考えられたりするものである。
ようやくうとうとしかけたころ、雨によってたたき起こされた。駅を探すことにした。和歌山市駅で寝ようとしたが、ホームレスのおっさんがうろうろしていたりして、気が気でなかった。盆休みとかには旅行者も駅で寝ていたりして安心するのだが、この日はてんでいなかったので不安だった。
雨はてんでやむ気配をみせず、天気予報を聞けば、大荒れのようす。おまけに雪がふる寒気がやってくるという話。レインコートではぜんぜん雨を防げない。雨ばかり降っていれば、自由がきかないし、公園でも寝れない。もう断念して、帰ることにした。野宿旅なんか天候とのたたかいだといってもよく、もうすこし対策を練るべきだった。
雨に濡れてびしょびしょになるのはつらかった。気温もどんどん寒くなってゆくし。しかし孝子峠をこえて岬公園と行くにしたがい雨は小雨になり、関空あたりではほとんど空は晴れていた。でもびしょ濡れになったおかげでものすごく寒い。関空ゲートタワーであたたまることにした。なかに本屋があって、いつも本屋ばかり寄る私としてはひと安心。日曜だというのはここはがらがら。難波のOCATもそうだが、お役所のシゴトってお寒い。
和歌山までの片道でだいたい7時間くらいかかった。5、60キロくらいだ。マラソンなんか2時間ほどで42キロを走るのだから、驚くほかない。あっさり一日であきらめてしまったのは残念だが、3月上旬はまだ寒すぎるかもしれない。雨つづきの予報も気持ちを萎えさせた。晴れつづきのあたたかい季節ならよかったかもしれない。
もうすこし野宿旅について情報を仕入れておくべきだった。HPでいろいろ見てみたのだが、一冊マニュアル本みたいなものを見つけていたほうがよかった。HPでは下関から大阪までわずか5日くらいで行っているツワモノがいて、思わず私も行けるだろうとタカをくくっていたのだが、甘かった。
予定距離の五分の一も行っていないし、目的の南紀の海岸線もぜんぜん見れていない。またいつか再チャレンジに挑んでみたいと思うけど、シンドイなぁ〜。もう、へとへと。家はいろいろなことで安らげることを痛感したしだいだ。
物語を読むことについて 01/3/6.
最近の読書は物語を読むというテーマで読み進めている。TVドラマやTVアニメ、マンガ、映画などを社会学や心理学的にどのようなことを語っていたのか読み解きたいと思ったのである。
映画とかドラマの物語ってなにをテーマやメッセージにして語っているのかよくわからないことがある。そういう解説をした本を読みたいと思ったのである。
しかしお目当ての本を探すのにすっかり疲れきってしまった。TVアニメやTVドラマを学術的に分析したような本はほぼないのである。あるのはアニメ・オタクやドラマ・オタクのためだけの本のようなものばかり。そんなのを読んでも深い洞察力や分析力は身につかない。感嘆するような鮮やかな物語分析とも出会えない。
映画では女性学関係の分析とか、精神分析家による分析とかは何冊か出ていた。映画関係の本はたくさん出ているのだが、たぶん私の求めているものとは違うだろう。中学のときも私は映画の物語の意味を知ろうとして、映画雑誌を見てみたのだが、ほとんどアイドルあつかいしたスター雑誌だったりしてがっかりした覚えがある。
マンガに関してはマンガ評論みたいなものがあったりするようだが、入手が難しいうえ、社会とか時代の関わりが薄そうで、マンガ世界に迂遠しすぎているようで、読解してゆくのはしんどそうだ。
私はTV世代だから、子どものころに見たマンガやアニメ、またはTVドラマの社会学的、心理学的な意味やテーマを知りたいと思ったのだが、どうもまだまだ学術的なメスは入っていないようである。残念であるし、学者が解説・紹介するべきだと思うんだが、まだ時期が早すぎるのか、TV世代の学者が育っていないためなのか。
これらサブカルに比べて童話分析は驚くほど充実している。フロイト派、ユング派、社会史学派、文学者などが入り乱れて、膨大な物語解釈をほどこしている。ついこないだまで「コワイ童話ブーム」というのがあったが、学者による豊穣な土壌がつちかわれていたんだなと納得。
童話分析が楽しいのは、子どものころに親しんだ物語にオトナの目を通してもう一度触れられることと、物語の意味や解釈がはっきりと示されることにある。あ〜、こういうことをいっていたんだなと、鮮やかな物語開示がうれしい。
子供向けだからといってバカにはできない豊かな心理的意味が童話には含まれているのである。それならアニメやマンガにしても同様なはずである。
ただ童話分析っていろいろな解釈があまりにもたくさんありすぎて、どれを信じたらいいのかわからない。でもどんな物事も無数の解釈が可能であり、どれもがもっともらしく、真実に思える、というジレンマにもまれるというのが、現実のありようというものなんだろう。いやぁ〜、困ったものだが、おかげで現実とのつきあいかたも勉強できたというワケである。
マクルーハン覚え書き 01/3/8.
マクルーハンの『人間拡張の原理(メディア論)』(65年 竹内書店新社)を読んだ。ややこしかったり理解できない箇所もいくらかはあったが、私なりにまとめたいと思う。
ちなみにマクルーハンは昭和40年代くらいに竹村健一の紹介によりブームになったそうで、メディア論の古典だ。高くて手が出せなかった本を100円で見つけた。
メディアや道具というのは人間の身体の拡張である。たとえばハンマーやかなづちは手や腕の拡張であり、車や電車は足の拡張、家や衣服は皮膚の拡張、写真や活字は目、ラジオやレコードは耳、といったように。ちなみに蜂は植物の生殖器官である。
これまでの機械の時代には肉体を空間的に拡張した。しかし電信や電話、TVの電気時代になると外部拡張から、内部拡張へと変わった。身体の器官や部分の拡張から、大脳や神経組織の拡張になった。
機械時代をもたらしたのは、活字文化であり、印刷文化である。なぜならそれは画一性、同質性、反復性、連続性をもたらすからだ。ここが驚きであり、深く理解したいポイントだが、同じモノを複数コピーできるという技術が大量生産の思考へと飛翔していったのだろう。
国民が平等になるという共産主義もこの印刷文化に負っている。アメリカも画一的な規格品であふれているというということで共産主義であるともいえる。これもグーテンベルグのテクノロジーに内在する画一性と同質化の論理によるものだ。
印刷文化や文字教養は視覚を王座に据え、感覚を分離し専門化する断片的な関わりを要求するものである。そして一面の相、ひとつの見解に固執させるものである。文字は分割し、分節し、分離するものであり、全体の関与から引き離す。
それに対して電話やラジオ、TVは完全な参加や全面的な関与を要求する。文字教養人は感覚の統合に慣れていないので、全面的な注意に反発を覚える。全感覚を必要とするメディアの登場は、文字文化の画一性や反復性とまったく異なる嗜好や社会構造を生み出すだろうということである。
ほかにも鋭い指摘はたくさんあったが、私の頭を整理するために重要なところのみまとめてみた。印刷文化が大量生産をもたらしたというのは意外である。画一化、同質化の根源がそんなところにあるとは思ってもみなかった。
もうひとつ印刷文化による視覚の偏りには考えさせられた。あるいは言語−活字文化だ。これは聴覚や触覚などの感覚を排斥した断片的なものであり、関心の対象に全面的に関与できず、隔離させてしまうということだ。それに比べてTVや電話は多くの感覚を関与させ、ほんらいの人間の活動により近づくというわけだ。
私はTVや映画で育ち、活字を読めない時期があったが、いまは活字のほうが好きである。言語ほど物事の構造を明晰に切り分けて見せてくれるものは、テレビや映画にはないと思うし、けっして劣っていないと思うのだが、たしかに感覚の全体関与というのも重要だと思う。目や耳を切り離したメディアのために人間ほんらいの全体性を喪失させられたもいえるからだ。
この本の中でいちばん気にかかったことは印刷文化−活字文化と画一化−均質化の関係であり、そのつながりをもっと深く理解したいと思った。あと、感覚の統合・全体性は無意識や超越的合一と結びつけるものなのかと気になった。
不完全なメディア 01/3/10.
メディアはいつだって不完全なものである。目に特化したメディア、耳に特化したメディアをつくりだし、全感覚を疎外、分断してきた。あるいは認識のありかたをゆがんだものにしてきた。
たとえば言葉である。言葉は線的で、連続的で、時差的な認識をつくりだした。意識や感覚は一瞬にして全体的に把握するが、言葉はほんのわずかな一側面を線的にじゅずつなぎ的に、時間的にものごとを把握させる。一瞬にして把握した風景は、言葉では順番に時間的にそれを口述あるいは記述しなければならない。
活字や印刷本は、聴覚や触覚を疎外し、遮断する。視覚に集中するさいにはそれらは不要である。印刷本は身体感覚を排除して、感覚の全体的な把握を拒む。
本に集中するためには物音さえ邪魔である。私は本を読むときにはラジオの声さえ邪魔だし、邦楽も歌声や歌詞が気になって集中できなくなるし、せいぜい洋楽かイージー・リスニングを流す程度がちょうどいい。逆にある一冊の本にはそのとき聴いていた音楽の記憶とわかちがたく結びつくということもよくある。
ラジオやCDは聴覚に特化したメディアである。視覚が排除されている。かつて音楽を聴くときにはナマで聞くのが当たり前であり、歌い手の顔や表情、身振りなどを直に見ることができた。
ラジオやCDばかり部屋で聴いていると、視覚が排除されているのでたとえばアメリカのMTVなんかではじめて歌手の顔や体格を見て驚いたりする。私はコンサートに行くより部屋で聴くのが好きだが、多くの人は生身の歌手やからだごと音楽に包まれたり、ともに踊ったりするのが好きなようである。つまり耳だけではなく、全感覚で音楽を感じ、からだじゅうで踊りたい。
電話も耳に特化したメディアである。相手の顔も表情も、身振りも、場所すらわからない。あとは想像になる。顔も表情もわからないこそ、伝えやすいこともあるが、逆に電子メールのように顔を知りたくなるということもあるし、不安な場合もある。
TVは目と耳、あるいは諸感覚を統合するメディアである。情報量は印刷本やラジオよりはるかに多い。多くの感覚を動員するために、視覚を中心とする読書の狭められた感覚には合わない。だからTVで育った子は活字や教育になじめない。
これまでのメディアというのはひとつの感覚に特化し、ほかの感覚を遮断するため、想像力による補強を必要としてきた。ほかの感覚が遮断されるからこそ想像力が飛翔し、そのために楽しみや喜びが生まれたり、隠れたり、姿を見せないで表現することも可能になった。
人間はだいたい対象を全感覚で把握したいものである。たとえば雑誌やTVによるグルメ情報ではたくさんのおいしそうな食べ物が紹介されている。これは知識を得ることで終わりになるのではなく、じっさいに食べ物の味覚を味わったり、五感で楽しんだりして、はじめてこの行為は終わりになる。旅行情報もそうである。写真や紀行文だけで満足するのではなく、じっさいに行ってみて五感で感じてきたい。
いっぽうアニメやアイドル歌手などは視覚や聴覚、あるいは想像力のメディアに閉じこもってそれのみで満足してしまうということもある。視覚・聴覚メディアができあがったおかげで、映像や声をながめたり、聴いたりすることで楽しみは終わってしまい、じっさいの女性との関わりを断ってしまうということも起こる。メディアの不完全さはいっぽうではそれに自足する人たちを生み出した。
メディアは言語もそうだが、伝達にはひじょうに優れている。しかし断片的で、細分化された感覚に頼るため、全体的で統合的な感覚や関与を奪いとってしまった。それが集合的無意識の幸福な合一からの疎外をもたらしたとベルグソンはいっているが、メディアによって分断された感覚の全体を埋め合わせようとわれわれは今日も消費やメディアにそれを求めるというわけである。
趣味人と仕事 01/3/11.
私が仕事を批判するのは、自分の好きなことや趣味ができなくなるからだ。自分の好きなことができない人生ってやっぱりつまらない。だから自分のために生きられない仕事は、私にとっては人生を剥奪するものなのである。
それなら世の中には趣味に没頭する人や趣味に生きる人たちというのはたくさんいるはずである。かれら趣味人は仕事のことをどう考えているのだろうかと気になる。かれらは仕事をやめて趣味に没頭したいとか、仕事は人生を奪う強盗のように思っているのだろうか。
趣味をやるにはお金がかかる。こんにちではどんな趣味も商業化が入り込んでいてしこたま金が必要になる。だからそのために働いている、仕事が楽しめる、我慢できるものになっているという人もいるだろう。
むかしは、あるいはこんにちでもそうだが、女という趣味のために金をかける人がたくさんいた。その延長には家庭や子どもやマイホーム、(あるいは愛人)があった。むかしは比較的こういう人がたくさんいて、それが世間の規範に叶うものであり、人生の常識でもあったのだろう。
しかしこんにちでは楽しみが他人を含むものから、自己完結型のものに変わってきた。個人主義的で、利己的な趣味に埋没するようになってきた。自分の楽しみが人とつながらず、自分のみの楽しみに終わってしまうものである。女とかセックスとか以外の楽しみがあまりにも増え過ぎたのである。
中高年には趣味がなくて、仕事だけが趣味という人がたくさんいるそうだ。かれらの時代には仕事以外の楽しめるものがあまりなく、あるいは経済成長がうまくいっているときであったり、貧乏で仕方なく働いているうちに仕事以外のなにものもなくしてしまったというのもあるだろう。こういう人たちはご勝手にそのまま定年までつっ走ってくれればいいのだ。
問題は趣味に生きたい人が仕事とどう両立するかということである。趣味をとことん楽しむためには時間がいくらでもいる。しかしそのための金も必要だし、生活するための金も必要になる。時間はほしいが、カネがなければ生活も趣味もできない。こんどはカネをたくさん稼ごうとすれば、趣味を楽しむ時間が奪われてしまう。ジレンマである。
解決するのは趣味を仕事にしてしまうことである。これはハッピーだろう。好きなことをできて、しかもお金まで稼げる。趣味人には理想の生活である。
ただこんにちの自己完結型の趣味では、他人のためのサービスである仕事から満足を得ることはむずかしいことである。自分の趣味と、他人へのサービスはやっぱり違う。仕事というのは他人に奉仕することであり、他人の楽しみを提供することであり、自分の楽しみとはやはりベクトルが異なる。またたいていの人は自分の趣味を仕事にできるとは限らない。
それでは趣味と仕事をきっぱりと分けて、あくまでも仕事は金を稼ぐための手段であると割り切ってしまうと、こんどは休みがとれなかったり深夜まで残業があったりして、趣味の時間が確保できなくなってしまう。こうして若いころ趣味があった人も長く会社に拘束されるうちに趣味なしの会社人間に育て上げられてしまう。アーメン。
だからげんざいの多趣味の時代には会社や仕事はもっとウェイトを減らさなければならないと思うのである。趣味に生きる人はもっと自分の人生を生きたいのである。また趣味に生きるというのは消費を華々しく行うということであり、この消費不況の時代では会社にとっても有益なことである。
日本人はもっと好きなように生きる人に寛容になったり、許容したりする意識や規範をもつべきなのである。さもないとつまらない大人ばかりになった社会は活力の枯渇を招き、けっきょくのところ、自国を崩壊させるのみである。
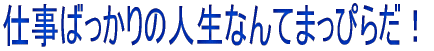
01/3/13編集
職業中心の人生観は終焉するのか? 00/11/26.
21世紀には今世紀までの職業中心の人生観は崩壊すると大胆にいいきった野田宣雄『二十一世紀をどう生きるか』(PHP新書)をよんだ。
私は現在のような職業中心の人生なんか生きるに値しないとは思ってきたが、この社会は職業中心社会のままぜんぜん変わらず、あきらめかけていたから、21世紀にそれは崩壊すると宣言したこの本にはおおいに好感と共感をもった。
かつての近代資本主義の時代では、一定の職業について勤勉に働くことが人生の義務であり、意義であると思われており、また人生の充実と幸福が手に入れられるものだと信じられていた。われわれのオヤジの世代はこういう信念にこり固まっており、その他の「流動的」な生き方は頑迷に否定するのが王道だ。この時代にはたしかにそれなりの見返りと充実が保証される時代経済があったのだろう。
しかし現在グローバル化と技術革新の波はすさまじく、崩壊する大企業はあとを断たず、安定と計画はのぞむべくもなく、人生は投機性と偶然性のつよいものにならざるをえないものになった。
このような時代にはかつての職業中心の安定した計画的な人生は立てることもできず、おおぜいの人はパートタイマー的な職業にとどまざるを得ず、したがって勤勉や忍耐が徳目でなくなり、「一億総中流」の時代は終わり、貧富の格差は広がり、貧しいその日暮らしな生活ながらも、人生を楽しむ日常倫理が必要となってくるということだ。
ふたたび江戸時代の町人のような暮らしがもとめられるわけだ。かれらは貧しいながら、日常生活を楽しむすべを知っていたし、その日暮らしの毎日を悔やむよりか、おおいに楽しんでいた。しかしその代わりにかれには民主政治は与えられていなかったし、階級社会だった。そんな時代が21世紀のわれわれの人生モデルになりそうなのである。
しかしすでに若者は片足をつっこんでいるといってもおかしくない。政治とか大きな状勢にはまったく無関心だし、刹那的な享楽を求めるし、勤勉な職業観をもっているかはかなりアヤシイ。あとは政治の道具をとりあげられる民主制の権利がなくなることと、貧富の格差とか階級社会という序列制度の経験があるかないかの違いだけだ。
おおむね私はこういう社会が来るとしても、楽観的に喜んでいるほうだ。職業に人生を捧げる一生なんかまっぴらだと思っているし、もしそれがとりのぞけられるのなら、貧富の拡大とか階級社会くらい大歓迎だと思っている。そのくらいの犠牲を払わないと職業人生からの脱却はのぞめないのであり、逆にいうと、民主制や平等は国家への自己犠牲がないと与えられないものである。二兎を得られない。
さて、はたして職業中心の社会は崩壊するのだろうか。これまでの勤勉な職業観から脱け出す気楽な人生観が、社会的容認や賛美を得るような時代に早くなってほしいものだ。そのためには貧しさと不安定という生け贄は不可欠だと覚悟しなければならないが。
労働のなかの自由か、労働からの自由か 99/10/15.
仕事とのかかわりにおいて自由はふたとおりあると思う。労働の中に自由を求める方向と労働から離れたところに自由があると思う考え方である。
仕事のなかに自由を求める者は出世して高い立場に立つことによって自由を得られると考えてきた。人に命令される服従ではなく、人に指図し命令する自由である。戦後の人たちはこういうことをめざしてきたのではないだろうか。またこれには消費選択の自由の増大もある。
近頃の若者に根強いのはやはり「クリエイティヴ」な仕事によって自由を得られると考えることだろう。ものを創造したり、デザインすることによって、機械や組織に使われない自由を得ることができると考えた。3K職種が嫌われたのはなにもキツイやキタナイからだけではないのだろう。
わたしが思うに出世で得られる自由は外から見れば、どう見ても企業組織という狭い井戸の中での自由でしかないように見える。またポストを得るためにどう見ても隷属としかいいのようのない状態に陥ってしまっている。わたしの自由の選択のなかにこれがないのはとうぜんである。
クリエイティヴのなかに自由があると思うのはわたしの中にもあるのだが、どうもたいがいの仕事はクライエントの意のままに従わなければならなかったり、ちっぽけな需要や要望を満たすためだけの仕事であったり、ここに自由があるかはだいぶ怪しい。趣味に逃げたほうが賢いかもしれない。
で、わたしは労働からの自由を求めたわけだが、ここにはとうぜん貧窮と不安定と不自由がある。さげずまれたり、みじめだと思われたり、身分的差別をうけたり、下請的待遇をうけたりする。この自由は社会的承認をうけていないから、よけい精神上にも悪い。
社会は労働からの自由をほとんど希求していなし、あるいは若者に現れるそのような現象を理解すらしていないから、法的保護や規制がほとんど行なわれず、政府の網の目からぼろぼろともれ落ちる行動を若者がおこす結果になってしまっている。
ひところ余暇論やレジャー論が騒がれたが、おかげで気違いじみた集団強制と強制的レジャーがまきおこった。平成不況はこれとは無縁ではない。自由への希望がとんでもない隷属、不自由に逆転してしまったことに恐れているのだろう。
自由に憧れた者は後ろ向きに落ちてゆきながら、労働からの自由に足をふみいれつつある。たとえば登校拒否やひきこもり、フリーター、失業、リストラによって、あまり褒められない自由を享受しつつある。これまでの常識では落ちこぼれと見なされたもののなかに、世間がポジティヴな自由を見出せるようになるのはいつのことだろうか。
「エリート幸福論」のあとにくるもの 99.10.8.
エリートになれば幸福になるといった神話の崩壊がしきりにささやかれているが、ひじょうにつくり事めいて聞こえる。すでに崩壊して久しいものを事後確認しているようなものだ。
ではそのあとになにがくるのかといえば、明確ではない。「有名人幸福論」といったものが世間では強そうだが、これに与かれる人はひじょうに少なくて、ひそかに不幸の蔓延を招いていたのかもしれない。われわれにできることは有名人の着ているファッションを身につけたり、動作や口調をまねたり、カラオケで歌ったりすることで満足してきた。
「有名人幸福論」を大衆化するためにひじょうに都合のよい技術がやはりできあがった。インターネットである。
エリート幸福論ができあがったとき、人々が学歴に殺到し、学校の義務教育化・大衆化がおこなわれたように有名人幸福論もその大衆化があとからやってくるのだろう。
しかしエリート幸福論が虚構であったように有名人幸福論もただの幻想である。その夢が醒めるまで有名になろうとする衝動はいつまでも覚めやらないのだろう。
われわれにほんとうに必要な幸福論というのは市井のなんにもない、ごくふつうの日常生活のなかに求められるべきなんだろう。そういった無名の人のなかに幸福を見出す技術をつくりださないと、「何々」になれないから不幸だという気持ちは拭い去れない。
無名のなんでもない人たちのなかに幸福を見出すということはひじょうに大切である。そういう人生の先輩としてひじょうに身近なところに親がいるのだが、われわれのたいがいは親を軽蔑して、親のようにだけは生きたくないと思い込むようになっている。
それがエリート幸福論や有名人幸福論の原動力や進歩主義のエネルギーになってきたのだが、おかげでわれわれはいつも不満と自己非難ばかりつづけて幸福になれない。
偉くなる人生より、楽しめる人生を 99/12/17.
戦後の教育の最大の失敗は、だれでもかれでも「偉くなれ」といってきたことにあると思う。「偉くなる」人生はいつも目的を先送りにし、多くの人を競争にまきこみ、偉くなれなかった百人中の99人を不幸と不遇に落としこんでしまう。
人生の価値と目的を狭いものにしたら、とうぜん多くの人はそこから漏れることになるのは当たり前のことだ。偉くなることを刷り込まれた多くの人たちは自らを慰める術をみいだせずに人生を不遇に過ごすことになる。
偉くなる必要なんかないのである。人生を楽しみ、大過なく過ごせれば、それで人生はハッピーというものだ。エリートになれなくたって、落ちこぼれたって、貧乏であれ、劣位や下層階級とよばれるものであっても、ただ生きていることだけ、存在していることだけに自分の価値があると思えれば、ほとんどの人はハッピーである。
しかし偉くならなければ生きている価値がないと教え込んだ教育と社会はとうぜんのことに大半の人の生きる価値を削ぎ落としてしまうことになる。はじめから人生の価値を局限してしまうわけである。こんな社会はとうぜんのこと、みずからの生きている価値も意味も慰めもみいだせない大量の人を生み出すだけだろう。
だから社会はただ生きていることだけに価値を見出せるのなら、多くの人は救われるだろうし、ハッピーになることだろう。偉くなれない自分を責めたり、苛んだりすることはないだろう。そういうふうになると社会はもっと生きやすくなる。
自由競争と立身出世を否定した現代社会 2000/2/20.
「現代という時代は、巨大な「組織と管理の時代」なんだということができるとおもいます」――これは梅棹忠夫のことばである。(『わたしの生きがい論』)
「ほんとうに皮肉なことだとおもうのです。自由競争を目ざして立身出世街道を驀進した民衆のエネルギーが、結果としてきずきあげたものはなんであったかというと、まさにそういう自由競争と立身出世を否定するような、巨大な官僚組織であった」
このことばにはがつんときた。けっきょくのところ、現代社会あるいは現代の組織というのは、明治のころに可能であったり、現実の夢としてあった自由競争や立身出世がまったくできない世の中になりつつある――あるいはもうすでにそのような形に完成してしまったのかもしれないのである。
これだったら、まるで封建社会の大悪人だった江戸時代とまったく同じ状態に帰り咲いたということになる。つまり現代というのはもう暗黒の江戸時代に片足ばかりか、頭までカンオケにつっこんでいるということだ。
おまけに現代は歴史で習ったような暗黒の江戸時代とはまったく違うんだというおめでたい認識がまかりとおっているのが現状である。学歴競争でわずかな夢を垣間見ることができると思い込んでいるし、学校ではこの社会は民主主義と自由と平等の社会だ、悪役の江戸時代だとは違うんだと、学校の教師にウソの仮想現実をたたきこまれてわれわれは社会人になる。
じつは現代は江戸時代よりヒドイ拘束と不自由の社会かもしれないのだ。自由と平等の社会といっても労働と会社に大半の人生を搾りとられるし、会社のなかに平等なんかあるわけない。社長や上司が新人やヒラと平等であるわけがない。江戸時代は身分差別社会だったということだが、会社の中でも会社同士のランクでもしっかりと身分差別制度ができあがっている。
斬り捨て御免とか圧制とかがあったということだが、現代でも民衆が政治を動かしているとはとても思えない。権力とか利益団体の意のままに操られて、民衆の手の届かないところにあるのが政治だ。現代というのは、歴史の教科書で習った以上の封建主義社会、江戸時代のすがたになっているのかもしれない。
立身出世だとか自由競争だとか、民主主義、自由と平等の社会という理想的な虚妄の認識をあらためて、この社会は暗黒の江戸時代と同じであると認識したほうがはるかに世の中の仕組みを理解しやすく、妥当であり、生きやすくなるのではないだろうか。
暗黒の江戸時代という認識から出発して、もう一度立身出世が可能になるような明治レヴォルーションを起こすか、それとも現代社会に適応すべく老荘や仏教の処世術を身につけるべきなのだろうか。
明治の立身出世をめざすようなものは現在では情報産業などがある。ぽつぽつと大金持ちも夢ではないというような起業家の夢も芽生えはじめている。
それともあきらめて社会や世の中を変えるより、自分の心の姿勢のみを変えようとする老荘や仏教の現状維持的イデオロギーに身をまかすべきか。ウォルフレンはこれを「敗北者の思想だ」といった。しかし変えようのない社会に憤るより、心の平安と体制順応に暮らすほうがはるかによい生き方ができるかもしれない。
歴史観も変える必要があるのだろう。われわれの知っている歴史観は革命家や立身出世主義者にとってのご都合歴史イデオロギーである。だから江戸時代は悪役になった。庶民の知恵にとっては江戸時代の怠け者でも、ぼんくらに生きててもよかった時代のほうがよかったのかもしれない。
えらくなれ、役に立て、という革命家の歴史観は庶民の心を強迫観念や自虐観に駆り立てる。現代はそういう大衆強制と、じつのすがたは封建江戸時代、というどっちつかずの状態だから、われわれはいろいろ苦しんだり、悩んだりしているのだろう。歴史はひと廻りしたのである。どちらのほうがいいのだろうか……
□封建社会をみなおすブックガイド
呉智英『封建主義者かく語りき』双葉文庫
石川英輔『大江戸生活事情』講談社文庫
中川八洋『正当の哲学 異端の思想』徳間書店
自由と企業の地位序列 99/12/31
.
自由には憧れるのだが、職場での地位が低い人を軽蔑して見てしまう。サラリーマンにはなりたくないと思っていたのだが、まじめにきちんと働いてきた人を評価してしまう。服従や隷従する人たちを軽蔑してきたのに、まじめな勤め人はエライと思ってしまう。過去になにをしてきたかわからない人や仕事があまりできない人は低く見てしまう価値基準が自分のなかにはある。
つまり自由な生き方の基準より、企業の人間評価のほうが優っているということである。企業のなかで人と出会うと決まって企業内評価と同じまなざしで人を評価し、見下してしまう目が自分のなかに根をおろしているというわけだ。
愕然としてしまう。自由な生き方をしてきた人はとうぜん企業内では評価も低く、劣等な地位におかれることになるのだが、自由に憧れる自分もそういう企業内評価のまなざしで人を序列づけているのである。自由な人というのは、きちんとした企業ではとうぜん軽蔑して見られる。そういうまなざしが抜きんがたく自分のなかに定着している。
わたしは服従や隷属を嫌い、自由な生き方をのぞんできたはずなのだが、サラリーマンの人物評価がしっかりと自分のなかに根をおろしてしまっている。企業内評価の低い人を軽蔑して見てしまう自分には驚くと同時に自分のモノサシの甘さには愕然としてしまう。
軽蔑するのは自由なのである。そしてそれは仕事ができないことや、あるいは仕事に定着しないこと、社内で低く見られることなのである。裏返せば、これは人間としての自由をもちあわせていることになるのだが、そういう自由を軽蔑してしまっている自分がいるわけだ。
これでは自由の息の根をとめているのと同じだ。企業での低い立場の人を軽蔑して見るということは、自由を抹殺していることと同じだ。一方では自由をほめ、その裏では自由の首を絞めているようでは、とうぜん自由なんかにはなれない。
こういうまなざし、評価基準には警戒することにしよう。自由と地位の低さはコインの表裏なのである。地位の低い人を軽蔑して見れば、自由を否定することになる。企業での低い立場にいる人を軽蔑して見るようなまなざしに訓化されるようなことは避けたいと思う。そのような評価基準で人々を判断してしまう反射性を警戒しよう。
自由のモノサシは企業のモノサシとまったくひっくり返るものだ。企業での低い評価は、自由のモノサシでは高い価値をもつものである。この転倒を忘れるようでは、みずからの自由の首を絞めているようなものだ。
ただ企業の集団の力というのは強い。弱いところにはいじめのような構造がかかる。だから人はそれを恐れて集団内での価値基準を自分のものにしてしまう。こういう力の構造があるから、人はこぞって企業の評価をみずからの内にとりこんでしまう。自由というのは、集団の力との闘いかもしれない。
「老後恐怖症」の洗脳と拡大 01/1/14.
あえて「老後恐怖症」と意地悪に命名させてもらおう、なんでも「ビョーキ」にしたがる心理学者みたいに。
われわれはみんな「老後恐怖症」にかかっている。就職や結婚をすすめるさい、だれもが「老後はどうするんだ」とか「老後一人はさみしい」だとかいって、不安からそれらを強制する。十代や二十代の若者からして、あと三十年も四十年も先の老後から現在の選択を迫られているのである。かなりイジョ〜でビョ〜的な事態である。
たしかにこれはしごくもっともな「心配」かもしれない。「現実」に懸念されるものである。現実には存在しないと思われる恐怖に囚われる「恐怖症」の範疇とは違うものかもしれない。
しかし何十年も先のことがだれにも予測できないように、老後のことも予測できるわけがない。目の前に現存する不安や心配と違うことからして、過剰でオーバーな恐怖ともいえる。
これまでは「予定調和」の時代だった。学校を卒業して就職して課長部長と出世して定年退職を迎えるといった人生が、ある程度無難に送れると予測できた時代だ。だからいまの若者も人生のはじめから老後と現在をセットにする考え方を植え込まれていた。
未来や将来から逆算する人生計画が当たり前のようにわれわれの頭に根づいた。これは国民年金や企業年金、健康保険などの老後保障が生まれたときからあったせいである。
むかしの日本人や現在の世界の大半の人々は「今日食うや食わず」の生活をしており、明日の心配や保障なんかできないのが当たり前だった。
200年前の産業革命、100年前のマルクス主義から事情は変わる。国家や企業が老後を保障するという思想と制度ができはじめる。人生は生誕のときから老後を守られ、計画されるものとなり、同時に人生は老後から束縛され、拘束されるものになった。
食うや食わずの人に将来の保障がないわけではなかった。家族や親類、地域社会などの福祉があった。しかしその福祉を国家や企業が担うことにより、家族福祉は崩壊してゆくことになる。
ソビエトでの社会主義が崩壊したようにこれから世界での社会主義的発想というものもどんどん崩壊してゆくものと思われる。ふたたび市場主義の発想に戻りつつあり、しかし豊かさは以前と比べて破格に高くなった時代であるが、エスカレート式の市場拡大が見込めた時代は終わろうとしている。
このような時代の老後逆算の人生はどのような運命をこうむることになるのだろうか。生まれたときから老後を守られていた若者は、逆に老後から拘束される人生を嫌う者も増えてきた。
計画人生はこのまま延長することができるのだろうか、それともどこかでぽっきりとハシゴを折られることになるのだろうか。老後保障は少子高齢化によって財政的に破綻しつつあるし、市場の変貌はかつての計画人生を不可能なものにしつつある。
このような時代に老後から発想する人生はただの「老後恐怖症」で終わることになるのか、それとも堅実な人生計画としてまっとうできるのかは今のところわからない。
ただ気分としては、現在を老後から発想する逆算法はどうもフツーではない気がする。人生は老後を守るためだけに存在しているというのはどうもおかしすぎる。
2001年春のオデッセイ

昔話と子どもの自立、大人の自立 01/3/14.
昔話を子どもの自立の話だと解釈すれば、あざやかに物語が見えてくる。松居友の『昔話とこころの自立』(99年 洋泉社)は目からうろこが落ちるような本だった。
たとえば『三びきのこぶた』である。三匹のこぶたが狼に食べられそうになって、家をつくる話である。家をつくるというのは自立を意味する。ワラや木でつくった安易な家=希薄な自立心では狼に食べられてしまう。レンガの家をつくって食べられなかったぶたは自立心をちゃんと育んだということである。
『ヘンゼルとグレーテル』は貧しい親に捨てられた兄妹が森の魔女に食べられそうになる話である。魔女というのは自立を阻む母親のことである。
『三枚のお札』は小僧が和尚にもらったお札で山の鬼婆を追い払う物語である。鬼婆は弱さで子どもの自立を阻もうとする日本的な母親のすがたである。三枚の札はそれぞれ山、川、火となって鬼婆の追跡をかわすが、母親の執着はそれだけ凄まじいということである。
『白雪姫』は子育てに人生を捧げ、容色が衰えてゆく母親の若い娘に抱く憎悪のなかで娘はどう自立をなしとげてゆくかという話である。若さに憎悪を無意識にでも抱かない母親はいないといってよく、子どもにとって母は魔女であり鬼婆である一面をもつわけだ。
昔話が子どもの自立のステップをうたっていたとは驚きである。魔女や鬼婆が子どもの自立を阻もうとする母親の否定的な面であるというのも知らなかった。
それらは外側の他人でもあるが、自分の内面にある自我の確立を壊す破壊力でもある。自分の内面の破壊的な感情の象徴や外部化でもある。だから魔女や鬼婆はやっつけなればならない。残酷でも攻撃的であっても悪役をやっつけないことには、みずからの自立を阻む心や攻撃欲をコントロールできない大人になるというわけである。
過激なマンガやファミコンの熱中は、学校などで大人にいじめられているうさを晴らそうとしているということだ。大人に向かう憎悪を悪役をやっつけることで晴らし、またその心を飼い慣らす過程でもあるということだ。
昔話で語られる自立を果たそうとする子どもの心の葛藤はひじょうに印象的であったが、大人の子どもからの自立も心に強く心に残った。親はいつまでも子どもを自分の手においておきたいもので、それは魔女や鬼婆として描かれるものである。
子どもの自立はまさに親自身の自立の闘いでもあるのだ。『三枚のお札』の鬼婆は自立できない日本的な母親を象徴していて、真におぞましいものがあった。親は鬼婆や魔女としての自分の心ともういちど対峙しなければならないのである。昔話にこんな大人の自立をうながそうとするメッセージが込められていたなんて思いもしないことだった。
親は子どもにやっつけられることによって、はじめて親子ともども自立をなしとげる。そういうことを語っていた昔話というのは偉大な知恵が込められていたんだなと改めて思う。
自分の心を他人に見る 01/3/17.
いま童話解釈にハマっているが、心理学的な解釈によると童話の登場人物はおもに主人公の心の要素だと見なすのが一般的なようである。
たとえば鬼や悪魔は子どもの心の中にある破壊的で暴力的な気持ちであったり、鬼婆や魔女は子どもの心の中にある自立を拒む気持ちの象徴であったり、言うことを聞いてくれなくなった否定的な母の姿であったりする。
心を外面化、人物化しているわけである。人物やバケモノに象徴される心の衝動は、だからこてんぱんにやっつけなければならないわけである。それはじっさいの外界の人物を暴力的にやっつけているのではなく、自分の心の破壊的な衝動を治めているのである。
物語はこのように読むようである。外部の物語に見出すものは、みずからの心のなかの否定的であったり、どう扱ってよいかわからない心の衝動であったりするのである。子どもは外部の物語に、自分の心の中の一部を発見するわけである。
また悪役は自分にとっての身近な脅威や敵であり、それをやっつけることによってストレスを発散するということもある。身近な敵というのはいやな両親や大人であったり、教師であったり、嫌いな友達であったりするのだろう。心の一部は無意識のうちに醜い人物へと凝集されるのである。
子どもたちは外部の物語に自分の心を見出す。でも大人になってもこれは変わりはしないのだろう。外部に自分の心を見出すのである。そしてたいがいの人は他人に、自分の心を見出しているということに気づかずに大人になる。
自分の心を外面化していたり、人物化しているということにはかんたんには気づけない。他人は自分が思ったり、感じたり、見えたりするそのままに存在しているように思える。そこには判断したり色づけしたり自分の心が当人には見えない。
子どもが心の一部を物語に見出したように、大人も他人や世間に自分の心を見出すのである。そしてこころの投影に気づかない。それがぜんぶ自分の心に発したものであるということに気づかない。心の存在はそれだけ見えにくいものである。
世界に広げっぱなしにした心の網は、コンパクトに心の中に収めることも必要である。外部や他人に自分の心を投影しつづけていると、他人や外界のモノを動かし、支配しなければ心の安定は得られないと信じつづけることになるからだ。これはたいへんな災厄であり、成功することのない徒労である。
他人や外界に見えるものが自分の心だと気づけば、支配すべきものはひじょうに小さなものになる。他人や外界のモノを動かす必要はない。ただ自分の心、他人や外界に投影されていた自分の心のみを治めたらよいことに気づくわけである。
童話の心理学的解釈はおもしろい 01/3/20.
童話の心理学的解釈の本をいくらか読んだので、なにかを書こうとしてもすごく難しい。ユング派とフロイト派の違いについて比べようとしても、てんで頭の中でまとめることができない。解釈の要点をここに載せるより、じっさいに読んでもらった方が数段楽しいと思う。
童話解釈なら河合隼雄の文庫本がたくさん出ている。『昔話の深層』とか『ファンタジーを読む』(講談社+α文庫)とか。この人はユング派で、ほかの童話とか神話の比較や象徴とかがだいぶ出てきて話がややこしくなるのだが、本家のフォン・フランツよりだいぶマシで楽しめる。
松居友の『昔話とこころの自立』(洋泉社)は、自立という切り口で昔話を読み解いていて、理解が俄然ひらけた。ユング派の影だとか個性化、元型とかの概念が出てきたら頭がこんがらがるけど、自立の話だと見なせばひじょうにわかりやすい。
フロイト派のブルーノ・ベッテルハイムの『昔話の魔力』(評論社)は童話解釈の金字塔とよばれるだけあって、さすがにすばらしい本だ。まいどおなじみのエディ・コンとか性的解釈は多いにしても、昔話の効用や必要性などが説かれていたり、物語分析もどこをとっても重要な警句や指摘に満ちている。
森省二という人は『名作童話の深層』とか『アンデルセン童話の深層』(創元社)でポピュラーな童話解釈をしていて楽しめる。
政治学からの解釈として、フェッチャー『だれが、いばら姫を起こしたのか』(ちくま文庫)がある。あ、そうか、童話というのは保守的な生き方を刷り込ませるものだということに気づかせてくれたし、童話は資本主義とか政治的観点からも推察すべきものだとたしかに思わせるものだった。
歴史学からは森義信という人が『メルヘンの深層』(講談社現代新書)からおこなっている。童話の主人公たちは犯罪者や殺人者、略奪者であるといううがった洞察は、たしかにそういう一面から人間の本性を理解することも必要なのだろう。
グリムとかペロー、アンデルセンなどの西洋の童話ばかり読んでいたら、日本の昔話も読みたくなる。河合隼雄の『昔話と日本人の心』(岩波書店)がある。なんかひじょうにややこしい日本人の自我のありかたを検討した本だが、日本によくある動物の嫁さんの正体がばれて去ってゆく話は印象的だなぁ。
だいたいこんな程度読んだが、あと、いろいろな学説を総合的に検討したマリア・タタールとか、フェミニズム的観点から読み解いた『眠れる森の美女にさよならのキスを』なんか読んでみたいな。ほとんどの本は古本屋で探し回って仕入れたのだが、なかなか見つからないな。
心理学的解釈は積年のうらみ(?)である物語の意味を明確に指し示してくれて感嘆と驚きの連続であり、心理的成長とはなにかとひじょうに気になるのだが、物語の教訓やイデオロギーにそのまま訓化されるのもやはり問題だと思う。物語べったりの解釈ばかり頭に仕入れたから、こんどは批判的に読み解く視点もぜひとも必要だな。
古本屋行脚 01/3/21.
古本屋めぐりは労多くしてあまり得ることの少ない疲れるものである。地理的にもばらばらである。めあての本を探していて、ぴったり見つかることはそうない。
ただ、さいきん童話の心理学的解釈の本を探していたら、コワイ童話ブームのあとだったからか、主要な本をほとんど見つけることができたし、新刊書店で見あたらないものも見つけることができたので、たいそうありがたかった。
古本でいちばんありがたかったのは、ドラッカーの本を半額で仕入れることができたこと、フリードマン『選択の自由』、マクルーハン『人間拡張の原理』を100円で手に入れることができたことだ。いずれとてもよい名著であり、前々から手に入れたかったものであったりしてカン・ジュースなみの値段で手に入ったのはめっちゃラッキーである。
ついでにブルデューの『ディスタンクシオン』とかドゥルーズ=ガタリの『アンチ・オイディプス』『ミル・プラトー』も100円でワゴン・セールしていたらいいんだけどなぁ。。夢かな。
ビジネス書は二千円の価値はない。あんな薄っぺらい本は文庫本ていどの価値しかないと思う。文量が少ないのだから、それは推し量るべきだ。
ここ大阪には大きな古本屋街みたいなものはない。せいぜい梅田のかっぱ横丁とナンバの球場跡(いまは南下してある)、日本橋に何件か固まっているだけである。
メガ書店で肥えた目にはやはり不満である。おめあての本があるときはなかなか見つけられないし、ほしい本が定まっていないときはなおさら疲れるだけだ。たしかに安く仕入れられるのはとてもありがたいが、新刊書店のようにジャンルごと揃っているということが少ないので、やっぱり探し疲れということになってしまう。
さいきんは郊外にできているブックオフとか古本市場という大型店には驚かされるものがある。あんなデカイ店ならおめあての本はいくらでも見つけられると期待するのだが、残念ながら私の好きな人文書とかの専門書は除外しているみたいだ。マンガが好きだったらこんなありがたい古本屋はないだろうし、ビジネス書や小説、文庫本も充実しているのだが、専門書めあての私はがっくりだ。
インターネットの古本屋は私のパソコンが古すぎて時間がかかりすぎるのが耐えられないし、やっぱりじっさいに中身をたしかめないことには選ぶことなんかできない。いまのところ、ラファルグの『怠ける権利』という本だけはネット古本で見つけたいとは思っているが。
まあ、これからも新刊書店と古本屋を適宜つかいわけてゆきたいと思っている。ブックオフも専門書をあつかうようになってくれたら、うれしいんだけどなぁ。それとも新刊書も価格破壊してゆくべきなんだろうか。このままでは古本の大型店に太刀打ちできないんじゃないかとも思うけど。文化は市場原理で守られるのか、それとも護送船団かな?
自分のなかの残酷さや残虐性 01/3/22.
ひところ、純真無垢と思われていた童話は、じつは残酷な話のオンパレードであるという暴露本が流行った。なんでこんなものが流行るんだろうとそのときは思っていたが、遅ればせながら童話の心理学書を読むようになってちょっとはわかった気がする。
心理学者によると、童話にたびたび出現する鬼や悪魔は子どもの心にある攻撃性や残酷さが人物化されたものであるという。子どもというのは思ったより攻撃的で残酷なものである。でも子どもはそれを親にも大人にもぶつけることができないから、童話のなかの悪魔や鬼にそれを仮託せざるを得ないし、またそれを成敗することによって自らの攻撃欲をコントロールすることになるということである。
残酷さは子どもの心の投影であり、それをどうあつかってよいかわからない子どもは残酷な童話によってそのあつかいかたを学ぶというわけである。だから食べられたり、殺されたり、目ん玉をひんぬかれたりする罰則が、象徴的に必要というわけである。したがって童話は残酷で残虐性のオンパレードである。
しかしわれわれの時代というのは残酷さや残虐性を極力、人々の目から遠ざけようとする社会である。とくに子どもにたいして、そういう攻撃性から目を覆ってやることによって子どもはその残虐性の影響から逃れられるだろうと思われている。狼に食べられるぶたは最期には狼と仲良くなりましたという話で粉飾される。これでは子どもはみずからの攻撃欲をどうあつかったらよいかわからないまま、とり残されることになる。
心理学的な解釈ではこうなるけど、歴史的にいえば、昔話ができたころの人々というのはすこぶる残虐だった。自然や経済、飢餓などの状況が、やさしさを許さない時代でもあった。子は捨てられ、または成人するまでに死に、魔女狩りなどで殺され、あるいは短い寿命で終わり、飢饉、ペストなどでばったばったと人が死んでいった。残酷さや残虐さは時代の条件でもあった。昔話の残虐さがじっさいの人間とまったく違っていたというわけではないのである。
それに比べて現代は自由や平等、博愛が説かれるように、思いやりとかやさしさの時代である。攻撃性や残虐さは社会の表面から葬り去られたかのようである。子どものときには残虐さから目を覆われ、攻撃性はたちまち切り落とされ、やさしさや思いやりだけが人間の全人格であるかのように教育・訓化される。
残酷な童話ブームは行き場を失った攻撃衝動の発露であるといえるかもしれない。その前にはひたすら猟奇殺人者の心理分析といったテーマが流行ったが、人はみずからの頭がもたげてくる攻撃衝動(あるいは自分の内にあるかもしれないもの)とどう向き合ったらよいかわからなかったのかもしれない。
穏やかで、思いやりがあり、やさしさで塗り固めた時代というのはやっぱりウソである。攻撃性や残虐性が社会の表面から拭い去られた時代というのはたしかにすばらしい、理想かもしれないが、人間の表面からそれがいくら隠され、隠蔽されようと、やっぱりわれわれの心の内に攻撃性は潜みつづける。子どもに残虐さがないと信じられるのは学校の教師か家庭のオバチャンくらいで、世の中というのはひどい残酷性に満ちている。
問題はそれがあることを認められないことだ。あってはいけない、あるべきではないと意識から隠してしまおうとすれば、神経症的な問題がおこってくる。性的抑圧が厳しすぎる時代にフロイトが意識下の性的欲望を暴露したように、目に見えるところから隠してもむだなのだろう。
攻撃性が隠されたやさしさの時代はアダルトチルドレンのような奴隷的な関係をつくりだしたし、内閉的な傾向もそうだろうし、攻撃衝動がコントロールできない子どももつくりだしてしまうのだろう。
わが内なる攻撃性や残虐さを認めて、それをとりあつかう知恵と勇気を養う必要があるようである。どんな人の心の中にも攻撃性や残虐さは必ずある。否認するわけにはゆかない。
『カバチタレ!』ほかのドラマ評 01/3/27.
『カバチタレ!』は一回目がダントツにおもしろかった。芸者宿に売られそうになる常盤貴子を代書屋が助ける話である。代書屋というのは行政書士であるそうで、資格の講座で知っていたが、法的な立場でそんな強い力をもっているなんて知らなかった。
人を信じることや、正義はだれのためにあるか、法的な力で窮状から脱け出すノウハウ、といったテーマが語られていたように思う。一般の人たちが法律の力を得る、あるいは知るというすこし啓蒙的なドラマであったかもしれないが、私としてはたいへんおもしろかったし、ベンキョーになった。
一般の人たちにとって法律というのは遠い存在であり、自分を守ってくれるものであり、また自分の味方につけられるなんて思ってもしないことである。これでもわれわれはほんとうに法治国家に住んでいるといえるのか? 法的な権利が与えられているといえるのか。会社のなかの人権なんかほぼないも同然だし、憲法番外地であるのはまがいない事実である。
法的な力がコンビニのようにわれわれの日常でかんたんに手に入れられるようになればいいと思うのだが。個人がそのような法的な力をふだんから意識できるようになることが、いまの日本に求められているのかもしれない。
親のない親戚のたらい回しの少女時代とか、暴力夫から逃れる妻とか、トラック運転手の権利のなさとか、このドラマにはちかごろのドラマがとりあげようともしない、日常の深刻で悲しい現実が刻み込まれていたことも好感がもてた。ドラマはちゃんとこのような現実を描けと思うのだが、まず人気が出ないのはまちがいない。現実の日常を描こうとした『彼女たちの時代』はたしかになんにもなく、つまらなかった。
『ロケット・ボーイ』もふつうのサラリーマンを描こうとして、見事につまらなかった。現実を描く必要性はあると思うのだが、だれもドラマの中に現実なんか求めないのかもしれない。現実は誇張されたほうがいいのか。30代男は現実にあきらめを見つけてゆくといだけの話だったのか。
『女子アナ。』はなかなかよかった。仕事のなかでの成長や勇気などが語られていた。ミーハーで軽薄な話かなと思っていたが、けっこう硬質な、つくりのしっかりした楽しめるドラマだった。浮かれた、空騒ぎだけのドラマではなかったのがよかった。
『ストロベリー・オンザ・ショートケーキ』の野島伸司はもうなにをやろうとしているのかよくわかんない。アバはなつかしかったけど、それだけ。『世紀末の詩』もジョンレノンの唄とともに印象深かったけど。
『HERO!』は平均視聴率をつねに30%を超えていたというヒット作品だが、私にはひじょうにつまらない、見ていられないドラマだった。検察官があんなにヒーローぶっていて、天才ぶっているような話なんか見たくもなかった。キムタクが出ているだけで人気が出るということか。宇多田ヒカルの唄ももう少女チックすぎる。
パソコン浦島太郎 01/3/29.
私はパソコンの技術的なことには興味がないので、少々古いパソコンでも問題はないと思っていたのだが、さいきん(というか、かなり前から)、新しいソフトが入らなくなってきたのはたまらない。
エクスプローラーの新しいヴァージョンももうハードディスク容量不足で入らなくなったし、このHPをつくっているホームページ・ビルダーもだいぶ前のヴァージョンどまりだ。べつに私のHPは文章中心なのでそんなには困らないが、たくさんのロゴとかフォントを使えないのはかなり不満だ。
技術的なことにカネをあまり使いたくないというのがホンネだ。いぜんは技術的なパソコン雑誌も情報を仕入れるために買っていたが、さいきんはすっかり買わなくなった。コンテンツ情報ならほしいのだが、私の趣味に合った細分化された情報というのがまだあまり発達していない。
ちなみに私がこのパソコンを買ったのは96年の頭くらいで、メモリが8メガ、ハードが500メガくらいしかない。さいきんの主流はメモリで128メガ、ハードディスクで40〜60ギガだ。単位が違う。まあ、あっという間にパソコンは古くなってゆくのはわかり切っていることだし、なけなしのカネをはたいて買ったパソコンをお払い箱にするのはあまりにも気が引けるからそのままにしていたら、やっぱり困ったこともちょっと出てきた。
フォトショップとかイラストレーターのソフトを入れることができたら、もしかしてDTPとかデザイン系への仕事の道が開けていたかもしれないのに当然もう容量がない。ドリームウェーバーとかファイアーワークスのソフトがあったら、WEBデザイナーになれたかもしれないのに、ソフトを試してみることすらできない。宝の持ち腐れというやつだ。そして必要なときにはカネがないというやつで、ある程度は技術的なテンポにもついてゆく必要を感じた。
こんなパソコンだから当然ネットの待ち時間もかなりのものだ。気にしないふりをしていたらなんでもないのだが、やっぱりその遅さは情熱と楽しみと根気を削ぐのにじゅうぶんな役割を果たしているのだろう。
電話代節約のためにネットは一日一時間しかやらないと決めたことをかたくなに守っている。NTTの電話代はなんとかならないものかな。政府がIT先進国にするというのなら、まずこの料金の高さだろう。
NTTにしても、われわれはコンテンツを見るために回線を利用しているだけであって、電話回線を見るためにカネを払っているわけではない。NTTの料金はまずはコンテンツに支払われるべきではないのか。電話回線はもう舗装道路と同じように税金でまかなわれるべき段階に来ているのではないか。古い技術と頭はほんとに役立たなくなってゆくという時代であるわけだ。
ユニバーサルスタジオは映画に勝てない 01/3/31.
ユニバーサルスタジオ・ジャパンが大阪にオープンした。ジョーズとかウォーターワールド、バックドラフトなどのアトラクションはおもしろそうだし、たぶん人気は継続することだろう。こういうテーマパークをゼロから考えて、実際につくり出した人の偉業には賛嘆する。私がする仕事というのは右から左へ流すような仕事ばかりなので、こういうことをする人たちというのは、ほんと私と同じ人間がやっているんかなと思うくらいだ。
だがユニバーサルスタジオは映画には勝てないと思う。ああいうアトラクションとかショーというのは、映画の経験の質にはかなわない。映画は見せるところを見せて、話の筋にのせて、観客の心をぐっとひきつけ、離さず、没入させ、そのほかの経験から見事に切り離す。
でも人間の経験というのはもっと散漫なもので、注意や注目はあちこちに移り、いろいな経験や感覚が注目をそらし、重要なことや着目すべき点に目が注がれるとは限らない。映画やTVにくらべて、現実の経験はあまりにものっぺらぼうで散漫である。映画やTVは重要さや要点を「編集」しているがゆえにたいそう劇的で、刺激に富み、飽きさせない。
子どものときに遊園地などで催されたウルトラマンショーとか仮面ライダーショーにはなにかがっくりとくるものがあった。現実の場所で、そういうショーをやられても、ぜんぜん魅力とか興奮はないし、メッキは剥がれる一方だった。お化け屋敷もそうだ。あきらかに人形とわかるお化けが吊るされていると、興が削がれるばかりだった。
野球もそうである。ひごろナレーターつきのTVに慣れていると、じっさいに野球場にいってみて、あの広がりとなんともとりとめのようのない鑑賞感にがっくりときた経験はないだろうか。遠くでだれか見知らぬ人がキャッチボールをしているようにしか見えない。TVはカメラによって注目すべき点がクローズアップされ、ナレーターにより試合の流れが解説され、重要な点と着目すべき点が見事に編集され、われわれに与えられる。そういう注目や着目、解説などの編集作業がひごろTVによって与えられるから、野球場の試合は散漫で、とりとめのない経験に思えるのである。
つまり現実の体験というのはあまりにも多くの感覚や情報をうけとるがゆえにその世界に魅力や重要性を感じられないし、没入できないのである。しかし映画やTVは違う。映画やTVはほかの感覚を遮断し、目や耳、脳だけの情報に没入させ、非現実的な世界をつくりだす。感覚が遮断された非現実的な世界こそ、われわれが映画やTVを楽しむ経験の基盤と魅力をつくりだすのである。テーマパークにそれが欠けているのはいうまでもない。
要は編集作業である。散漫でとりとめのない世界が、編集によって重要や魅力的な要点だけがあつめられる。だから編集の完成品である映画やTV、雑誌などはたいそう中身がつまっていて、楽しいのである。観光旅行の情報なんてとくにそうだ。現実の観光地はのっぺりしていて、だらだらしていて、散漫で、色褪せているように見えるものだ。
だからといって、現地に行きたくないとは限らない。じっさいに現地にいかないことには、その経験は完成しないのである。経験はそうしないと自分の「所有物」にはならない。目と耳、鼻、皮膚、そして足と触覚の感覚をすべて味わって、はじめてその体験は自分に「所有」されたことになる。「場所」を占有してはじめて、「私のもの」となるのである。
映画やTV、雑誌はわれわれの経験上ではまだ「欠けている」のである。関与の度合いが低すぎるのである。皮膚や足、触感の感覚を味わって、はじめて私はそれを体験し、完成したことになる。
はっきりいえばTVや雑誌はほとんどの情報を与えているので、その経験をもって「完成」してもいいばずなのだが、まだ「足りない」。なにが足りないかというと、メディアは人間の全感覚で体験する経験の全体に達していないということである。その場所の広がりや距離感、風やにおい、地面を歩いた感覚はそこにいかないと体験できないし、これらを経験しないことには情報の体験は終わりにはならないのである。これらが欠けているがゆえに私たちはじっさいにそこに行かなければならない。(カネを払って)
ほんとうのところ、TVや雑誌によってかなりの情報や経験は完成しているはずである。ここで満足して、終わってもいいはずである。しかし人間は動きたい。歩いて、体験して、風を感じて、手でさわってみて、ほかの人と体験を共有し、楽しみ、時間を充実させたい。
しかしTVや雑誌、映画は人を座席に固定させる。動けない、さわれない、行為できない、参加できない。家や室内にこもり、人間関係はできないし、暗いし、ときには陰鬱であったり、空しくあったりする。人は行動して、参加したいのである。だから行動をともなうテーマパークや観光地は固定し、閉鎖された情報関与のストレスを解消させ、私たちの人とのつながりや楽しみの共有を促すのである。
ユニバーサルスタジオは映画を楽しむという点ではとうぜん負けるだろう。だが、映画を見ることでの行動や参加の欠如をおぎなうことで、映画に勝つ。あるいは映画の経験を完成させる。メディアによってうみだされた体験や行動の欠落は、メディアの継子によっておぎなわれるのである。その欠落をうみだしたのは当のメディア自身である。
失われた感覚と体験 01/4/3.
メディアは魅力的である反面、欠落をもたらした。目や耳の感覚に偏重と過重をもたらし、そのほかの嗅覚や触覚、皮膚感覚の抑圧や蔑視、忘却をひきおこした。感覚の変貌は認識世界の変質ですらある。
たとえば本のことを考えよう。私は本が大好きである。本は優秀で先鋭的な人たちの思想にふれられることができるし、空間や時間のへただりをこえて、かれらの思考に出会うことができる。偉大な人たちの思想が近くの本屋に行くだけで得られるというのはたいへんすばらしいことである。
本ができる前は優秀な人たちの思想にふれる機会は直接かれに会いに行って聞くしかなかった。もしその人が遠い外国にいたら聴講の機会はまずなかっただろう。何百年もまえに死んだ人ならなおさらである。本はそんな不可能を可能にした。
本ができる前、人は直接おおぜいの人に会って自説を紹介しなければならなかった。各地を旅しなければならなかっただろうし、思想を必要とする人を探し出すだけでもたいへんな苦労だっただろう。むかしの学者はこんにちの大道芸人のように漂泊や放浪者の一群たらざるを得なかったはずである。かつての仏教者がそうであったように。
本はいっきょにその問題の解決をもたらし、さらに思考の蓄積や深まりを何倍にも拡大した。個室でおおぜいの人の本を読み、文章を書くということは、思索をさらに深めたことだろう。空間や時間、テーマ検索の障害や手間をいっきょに省いたのである。
本は思索に必要とされる目と脳の機能への最大限の搾り込みをおこなった。すばらしい反面、五感で得られるフルの情報を削減しなければならなかった。本を読むさいには耳や鼻、手や皮膚などの感覚は抹殺される。
もし直接人に出会い、話を聞けば、五感からの情報はもっと多くの知見を与えたことだろう。本はそういう機会を奪い、ほんらいなら情報の集約であったはずの実際の人に出会うという機会すら価値の薄いものにしてしまった。人は魅力の座を本に奪いとられたのである。また行動や対面すること、会話することの価値も低めて、さらに不必要さすら感じさせるにいたった。
じっさいに会ったら、顔はもっと多くを教えただろう。表情や身ぶり、話し方、声の質はもっと多くの意味や情報を知らせただろう。においや触覚、皮膚感覚もさまざまな知見をつけ加えたことだろう。しかし思索の価値からいえば、そんなことはたいして重要なことではない。そうして目や耳、鼻、手、皮膚の感覚をもちいなくなる。じつは人間はこれら捨て去った感覚からじつに多く豊穣なる知見や情報を得てきたのだが、それは忘れられてゆく。
メディアは最大限の必要な集約をおこなうが、同時に諸感覚の排斥と疎外をももたらすのである。ひとつの感覚への磨きかけは、ほかの感覚の擦り減りをもたらす。用いられなくなった感覚は弱まり、あるひとつの感覚への強化と同一化は、おそらく人間の全体性への疎外と障害をもたらすことだろう。断片に同一化した自我は全体の感覚を忘却し、おそらく私たちに断片の苦悩と苦痛をひきおこす元になるのだろう。
本はながらく社会を支配してきたが、耳の拡張であるレコードが生まれ、ラジオが生まれた。人間はひとつの感覚の専横だけに満足できないのである。全感覚をとりもどしたいのである。しかしレコードやラジオの耳の情報は、視覚やほかの感覚を疎外するかなり偏ったメディアである。すがたかたちが見えない音というのは考えてみたら、未開民族が驚いて当然のじつに偏った、ヘンな装置である。
TVは目と耳の集約をおこなった。じつに人間の感覚に近い機械になった。目、しかも想像によっておぎなう活字本にくらべたら、じつに進歩と飛躍である。耳を排斥したり、視覚のほんの少ししか活用しない活字本とは破格に違う感覚の活用をもたらす。あまりにも多くの感覚を用いるため、視覚に集中した活字教育にはもどれないといわれるくらいだ。情報があまりにも多すぎて、活字からほそぼそと想像する情報なんかやってられないということだ。
視覚文化、活字文化というのはわれわれに気づかれない、しかしひじょうに重要な感覚の欠落をわれわれにもたらしてきたのだろう。認識の歪みや偏りはわれわれにかなり甚大な影響を与えてきた。世界観や世界のありようすら異なったものになっていたと思われる。
視覚・活字偏重の人間にはそれすら気づかれないし、価値すらあるのかと疑いたくなるものである。しかし人間の諸感覚というものは活字以上の情報や知覚を得られるものかもしれないし、眠っていることを好まない。全体的な感覚を味わい、全体で物事を感じとりたいのである。メディアの発達と歴史がそれを物語っている。ヴァーチャル・リアリティによって嗅覚や触覚、皮膚感覚を満足させることがおこなわれている。われわれはからだの全感覚やその深い能力をもういちど思い出し、活用すべきなのだろう。
2001年桜の季節の断想集
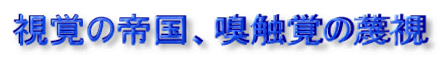
メディアは世界からの疎外をもたらすのか 01/4/7.
メディアは遠くの出来事や遠くの人の思想、あるいは過去の出来事や思想をつたえ、保存するひじょうに重要な機能をもっているが、同時にメディアは人間のひとつの感覚器官しか使用しないというひじょうに欠点の大きい面がある。
言葉は耳しか使用しないし、文字や印刷物、写真は目しか使わない、レコードやラジオは耳だけ、TVや映画は目と耳だけといったふうに、人間の諸感覚の欠落をもたらす。
空間と時間を超えた情報や知識は、人間に歓喜と情熱をもたらし、とうぜんその感覚への傾斜や特化、至上化がおこなわれる。五感を排した一器官の特化はおそらく世界からの分離や分断をもたらすのだろう。これが集合的無意識の幸福な合一からの脱落をもたらしたのかは私にはわからない。
活字文化と印刷文化においては視覚が感覚の王座を占め、聴覚は重要視されなくなり、嗅覚や触覚、味覚は動物に近いものとしておとしめられた。言葉や活字がこの世界の全構造を知るのに最高のメディアとなり、ますます視覚への特化と深化がおこった。
言葉や印刷文化、または視覚至上主義がもたらした世界観とか考え方のありよう、偏りとかはもっと深く追究したいと思うのだが、なかなかつかみ切れない。言葉や視覚の世界がほかの感覚器官の世界とどう違うのか知りたいと思うのだが、まだこれからの課題である。
ある感覚の特化や欠落は、世界の知覚にも影響をあたえる。われわれは世界をありのまま知覚し、物理的世界を写しとっていると思っているが、すでにしてわれわれは文化と社会のフィルター濾過をおこなった世界を見ているに過ぎないのである。母国語が世界観を規定するという「サピア=ウォーフの仮説」は有名だが、言葉だけではなく、感覚器官の活用や比重も文化によって規定されているのである。
感覚の世界というのはすでに文化規範の産物なのである。世界をありのまま見ているわけではない。われわれの知覚する世界というのは西欧化社会の視覚主義に染められた世界を見ているのであって、全感覚をフル活用した知覚世界を見ているわけではない。視覚主義になってから、われわれは聴覚世界や嗅覚世界、触覚世界の豊穣な地図や模様をどれほど失ったか思いもよらなくなっている。
人間というのは全感覚を最大限に活用してはじめて人間として生きられるのだろうか。あるいは感覚の偏りや特化をうけいれつつ、そこから最大限の果実を得るように生きたほうがいいのだろうか。
人間はいつだって全感覚を味わおうと努力してきた。印刷文化からはレコードやラジオがうみだされ、TVがうまれ、触感を味わうバーチャル・リアリティーもうみだされてきた。五感を全部味わおうとするのが人間の本性である。感覚の欠落は人間に埋めがたい飢餓をもたらすようである。排除されてきた感覚器官の豊穣な世界を探る必要があるようである。
知性=言葉の欠陥 01/4/8.
メディアの感覚欠落は知性の欠陥でもある。知性や言葉はひじょうに便利で卓越したメディアであるのはまちがいないが、五感のセンサー世界を排するし、言葉独特の偏狭で偏った、底知れぬ欠落をもたらす場合もあるのだろう。
言葉の欠陥をまとめてみよう。マクルーハンによると活字文化は画一性、規格性、同質性、反復性、連続性をもたらしたという。未開民族にとってこの世にはひとつとして同じものがないのだが、印刷された活字は同一のモノを大量につくれる。この驚異がこんにちの大量生産社会、または均質化・画一化された計ることのできる空間と時間の発想をうみだした。
これは近代科学の大元になった近代合理主義の考え方である。均質化、客観化された、測定可能な世界観というものがなければ、近代合理科学はうまれなかった。しかし世界は自己をはなれて客観的に存在するという発想はドグサ(臆見)にすぎないとフッサールはいっている。言葉は対象を捉えるためには、対象を分離=客観化しなければならないのである。
分離・分断は言葉が成り立つために欠かせない作業である。切り離し、切りとらないかぎり、言葉は言葉としてなりたたない。「頭」と「首」は線を引かなければ分けることができないし、「水」と「湯」は区切りをつけないと区別ができない。ほかのすべてもつながり、連関しているものにむりやりメスを入れ、切りとらないかぎり、言葉としては意味を成さない。これらはすべて切り離して存在できるかは疑問であるが。
物事や事象には無数の相・瞬間・側面があるのだが、言葉は単一の相を切り出す。世界には二度と同じもの・現象はないと考えるのが妥当であるのだが、同一性に固定する。活字ももしかして矛盾や変化の激しかった意見や考えを、固定した見解にしばりつけたかもしれない。一時的な現象もまた固定した「モノ」として表現されるのがしばしばである。
固定した見解は即時性や即座の参加の拒否をもたらした。行動や参加の融通がきかないのである。それは自己と対象の分離・客観化からはじまっているのだろう。それは存在と行為の分離でもある。
なによりも最大の欠陥は、言葉を対象そのものだと思ってしまうことである。言葉でイメージされた世界が世界「そのもの」に勘違いされてしまうのである。頭で描いたにすぎないものが世界そのものになってしまうのである。愚かなことだが、人間はこのカン違いからなかなか抜け出せないのである。
だからわれわれは怒りや悲しみからも自由になれない。頭で描いたり思い出したりしたものを現実だと思ってしまい、言葉からわきあがる感情の牢獄に囚われる。それがただの想像や虚構である――存在しない絵空事であるということに気づけないのである。
言葉=活字文化は視覚主義をももたらした。嗅覚や触覚、皮膚感覚などを侮蔑や感覚ヒエラルキーの劣位に追いやったのである。活字は視覚以外の諸感覚をいっさい必要としない。そのために豊かな五感の世界は失われ、五感センサーの多彩なる地図や情報は忘れさられることになった。
言葉は人間を世界や身体感覚から、分離し、分断し、切りとり、切り離すのである。断片やこまぎれとなった人間は、世界や身体の全面的な関わりから疎外され、抑圧され、分断されるということわけである。この決裂した人間のありさまは、言葉や活字文化、視覚主義によってうみだされたものである。深く胸に刻み、思い出す必要があるのだろう。
メディアVS現場と行動 01/4/10.
五感の全情報から、言葉や視覚、聴覚だけを切りとってくるのがメディアの仕事である。現場にはもっと多くの情報や感覚があり、においや騒音、風や温度感覚などさまざまな感覚が渾然一体となってそこの状況をかたちづくっている。そこからほんのわずかな切りとれるだけの情報を切りとってくるのがメディアである。
そして運送可能な情報や知識の価値ばかりが高まる。輸送できない、切りとれない感覚の価値――たとえば、においや体感、触感、皮膚感覚などは忘れられてゆく。なくても困らないものかもしれないが、それらの感覚は人に多くの情報や好悪の判断をつけくわえていったはずであり、人に快楽や喜びの感情、さらには生きている実感すら与えていたものかもしれない。
たしかにメディアはすばらしい、とてもよいものである。空間と時間、選択と編集の壁を飛び越える卓越したテクノロジーである。言葉がなければ一日たりとも社会生活を過ごせないだろうし、TVやCDがなければ豊かで楽しい日々を暮らせないだろう。
しかしメディアはある感覚機能しか輸送できないという点で、大いなる欠点をもっている。これは忘れてはならないだろう。目と耳しか輸送できないメディアはたしかに五感をもつ人間には欠陥商品である。人は五感全体で対象を知り、味わいたいのである。それこそが生きている実感と楽しみというものであり、その欠落をもたらすメディアの不完全さには警戒を怠るべきではない。
われわれは輸送可能なメディア情報に頼るばかりに現場感覚や体感、五感の大切や意味を忘れてしまったのである。生きることの楽しみや喜びはそれらの五感や身体に多く根づいているものかもしれないのである。
メディアはまた人々から行動することや反応すること、応えることなどの価値と実践力をも奪ってしまった。現場や対面において人々は即座の行動や参加を必要としていたわけだが、メディアはそういう行動をいっさい削ぎ落としてしまい、われわれを姿の見えない観客や聴衆、傍観者にしてしまった。われわれはのぞき部屋から世界の出来事をずっと覗きつづける無力で透明な存在になってしまった。
情報や知識はメディアから輸送されるばかりになり、われわれは現場にいることがなくなり、行動や参加の体験や経験はますます遠のいてしまった。われわれはメディアによって五感を失ったのみではなく、まずは行動を失ってしまったのかもしれない。
メディアと行動の分離は、言葉の性質ゆえかもしれない。言葉は主観と客観的世界を分け、存在と行為者を分けてしまう。出来事や物事から、行為を切り分けてしまうのである。
客観的世界を極めようとする近代科学観も主観と行為の分離によって成り立っている。そもそも思考することや観察することは、行動をやめることである。言葉の発展メディアである本やTV、レコードなどは、行動を滅却する大量生産・大量販売ともいえなくもない。
メディアは五感の人間にとってずっと欠陥商品でありつづけてきた。目や耳の機能に特化したその欠陥メディアのためにわれわれの意識形態や社会形態はどんなに歪まされ、欠陥的な生き方を余儀なくされていたかわからない。それは言葉の性質や機能自体から始まっている。深く反省する必要があるようである。
五感と身体感覚の価値 01/4/13.
メディアによって伝達できない五感にそんなに価値があるのか、いまの私にはよくわからない。嗅覚や触覚などの五感はとりもどされるべきものなのだろうか。それともこれまでのメディアによって仕込まれた視覚や聴覚中心でもべつに問題はなく、使われない器官はべつだんそのままでよいものなんだろうか。
トータルな五感で世界を味わうことはそんなに重要なことなのだろうか。まあ、いまのところは人はからだ全体で世界を感じとりたいのであり、技術や芸術などがそれをめざしてきた歴史があるとしかいえない。
メディアはとりわけ視覚を特化させてきた。視覚によって世界を知り、世界の構造を見極めようとしてきた。視覚中心の社会では視覚ばかりを用い、視覚のみで世界を知ろうとする傾向が強く、ほかの感覚世界を無視する。視覚の断片感覚だけが鋭敏になった人間ははたして人間の全能力や可能性を活用としているといえるだろうか。
ほかの感覚を抑圧することの意味はどのようなものなんだろう。たとえば匂いを忘れた人間は匂いによる世界のありようとか状態、判別や識別の能力や世界を忘れ去ったことだろう。匂いによって人は他人の健康状態や精神状態、あるいは病気すらわかったということだし、階層や外集団との区別すらそれで知り得ていた。
触覚は人との安心や一体感をもたらしていたし、心を癒す役割ももっていた。体温で人の状態がわかったかもしれないし、皮膚の質は知見をひとつ増やしていたかもしれない。触感や味覚というのは世界を知るための最初の探索であったし、いちばん深い安心や不快を鋭く分別するものであっただろう。
皮膚やからだの感覚というのは外の空気や天候、温度などをかくべつに感知するセンサーであり、気もちよい風や空気、晴れ渡った空気の爽やかさなどを直に感じとるものであり、同時に閉め切った部屋の空気のよどみ具合や梅雨のじめじめした湿度を感知する、いちばん基本的で原初的な感覚であり、自然の中で生きる人間たちはこの感覚から多くの情報や知見を得てきた。
そういう世界のありようを多く知り得て、かつ快不快の土壌であった身体感覚というのは、視覚特化をみちびいたメディア装置により、その役割や用途を抑圧させられてきた。視覚主義においては意味や価値が貶められ、その感覚によるコスモロジーは描かれなくなった。
メディアの情報というのは伝送できるものである。世界に一つしかないものではないし、唯一無二のものでもない。コピーできるし、同じモノをいくつでもつくれるし、とりかえがきき、大量生産でき、時間と空間を超えて伝達できるものである。
しかし伝達できない、輸送できない感覚や体感というものが、人間の生きている実感をより深く感じさせるものではないだろうか。感覚というのは唯一無二のものであって、言葉では伝達可能であっても、その感覚自体を他人に感じさせることはできないし、自分にしか感じることができないものである。
メディアは伝達できるものの情報や価値を高めた。共通の感覚や体験が重要なものになった。唯一無二のものより、数が多く、どこにでもあり、とりかえがきき、多くの人が共有するものに価値が高まった。つまり自分しか体験できない感覚の価値は弱まり、共同的な感覚共有の価値が高まった。
これは個々人の感覚より、共有感覚のほうが意味があり、価値があるということである。自分独自の感覚より、共通した、均一化された共有感覚のほうが重要であるということである。
このことによって個人の生は転落した。個々人の唯一性や自分しか感じることのできる身体感覚は重要でなくなった。つまり人間の生の根源である身体感覚や個別性といったものが重要視されなくなったわけである。メディアは共有感覚を高めるがゆえに、個々人の唯一性である身体感覚の抑圧や鋳型にはめこむこと、パターン化をもたらしたのだろう。
メディアは言葉も含めて、人間をどこにもであり、共有でき、複製でき、とりかえのきくものに仕上げる装置なのだろう。唯一性は言語からはじまって暴力的に駆逐され、唯一独自な生の土壌たる身体感覚は弱められ、薄められ、感じられなくさせられてしまうのだろう。
五感や身体感覚というのは、生の土壌であり、生存の実感を深めるものである。それらの鋭敏な感覚を用いないで、どうやって生の実感を感じられるというのだろうか。
唯一無二の存在である自分 01/4/14.
自分にとって自分はとりかえのきかない、かけがえのない存在である。自分がいなければ世界は消滅してしまう。生の実感や根拠のもとになるものである。自分は唯一無二の存在なのである。
しかし人は他者や社会のなかでも唯一無二の存在になろうとする。人々から認められたり、優越しようとしたり、偉く見られようとする。社会のなかにおいても、とりかえのきかない、かけがえのない存在になろうとして躍起になる。
そもそも人は生の基盤を与える唯一無二の存在なのであるが。なんでこんなことになってしまったのだろうか。社会に認められなくとも、自分は自分にとって生の実感や世界の現実を感じさせる唯一の基盤であり、存在なのだが。
どこから生は転落したのだろう。自分がどこにでもいる、大勢のなかの同じような人間のひとりに過ぎないと知るのは概念上のことである。頭のなかで知ってゆくのであって、身体感覚で知るのではない。言葉や自我が、自己の矮小化や卑小化をもたらしたのだろう。
メディアはもっと自己の矮小化を押しすすめる。大量伝達による画一化、均質化、規格化の波をかぶって、ますます自己はとりかえのきく、どこにもでもいる、似たり寄ったりの群集のひとりにすぎない卑小な存在に貶められてしまう。頭のなかの自己像はますます弱く、卑小なものになってゆく。
言葉が自己の客観化をおこなう。そこから自己の転落は起こっているのだろう。言葉は自己のなかの伝達できるもの、とりかえのきくもの、人と共通したものをとりだし、ますます自己の唯一性は少ないものになってしまう。
感覚の重心も身体から目や耳と移り変っていって、自己の唯一性は失われ、客観性や概念化による理解が進んでゆく。生の基盤や実感を与える身体、あるいは身体に関わる皮膚や筋肉、触覚、味覚、嗅覚などの感覚は重心が弱められてゆく。つまり自己の唯一無二性からかけ離れてゆくわけだ。
身体から感覚比率が目や耳、頭に移り変わるにしたがって、概念的・客観的理解がすすんでゆき、ますます自己の唯一性は失われ、自己はとりかえのきく、どこにでもいる画一大衆のひとりになってゆくのである。目や耳を使い、身体感覚を用いない言葉、活字、映像がますますそれを押しすすめてゆく。
そしてわれわれは自己の矮小さや卑小さ、画一・均質さから逃れようとして、比較や優越のチキン・レースをおこなうというわけである。唯一無二性を証明してくれるのは、他人の評価や認知、称賛だけだと思い込むようになってしまう。自分を群集のひとりとして見なした他者の心に自己の存在を植えつけることにより自己の唯一性を手に入れようとするのである。他者にとって無意味で無価値である自己の存在はそれによって補われるのである。
しかしそんなことをしなくても、自分は自分にとってかけがえのない、とりかえのきかない、生の実感や基盤を与える唯一の存在である。自分がいなければ世界は消滅してしまう。他者も存在しなくなってしまう。宇宙すら終わってしまう。
自分は生まれたときから、自分にとって唯一無二の存在なのである。努力も比較も優越もクソも必要ない。そもそもはじめからそういう存在なのであるから。なんて愚かなことなんだろうと思う。客観的な概念だけが否をいい、不安に火を点ける。この世界の実感や根拠、ありようを感じとるのは自分の感覚しかなく、自分の身体でしかない。安心すればいい。これだけでじゅうぶん唯一無二の存在であり、これ以上かけがえのない実感はないのである。
感覚のヒエラルキー 01/4/17.
人間は外界を支配・統御しようとしてきたが、自らの身体においてもその手綱をかけなかったわけがない。世界と接し、世界の状況を知る各種の感覚も、社会や文化のヒエラルキーづけをほどこされて、支配と統御を受けてきた。
ある感覚はもちあげられ、ある感覚は貶められるといったヒエラルキーである。視覚は活字・印刷文化においてますます重んじられ、嗅覚や触覚はどんどん貶められた。
いまでは鼻でにおいを嗅ぐ行為は動物的なものと蔑まれているし、触覚は性的なものとして遠ざけられている。しかしこれはどこの文化・時代圏においても通用する感覚秩序ではなく、西洋近代にあらわれたひとつの特殊な文化規範にほかならないようである。そしてあるひとつの感覚で捉えられる世界観はその感覚に限定されるというわけである。
あきらかに「文明/動物」の単純な対比の網目が身体感覚にかけられているだけである。また「理性/本能」といった対比ともいえるだろう。これはどういうことかというと、文明化、理性的であろうとしてきた近代人の価値観のヒエラルキーが五感のヒエラルキーと活用度合いをも決めてきたということである。
目や耳は文明や理性の旗印であり、嗅覚や触覚は動物や性欲の権化というわけである。したがってもっと目や耳をもちいて文明人になりなさい、鼻や手、皮膚は動物的な感覚であるから遠ざけなさいというメッセージを発してきたわけである。
多田道太郎によると、目や耳は明晰化・分節化の器官である。これらはスペクトルや音符によって分節化される。これに対してにおいや香りは多くが比喩で表現されるように、分節化されにくい。したがって「低級」な感覚であるということだ。明晰化・分節化をめざしてきた西洋近代はそれの劣る感覚を隠蔽してきたわけだ。(『しぐさの日本文化』角川文庫)
触覚が貶められるさいには、心の触れあいを「愛情」に、愛情を「性」に局所化してきたと多田道太郎はいっている。つまり触ることは「エッチでいやらしい」ことになり、心=身体の触れあいは性器に一本化されたというわけである。皮膚や身体の感覚はこうして抑圧されていった。SMやラバーマニア、においフェチというのは、性的色づけのむこうにある五感の感触や心の触れあいを無意識に求めているといえるかもしれない。
これで思い出すのが、フロイトのあの奇怪な幼児の性欲理論である。幼児には口唇期、肛門期、男根期といったそれぞれの快楽の段階があるそうである。これはたんに自文化の感覚ヒエラルキーの色づけをかぶせただけであって、ヨーロッパの感覚抑圧の機構をなぞっただけかもしれないといえなくもない。感覚の局所化というのははたして人間の順調な成長なのか、退化や不具化ではないのか、疑問である。
われわれの身体感覚や五感というのはあまりにも分化や分断化、局所化がおこなわれているといえる。そのような局在化がはたしてよいことなのか、全感覚をすべて用いるということがどのようなものか、あらためて考えてみるべきだろう。あるひとつの感覚器官による世界はとうぜんその感覚の限界内のものしか捉えられないし、感覚の分節化により縮小された感覚は全体の連関や活用を疎外してしまうものである。
これは社会において分業化がすすみ、断片化・専門化された人間は偏り、疎外され、充足した生を生きているとは感じられないことと同じである。文化の拘束着といったものを脱ぎ捨てるためには、見えないそれを知ることが必要なようである。
触わることの禁止 01/4/18.
深い悲しみや不安に襲われたときに私たちは言葉をかけるより、そっと抱きしめる。ひさしぶりに再会したときや、ものすごくうれしい出来事があったときには抱きしめ合う。親密にありたいと思う相手には触れたいと思うものだし、愛する相手にはとうぜんからだを触れたいと思う。
触れること、肌と肌を合せること、からだを合せること、といった一連の接触は言葉より多くの気持ちや思いが込められている。皮膚や触覚、身体の感覚というのは言葉より雄弁に私たちになにかを語りかける。
しかしわれわれの社会においては触れることは多くのタブーに囲まれている。見知らぬ人を触わるのはとうぜんにご法度であるし、女性なら性犯罪になるし、男同士で手をつなぎ合っていたりしたら、あらぬ関係を疑われかねない。
触わることというのは高度に社会規範や秩序、所有などの関係の網の目がかけられている。そして男同士でキスする国があったり、または男同士で手をつなぎ合うことが普通の国があったり、また女同士で手をつなぎあってもべつにおかしくはない国もある。つまり触わるという行為は、ある文化によっては許されたり、許されなかったりする文化規範なのである。
日本はほかの文化圏にくらべてかなり非接触の国であるらしいが、メディアの発達とも関わりがあるのだろうか。活字を文化の要にする国はとうぜん目の感覚比重を増やし、触覚や嗅覚などのあいまいなものは貶めてゆくことだろう。いっせいに視覚人間(つまり文明国)にするためには触覚や嗅覚の快楽や愉楽は狭め、禁止し、触れられないようにしたほうが都合がよいだろう。
どの感覚に比重をおくかは環境や文化に多く規定されるようである。視覚で知覚されるものに価値をおく文化は視覚に比重をおき、聴覚中心社会では聴覚、触覚には触覚といったようにその感覚に焦点をおく訓練や訓化がしぜんにおこなわれることだろう。こうしてあるひとつの感覚に焦点が当てられつづけ、それが研ぎ澄まされ、習い性となる。断片的になった人間が幸せかどうかはわからない。
視覚中心のこの社会では触覚や皮膚感覚はずいぶん貶められ、性的嫌悪のレッテルを貼りつけられてきた。そうして視覚比率の高い人間や社会はできあがってゆくのである。
肌の触れ合いや触覚というのは乳児期にその満足が得られなかったら、のちに暴力的な傾向が強くなると最近ではいわれている。接触や触覚というのはそれほどまでに人に深い安心ややすらぎ、愛情をもたらすもののようである。
その接触は性的レッテルのもと多くの範囲を禁止されている。また性感帯というのも全身の皮膚から性器だけに感覚の局所化がおこなわれてきた。狭めたり、局所化したり、また時間限定的なものにされた身体感覚の快楽というのはどうしてこう不運な目に会ってきたのだろう。おかげでわれわれの身体は多くの能力や快楽、活用度合といったものを失ってきたのである。
視覚ばかりに感覚比重をおく人間はとうぜん感覚の回線ができあがる。触覚や嗅覚の回線はますます使われなくなり、廃れてゆく一方である。断片的な存在になってゆく人間はやはり足や腕を失ったみたいに不自由で不幸なのかもしれない。全身で全身の感覚をもって生きることこそ、十分な生とはいえないだろうか。
【ご注意】最近モニターの調子が悪いです。まっ暗になります。とつぜん更新がとどこおったり、メールの返信をお届けできなくなったりする場合があるかもしれません。その際はモニターが故障した旨をご了解いただきたい。
復旧はなるべく早くしたいと思いますが、金欠と明日も危ぶまれる身の上のゆえにどうなることかわかりません。まことに申し訳ない。ガンバリマス。
(これは故障にそなえての一応のご報告です。) 01/4/7.
2001年初夏の断想集
五感を楽しむ 01/4/25.
個人的に30年ほど遅れてマクルーハン・ブームである。マクルーハンのメディア論についてはいろいろ問い方が可能だと思うが、私の場合は暗中模索だが、まあ五感に手がかりを求めた。
身体や感覚の延長であるメディアや道具によって人間は世界との全面的な関わりを失ってしまった。活字−印刷文化は大量生産の根幹をつくりだしたともいう。そういう感覚の欠落による世界観を探ってみたいと思ったのである。
ブームから30年たっているというのに感覚欠落の研究というのは思ったより進んでいない。メディアは視覚や聴覚の伝達の発達にはかなり寄与してきたが、嗅覚や触覚、身体感覚などを完全におろそかにしてきた。そういう感覚は文化的に動物的−性的な感覚として貶められてきたから、よけいに完全無視状態である。
文化的に劣勢とされてきた感覚というのはやはりメディアの発達とも関わりがある。印刷文化の発展により活字−視覚頭脳文化が尊重させられ、分節化・明晰化・分断化・専門化がひきおこされ、それらの性質に合致しない聴嗅触覚はますます貶められた。
視聴覚というのは伝達が可能であるが、嗅触覚というのははたして伝達が可能かわからない。目に見えるもの、音で聞くことができるものは複製や保存、伝達が可能である。この複製・伝達の可能性がマスメディアや大量生産社会の道をひらいた。こんにちの画一性・均質性の社会は工業社会からはじまったのではなく、すでに活字印刷文化、あるいは言語文化からはじまっていたともいえるのである。
複製・伝達できるものに価値が高まれば、ますます個人的体験や個人的実感というものがないがしろにされてゆく。身体感覚を経たものではなく、視聴覚と頭脳で結ばれたイメージで理解されるものがますます重要になる。こうしてわれわれは世界に対するしっかりとした手ざわりや実感、肌で感じる感覚というものを失い、より深い生の実感というものから引き剥がされてゆくのである。
われわれはますます頭の中のイメージで生きてゆくことになる。べつにそれで不便はないかもしれないし、メディアの価値や快楽はたしかに強いものであるが、人間の生きている実感や深い実存感というのはやはり身体の感覚にいちばん強く根づいているものである。
われわれはいろいろなものの手ざわりを楽しんだり、風や空気などの体感を楽しみたいのであり、伝達する必要もない音やにおいに多くの快適さや思い出を感じているものであり、肌や手にふれる人のあたたかみや心地よさに委ねたいものなのである。人間はそういうものにこそ、より深い快楽や快適さ、充足や満足を見出してきたのではないだろうか。そして身体の痛みやけが、出血、腫れ、不快感、脈拍や心臓の音などに生きているという実感をより深く感ずるものである。
複製・保存・伝達できるものはたしかに快楽であり重要なものであろうが、身体感覚の快楽や心地よさといったものも忘れるべきではないのである。マクルーハンはそういった生のより深い実感の大切さといったものを教えてくれた気がする。身体や感覚の延長であるメディアや道具は人間の生の実感を遠ざけるものなのである。五感の心地よさに回帰しよう。
他業種に転職するむずかしさ 01/4/27.
仕事に情熱も生きがいもそそぐ気もなし、仕事や会社ばっかりの人生なんてまっぴらだと思ってきた私は、かなりいいカゲンな職業人生を送ってきた。といってもカネを稼いでメシも食わなければならないので、まったく働かないわけには当然いかない。
働くとなったらできるだけ自分の好きなこと、興味の近い仕事につきたい。私はごらんのとおり書くことや本を読むことが好きなのだが、いかんせんコミュニケーション能力がない。人と会う仕事がだめだ。それによって仕事の幅は大幅に狭められる。
ほんとうのところ、このジレンマが私に人生の情熱と生きがいを削がせる最大の要因なのだろう。じつは自分の性格が人生の可能性を狭めるふがいなさに自分は参っているのだろう。あるいはそれに目を伏せて、嫌悪を社会に向けているだけかもしれない。反省して努力する必要があるのかもしれない。
まあ、この話は置いておいて、たとえばやりたいなとかおもしろそうだなという仕事につきたいと思っても、それが他業種のばあい、たいていは経験者のみの募集が多い。未経験の者にとってはものすごいカベである。たいがいはあきらめて、イヤで辞めてきたはずの業種に経験や知識があるということで戻らざるを得なくなる。夢はここで潰える。
まだその業種があるばあいは幸運なほうだろう。たとえば中高年のリストラなどのばあい、その業種が斜陽していたり、将来なくなったりする業界から抜け出てきたときにはどうなるのだろう。まったく経験のない世界ばかりに放り出されることになる。こういうケースが問題なのであって、産業や職業というのは長いスパンでみれば、絶対にこういうことが起こるので、衰退産業にいる者にとってはかなり深刻な問題である。
日本は解雇者をなるべく出さずに雇用を守ってきたから、逆にかんたんに移動する方法がてんで育ってきていない。おかげで衰退産業は政治力で守られる必要が出てくる。これをやったら競争力が育たないわけだが、当の労働者たちは転職する見込みが立たないのだから、意地でも政治の力でカネのあるところからぶんどってくるしかないだろう。
まず初めにおこなわれるべきことは転職がしやすくなる機構をつくることであり、先に産業を見捨てることではない。しかし新しいスキルを身につけて転職するというのはかんたんではない。まず戦後の人は一生涯ひとつの会社に尽くすことがよいことだと思いこんできたから、齢半ばにして新技能を身につける想定などまるでしていない。
リストラによってこういう労働者がちまたにあふれても、買い手市場の現在、企業側は未経験者を一から育てる気はない。かれらは新卒者以外の教育の必要性をまだ感じていない。教育ある労働者が足りないという経験をまだしていないからだ。即戦力をもつ者はうじゃうじゃやってくると思っている。つぎに売り手市場になったときには若干変わることは考えられるが、企業側はリストラ者があふれ出ても、ひと昔前の仕組みでじゅうぶんやっていけるのだ。
20代以下の求人ばかりだというのも、以前の年功序列の考えから抜け出ていないということなのだろう。年上の新人では年功序列も、賃金もまったく狂ってきてしまう。いまの買い手市場では変える必要がない。あふれ出た失業者は行き場がない。おかげで企業は労働市場でおこっている変化をとり入れるのに遅れることだろう。
他業種に転職するのはほんとうにむずかしい。自分で技術を身につける必要があるということだろうか。カネも時間もない人はどうしたらいいのだろうか。経験のある業種に帰ってゆかざるを得ないのだろうか。あまり夢も希望もないことである。仕事がますますつまらなくなる一方である。この状況はつぎに売り手市場が来るまで好転することはないのだろうか。いったいいつ来ることやら。。。
触れ合うことの安らかさ 01/4/28.
人が触れ合うことには大きな安らぎと慰めがあるのだが、そういう触感や体感の愉しみというのは多くは遠ざけられる運命にある。性的である、はしたない、幼稚である、といって公共の目からどんどん遠ざけられてきた。
触れ合うことはとうぜん幼児期の母親とのふれあいにさかのぼるわけだが、人はいつまでたってもその慰安にたちもどったり、そこから安心を得てきたいものなのである。しかしその弱みを隠さなければならないのが、文明というものである。
それを禁圧してきたのが文明である。また都市化である。見知らぬ人、関わりのない人ばかりにあふれる都会では、他人の親密な接触は人に不快感や怖れ、心配をもよわせるようである。疎外感や見捨てられた気持ちといったらいいか。したがって都会では、親密な接触はどんどん禁止されてゆくのである。
また文明では伝聞が紙や電波などのメディアによって伝えられる。文明の一員になるためにはメディアのリテラシーが求められる。触覚や体感の快楽を抑圧し、目や耳の器官に集中する能力が要求される。そのために触覚や体感はますます貶められ、性的や幼稚であると蔑れ、不必要なものとされ、鈍感になっていった。
大量生産が必要とする画一化・規格化のためにも、規格化を容易にする視覚の能力が必要である。画一的・規格化された知識・世界観を皆にもたせるためには視覚のリテラシーが不可欠である。触感や体感、または嗅覚などは規格化には不向きである。したがってわれわれは目と頭脳による仮構=虚構の世界にとどまる能力がますます必要になる。
こうして文明人たるわれわれは触覚や体感による世界との現実感や実感からますます隔てられ、脳のなかの仮構の世界に埋没し、現実との手ざわりや感触を失ってゆく。おまけに人と触れ合うことの深い安らぎや慰めからも遠く隔てられる。
親密さからも疎外され、世界の実感からも疎外され、頭脳により自己の唯一無二性も見失われ、規格化・均質化された群集のひとりにすぎない存在にされてしまう。頭脳や言語による自己理解というのは、自己の卑小さを強く理解させるものであり、触覚や体感、嗅覚などは自己の唯一無二性を感じさせる感覚で、自己の重要性や生の実感をゆいいつ痛感させるものなのであるが。
われわれはもっと身体の感覚というものを大事にするべきなのだろう。目や頭脳などのイメージ世界にばかり集中するのは世界の実感や手ざわりをますます遠ざけるばかりである。生の実感というのは身体にこそいちばん多く感じられるものなのである。こういう能力をみすみす見逃しているようでは、空しさと生の希薄さが募る一方だろう。
ヒト、家に隠れる 01/4/29.
人々の営みや暮らしが見えなくなったといわれる。人々の交わりや声、表情、身体表現などがますます都会から消え去っている。人は都市からつながりをなくし、表通りから人のにおいを消し、人々はすっかり家や建物のなかに閉じこもってしまい、まったく見えなくなってしまった。
都市というのは人がつながり、まじわり、話し合う空間でなくなり、道路や家、車などの無機質なモノばかりに遮断される空間になってしまった。人がざわざわと住んでいる空間というよりか、壁で築かれた防塞都市のようである。
寂しい、荒涼とした空間になってしまったのは間違いはないが、それはやっぱり人々がそれぞれ心の底で望んできたことなのだ。われわれは人と会い、まじわり、話し合うことを避けて、自閉した、まるで「ひきこもり」のような生を望んできたのである。なにもひきこもりの若者だけが現代社会から突出した存在ではないだろう。
そもそもなぜわれわれはこんなに他人から隠れようとするのだろう。なぜ家のような他人から見られる心配のない壁の建物を必要としたのだろうか。われわれは生まれたときから家に住み、家に帰ろうとするが、なぜこんなに壁の家に舞い戻ろうとするのか、考えてみたらふしぎなものである。
人間というのは人から見られることをたいそう嫌う動物のようである。とくに性愛や休息、睡眠などの最中を見られたりするのを嫌うようである。金銭や所有物などが加わって、人間はさらに空間の防御にことさらこだわるようになった。
最近ではさらに自分が「なにもの」であるか、といった存在表示さえ厭われるような感すらする。われわれはファッションによって自分が「なにものでないか」、流行やブランドなどの画一品によって隠そうとしているかのようだ。
自分の存在だけではなく、不安や心配、恐れなども通りから見えないようにしているのだろう。表通りから隠せば、私はいっぱしの人間であり、不安も心配もなく、みんなと同じふつうで健康的で平均的な人間であることを表示できるかのようだ。こうして問題も心配も不安も家の中に隠される。
仕事も田や畑、通りにあったものからオフィスビルや工場に隠され、人々の交わりや話し声も家や建物に遮断され、病気や老いも建物のなかに隠蔽され、犯罪も警察署と刑務所の塀の向こうに閉じ込められる。人々は行動や生のすべて、死までも建物のなかに隠しておこうとするのである。
まるで隠すことが万能薬のようである。隠したら、すべての問題は解決し、なんの問題も発生せず、不安も恐れもなく、死すら存在しないかのようである。都市というのは隠蔽に憑かれた人たちの密集地なのだろうか。
身近な人たちの生身の生を体験するかわりにわれわれは部屋の中に閉じこもり、TVやラジオ、新聞で事件や社会の出来事を知り、映画や本を読むことによって世の中の出来事を知る。子どもの外の遊びも、TVゲームや勉強に変わって家の中に入ってゆく。
都市に築いた人の営みとはいったいなんだろうかと思う。われわれはますます壁の中に隠れてゆくのである。人に見られないということがそんなに生の万能薬なのだろうか。たしかに人に見られることは窮屈で自由ではないし、不安なことでもあるが、問題の解決の方向性がどうもおかしいなという気がしないでもない。
人の街に住んでいながら、こんなに人のすがた、生きざまが見えない都市というのはやはりおかしなものだ。子どもたちに伝えられることも減ってゆくに違いないのだ。
都市の視線、スマートな都市 01/4/30.
むかしの街はもっと騒がしく、にぎやかで、人々の働きや立ちふるまいはもっと目立ったものであり、ことさら人の目を引くようであった気がする。
人々はどんどん見えなくなり、壁の向こうに隠れ、静かになり、スマートになった。むかしはもっと行商人や商売の人がけたたましく呼び声をあげていたり、すぐにそれとわかる商売の格好をしていたように思う。いまはそういう行商人の呼び声はほとんど聞こえなくなり、店舗の奥にひっこんでおとなしくなってしまった。
たぶんどこにでも見かけたであろう荷物を運ぶ人たちはどこにも見えなくなってしまった。むかしは大八車であれ、飛脚であれ、牛の荷車であれ、すぐにそれとわかり、かなり目立っていたことだろう。こういう人たちや業者はどこに行ったかというと、コンテナやトラックの荷台に隠れてしまい、しかも高速道路や湾岸線などに追いやられた。
仕事や商売はほとんど都市から姿を消してしまった。都市から人とのつながりが失われ、しゃべり声や騒がしさ、たちふるまいも失われてしまった。人々はどうしてこうおとなしくなり、みんなから隠れ、こそこそと生きるようになり、かつスマートになったのだろうか。街で見かける人はほとんど帰路を急ぐ人たちばかりである。
人々は他人から自分の生のほとんどを見せないようになってしまった。たしかに情けない部分やみじめな部分、さらしたくないことなどを隠せば、カッコよさも維持できるし、スマートである。でも、なんだろうな、気安さとか気さくなつきあい、人情とか、そういったものはスマートで隔絶された都市からは生まれないのだろうな。
車の発展が人々のすがたを消す大きな理由になったのだろう。荷物を運ぶ人たちは車の座席に隠れ、とんでもない荷物を肩からかついだり、ものすごい重量もある荷車を引いたりする人たちの少々哀れを誘う、あるいはたくましさを誇示するような格好はまったく見えなくなったのである。車はまた遊びに行く人や散歩する人、買い物する人のすがたをも消し去った。家族の場合はとくにそうだろう。
技術や道具の発展が人々を街から見えないものにしていったのである。そして見られるものは劣等や哀れを誘う存在になり、かれらも隠れる存在になっていったのだろう。見られる人はブラウン管の中か、写真や文章の中にあらわれることになった。
視線は権力でもある。近代人は見られ、監視されることによって権力を内面化し、縛りつけられてゆく。見られることにはひじょうに敏感である。できれば他人の視線を感じていたくない。そして部屋の壁の中で人に見られることなく、人を見ることに専念できるTVなどに没頭してゆく。
人の姿や声、たちふるまいが見えなくなった都市というのはいったいなんだろう。なにか大切なものが伝達されず、大切なものが失われていった気がする。われわれは自分を表現したり、自由に発散したり、気安く話し合えるといった関係をどんどん失っていった気がする。人々の息遣いや生きる営みも見失われていったように思う。
ナゾ解きの愉しみ 01/5/2.
読者の方々の中にはどうして私はこうも本を読んだり、エッセイを書きつづけているのか、とふしぎに思う方がいるかもしれない。
私の読書熱というのは完全にナゾ解きの愉しみである。「これはどういうことなんだろう」、「これはいったいどうなっているのか」と疑問やナゾを考えているうちに次々に本を読まざるをえなくなり、文章上で考えなければならなくなる。まったくナゾ解きである。
たいていの人は学問上のナゾ解きの楽しみを知らない。そもそもナゾを感じたり、それを追究する方法を知らない。学校ではナゾの解き方を教えない。ただそのナゾ解きの結果にすぎない学問知識を羅列的に教え込まれるだけである。これは最高につまらない。好奇心がわかないまま、知識なんか吸収したくもない。
不幸なことにナゾ解きの楽しみを覚える前に大量の知識を覚えなければならないのが現在の学校である。またナゾ解きの楽しみを教えないほうが、既成の知識権力を覆さないという利点があるのかもしれない。既成の知識で満足するか、それ以上は追求されない。
したがってたいていの人はほかのナゾ解き、もしくは楽しみに熱を上げることになる。女体のナゾであったり、競馬のナゾであったり、サッカーの勝敗のフシギであったりするのだろう。ミステリーもナゾ解きであるが、なぜか私は興味がない。どちらかといえば、人工のものより、自然の神秘を相手にするのが好みだ。
私がナゾ解きの愉しみの対象にするのは、社会学とか哲学である。こういう身近で日常的な事柄でありながら多くの人が興味を示さないのは、ナゾを解かなくても十分暮らしてゆくことができるからだろう。あまりにも当たり前に送っている日常のことなので、ナゾや疑問を感じる必要はないのだ。
それに対して多くの人の心を捉えるナゾというのはUFOや超能力や怪奇現象である。これらはかなり身近なことでありながら、永遠の神秘やナゾでありつづける。だから多くの人が好奇心を引きつけられつづけるのである。社会学や哲学にはこういう外に開かれたナゾの糸口というのはかんたんには見いだせない。
でも社会や人間というのはいちどギモンやナゾに思いはじめたら、ナゾばかりである。ふと日常おこなっている当たり前のことに疑問符を付してみたら、強烈なナゾの亀裂がぽっかりと足元に広がっているものである。そういう奇怪とか異様とか、摩訶不思議とかいう目で人間や社会を見直すことが、ナゾ解きの楽しみのはじまりである。まあ、この世界にナゾナゾの呪文を唱えつづけるようなものだ。
ナゾ解きを楽しむ方法というのはそんなに難しいものではないと思う。疑問やナゾに思う気もちを強く持続することさえできれば、本や知識というのは向こうから網にかかってくるものだ。知りたくてたまらなければ、いろいろな知識を貪りたくなるものである。そうなれば、難解に思えた哲学書や学術書だって、より興味をそそり、自分の興味に叶うものに見えてくるからふしぎなものだ。
こういう興味の持続に、私の場合は書くという行為がたいへん大きな役割を果たした。ある主題のナゾについて書き出せば、どうしても答えやなんらかの解答を書かなければ収まりがつかなくなるのである。こうして私の答えを見出すためにあらゆる本を読みあさり、書きながら考えるというナゾ解きの愉しみはいまもつづいているというわけである。
知識を吸収したり本を読むということには、疑問やナゾに思う気もちというのが深く関わっている。こういう気もちを育まないでたくさんの知識を得ようとするのはムリというものだ。ナゾや疑問に思う気持ちだけが、知識や本を強烈に吸い寄せるのである。
テーマに合った本を探すむずかしさ 01/5/3.
私の読書はナゾ解きスタイルである。ナゾを掘り出そうとして、いもづる式に本や知識がひき出される。
ナゾや疑問のテーマを思いついたら、まずは書店に探しに行く。こういうテーマの本だったら岩波新書や中公新書にありそうだなとか、いいやたしかちくまや講談社学術文庫にあっただとか、専門的なばあいだったらハードカバーにしかないなとか、本屋の書棚の記憶などをたよりに本を探す。
でも最近なんだか徒労感をたまに感じる。新テーマを思いつくたび書店を探し回らなければならないし、おめあてのテーマの本を探し出すのもかんたんではない。本というのは私のナゾ解きスタイルに合ったかたちで編纂されているのではなく、あるひとつのテーマを一から十まで解説、説明するパターンが多い。
書店を見回すのは新刊などを見たりして楽しいことではある。でもはじめからひとつのテーマに絞った本探しのばあい、見つけられなくてたいがい苦労する。書店でたくさんの本に当たってみて自分の知りたいことを確かめることができるが、いちばん知りたいことはどの本に書かれているのかを見つけるのはたやすいことではない。
たとえば最近のテーマでは「五感」というものを探ろうとした。マクルーハンに触発されて、メディアと五感の感覚比率を探りたいと思ったのである。できれば安い新書で見つけたかったのだが、ほぼなくて、メディア論はなんか違うし、高いし、あきらめ気味になる。
私のナゾ解きはじつのところ、たいがいは尻つぼみで終わる。知りたいことを全部極めたのか、満足したのかは自分でもよくわからない。読みたい本が尽きてきたころには自然に興味も醒めているといった具合だ。たいがいは投げているのかもしれないし、私の興味の持続力はそのていどなのかもしれない。
自分で考えることも必要なのかもしれないが、つい先達の成果に頼ってしまう。成果ははるかにあげられていることが多いからだ。またじつに自分の感覚だけをたよりに考えるのはひじょうにむずかしいばあいもある。本のあいだで考えるほうが効率的だろう。インターネットで人に見せるエッセイになったことは、稚拙な思考の積み重ねを許さなくなったということがあるのかもしれない。
しかしこういう方法がパターン化されてくると、やっぱりやみくもなやり方は反省されてしかるべきだろう。進歩がない。パターンの結果に習熟してきたのだから、同じ失敗は避ける努力や方法は考えるべきだろう。
文献目録やブックガイドのようなものをなるべくもつほうがいいのだろう。書店を探し回るのは効率が悪い。できるだけテーマや内容別の文献目録のほうが好ましいだろう。こういう本はなかなかなかったり、あったとしても役に立たないものであったり、高すぎたりする。まあ、なるべく当たってみることにしよう。インターネット書店の二、三行の解説なんかまず役に立たない。
でもなんだかほかに方法がないみたいだなぁ。書店で探し回るというのが古典的であり、疲れもするが、疑問に合致するか確かめることができるので、いちばん合っているのだろうか。う〜ん、もっと効率的で、ワリのいい見つけ方はないものだろうか。ぼちぼち考えまひょ。
平等はやっぱりよくない 01/5/4.
平等というのは地位や順位によって生まれる夢や目標を失わせてしまう。違いや格差がなくてみんな同じようでは若者は目ざすべき憧れを見つけられない。小さくまとまった、希望のない将来像しかいだけない。
みんなが平等というのは搾取や差別のない理想に思えるが、よく考えてみたら、「みんなと違う生き方をするな」ということだ。旧来の生き方や画一性・均質性を押しつける都合のいい隠れ蓑になっている。
ファッションの流行にあらわれるように若者はみんなと同じ格好をしたくない。オヤジの生き方に反抗するのも若者の自立として当然のことである。理想としての平等はこういう自然の気もちを刈りとり、若者の夢や自立をもつぶしてゆく。
なによりもいけないのは会社や国家が人々の多様で個性的な生き方を認めないことだ。「みんなと同じでなければイカン」という考え方が、平等という人権的な正義ヅラをして、人々に画一的な生き方を押しつけている。これが最悪である。
平等はまた価値観の統一や押しつけもおこなっている。現代の平等観というのは富やモノにより測られたもので、差別や搾取の不当性のスピーチを聞いているうちに、なにがあわれなのか刷り込まれ、いつの間にか富や経済を優位におく価値観に染められるのである。
なにに価値をおき、なにに幸福をみいだすかは人それぞれ、多様で自由であるべきなのである。平等の理想はそういう多様性や自由を叩きつぶしてきたのだろう。平等が理想とされるときにどんな多様性や自由が奪われるか考えるべきである。
広い目でみてみたら私はこう考えるけど、個人的には人にエラそうにしている人はキライだし、人にエラそうにするのも好きではない。なんだかその人の浅はかさが透けて見えるようだし、役割の上でエラそうなことなんかしたくない。けっこう私は平等の理想をもっているのかもしれない。どう考えればよいのだろうか。
私は人格の平等はぜひとももちたいと思うが、人の自由や多様性を奪うような平等は撤廃すべきだと思う。経済的差異や階層はあっても、人格にくわえられる差別や中傷は許されないのが理想である。経済的階層が強い社会は、経済的に劣っていてもそれぞれのよさやありようを寛容に認め合う社会になることができるのだろうか。そのような社会なら平等を理想とする社会より、よほど自由で楽しい社会になるだろうと思う。
モニターが故障しそうです。今のところ叩いて直しておりますが、いつブッ壊れてしまうかわかりません。しばしの「凍結状態」に入ってしまうかしれませんので、お先に謝っておきます。
010507断想集

竹内久美子の本について 01/5/7.
このところ、たてつづけに竹内久美子の本を読んだ。おもしろいからつぎつぎと読みたくなるし、100円の文庫で手に入る気軽さもあって、ついついまとめて読んだ。
私が興味の中心にしているのは社会論あたりなので、とくに繁殖戦略を中心に社会文化を説明するところに興味を魅かれた。とにかくおもしろいし、読ませるのだが、違和感はあるし、ほかの説明のほうがいいんではないか、あまりにもご都合主義的な説明ではないかと、つぎつぎに反発したくなる。
著者ははじめからそういう納得と独断と反発を生む本を意図していたらしい。まさに思惑にはまっているわけだが、ここまで空想的でご都合主義的な説明ならとうぜん学者の反発を招いてきたことだろう。なんかよく知らないが、トンデモ本にもとりあげられているらしいし、盗作の裁判もネットで見られるし、学者の評価もよくないのだろう。
科学的な慎重さがなくて、パズルのような空想的つじつま合せの整合性にいかさま師的な要素を嗅ぎつけないわけにはゆかないが、だからこそ発想がゆたかでおもしろい、意外な論理性を発見するなどのお楽しみがついて回るのだろう。実証性には信頼はあるが、堅苦しさやつまらなさがつきまとい、柔軟で大胆な発想はできないということである。
私としては動物行動学の最近の知見を魅力的なかたちで知ることができたので、一般読者と学問のあいだをとりもつ本として楽しませてもらった。動物行動学はゴリラとかライオンとか一種類の動物を追う本はどうも読む気がしない。もっと多くの知見をまとめて垣間見せてくれる本のほうがありがたいのである。しかも竹内久美子の本はそれを人間にまで延長して社会や国家まで語ってくれる。仲立ちをしてくれる本である。
基本的なスタンスとしては利己的遺伝子や繁殖戦略によってすべての動物の行動や社会構造を説明づけることにあるみたいである。たとえばオスとメスの大きさの違いは繁殖戦略にあり、クジャクのオスの豪華さもそういうことである。食べる食べられる関係より、性別間の競争のほうがより早く進化をうながすそうである。
そういう繁殖戦略から人間社会を説明づけようとするのが竹内久美子の発想であり、またこれは社会生物学という学問だそうだ。この学問が生まれたとき、キリスト教とか人種差別的な問題から、とうぜん反発を生んだようである。たしかに性淘汰とか生存淘汰の考えは人々をたいそう震えあがらせるし、慎重にとりあつかわなければならない倫理の領域である。それが決定論なんかになったら最悪の思想だろう。
ある学者は社会科学は社会生物学の下位分野になるといったそうだ。たしかにすごい説明能力をもっている。逆になぜ社会科学はそれにはまればはまるほど、繁殖や生殖の領域から遠ざかってしまうのかふしぎである。またふだんの人間の頭にしても、繁殖や生殖はほとんど考慮の外にある。社会生物学はそういう繁殖から人間を見つめる必要性というのに改めて目を啓かせてくれる。繁殖戦略の結果としての人間のありかたというものをもっと重要視する必要があるのだろう。
繁殖戦略はなぜ頭にのぼらない? 01/5/9.
竹内久美子は人間の性格や社会のほとんどのことを決めるのは繁殖戦略であるといいきっている。その分析や解釈は唖然とさせられることばかりだが、なるほどだなといいたくもなる。
私は社会学とか哲学分析に慣れているので、動物行動学からの繁殖至上主義みたいな発想法はなかなか根づかない。社会学や哲学、または経済学では、人間の行動を繁殖戦略から説明しはじめるということはまずない。経済合理性を繁殖合理性から説明したりしない。
逆になぜ社会科学は繁殖戦略をほとんど考慮の外においてきたのかふしぎなくらいだ。そもそもふだんの私たちからして、行動や考えの発端に繁殖戦略を意識するということはほとんどない。どちらかといえば繁殖のことなんて、現代の消費社会においてなおさら考えない。
われわれは子孫の永続や繁栄のことより、自分の楽しみや快楽、喜びのことをまず先に考える。文化や政治、芸術、消費、生活がまずはじめにあり、最後までほとんど繁殖のことなど圏外である。
現代の人は繁殖を目的に考えないし、第一に思ったりしない。だから動物行動学や社会生物学の繁殖第一主義や利己的遺伝子の考えは、反発や違和感を感じさせるが、しかししぶしぶは何割かは納得せざるを得ないものである。(世界の原住民は子孫をのこすことだけが人生の唯一の目的であり、そのほかになにがあるのかと思っているそうだが)
私たちにとっていちばん大事なことはどうやって生き、生活してゆくかということである。つぎに社会の地位や活動、恋愛や性、または文化や芸術、消費、享楽、などとつづく。人間の頭には繁殖のことより、生活や楽しみのほうが重要なのであり、繁殖は現代ではどちらかといえば、性的享楽のためにあるようなものだ。
これすらも繁殖戦略だといいだすかもしれない。繁殖戦略は人間の頭に意識されるよりか、楽しみや文化に意を注いだほうがよほど効果をうるのだと。よそ見をしたほうが繁殖戦略には有利というワケである。人間の社会は複雑だし、繁殖のみにいそしむ者は社会生存のうえで有利ではないだろうし、本能むき出しは文明の作法にも反するということである。
たとえば善人や無欲の戦略というものを考えてみたら、かれらはその表の目的を意識するが、その裏の目的である評価や称賛は考慮にいれない。真の目的は意識したら、人に見破られ、成就しないのである。
もし繁殖のみが人類の目標だしたら、それを頭で意識しないほうが、うまくゆく可能性が多い。知らんぷりをして、文明の抑圧やルールの網の目をとおりぬけて、繁殖戦略に勝つというわけである。
とはいっても、繁殖と利己的遺伝子の存続だけが人間の究極目標という考え方にはどうも全面的に賛同する気にはなれない。私のこれまでの価値観や生き方とあまりにもかけ離れているということもあるだろう。現代社会は繁殖から離れた価値観ばかりを追求してきたからだ。
しかし竹内久美子による繁殖によって人間のかたちや社会形態がいかに変化・進化してきたかという説明にはひじょうに納得、共鳴できるところが多かった。繁殖戦略、忘れるべからず。
失われた興味とその行方 01/5/11.
私はこれまでさまざまなテーマで本を読んできたが、そのテーマ探索が終わると、そのジャンルに関しての興味をほとんど失ってしまう。まるで興味を失い、その本のページをめくろうとも思わないのである。
いまでは大衆社会論の本はほとんど読まない。共同幻想論の本も読まなくなった。ビジネス書もこのHPをアップしたころには興味があったが、ほぼ興味を逸した。現代思想の本に触手がのびることはほとんどなくなった。
興味の失い方ははなはだしい。まるで興味をそそらなくなるのである。一時期、熱した情熱や興味はさっぱりなくなるのである。
まあ、私の性格自体がふだんから興味のないことはまったく興味がないタチであり、一般の人たちが好きそうな野球とか車とか競馬とかまるで興味がなくても平気だから、これは自分の性格ゆえのものだろう。
ただ、自分の過去の興味に対してもまったく興味を失ってしまうのはなんか少し恐ろしい気もする。蓄積とか専門性がほとんど育たないからだ。
大学の教授なんか何十年もかけて同じ専門分野を追究してなんらかの成果や業績を生んだりするものだ。私にはそういう専門性の持続力がまるで欠けている。ただし、教授のなかには何十年も同じノート、同じ講義内容を教えている人がいるらしいから、一概にはよいとはいえないが。
新しい未知の分野だからこそ興味が沸くものなのである。それに私の興味範囲はてんでばらばらというわけではなくて、やっぱり社会学あたりを中心にぐるぐる廻っている。さまざまな角度から社会学をやっているといえなくもない。ひとつの専門分野だけならすぐネタがつきてしまうし、ナゾ解きのおもしろみもなくなってしまう。
興味が逸するだけならまだいいが、私は物忘れがはなはだしい。読んだ本は、たぶん告白するならほとんど覚えていない。自分の記憶力に唖然となる。じつは私はふだんからそうで、さっき自分がしたことを思い出せないことはしばしばであるし、昨日の昼飯も思い出せないので、戦慄するほかない。
私は日々、記憶と興味を失った本を積み上げつづけているというワケだ。これはなんだろうな〜、私は自分にとってよい行いや役に立つことをしているといえるのだろうか。このような結果からして一時期の興味は追求されるに値するものか顧みる必要もあるのかもしれない。
これまで追究してきた知識は私の血と肉になっているのだろうか。私に賢明な知恵と知識を与えてくれたのだろうか。あるいはべつにそうでもなくても、ただ一瞬の知の愉しみ、喜びを与えてくれるだけでもよいことなのだろうか。そういう答えに落ち着きそうである。
繁殖がすべて? 01/5/14.
繁殖で人間のすべてを説明できるものなのだろうか。たしかにこの説明道具は魅力的である。人間のすがたかたち、社会行動、社会形態、歴史まで適用することができるだろう。
人間を経済的要因や文化的要因によって説明づけてきた者にとっては驚愕のあまりアゴを落しそうだ。現代の人間にとって繁殖以外の説明のほうが納得しやすいし、繁殖を唯一の目的と考える人間はそう多くないだろう。
だけど繁殖が人類の歴史に多くのものを残してきたのは間違いない。子孫以外に残せるものは生命にはないのである。結果的に子孫を存続しえた者は歴史を決めてきたのである。人間はそういう者たちの成果や結果をより多く刻印づけられてきたことだろう。
しかし現代人はあまりにも繁殖以外のことを重視し勝ちである。経済や文化、芸術、消費、レジャーといったものだ。繁殖や子孫より、「自己」と「自己の享楽」が大切なのである。晩婚や子どもを産まない選択もある。
現代人およびその歴史は繁殖のみでは説明しにくい経緯をたどってきた。経済的要因が多くを決定してきた。経済が自己主義や現世享楽主義を促進してきた。これすらも繁殖や生存に有利だからという答えが出されるだろう。経済や文化に邁進したほうが子孫の存続を有利にするということだ。
これをミーム(文化的な遺伝子)というそうだが、個体は遺伝子を残さなくても、血縁の生存が有利になるという、とってつけたような説明がつく。われわれは血縁のために文化的名誉や自己享楽を求めているようにはとても思えないけど。
繁殖という視点は人間の新しい面を見せてくれるが、ほかの要因で動いていることも多いように思える。しかしそれすらも繁殖の有利さに帰結するのだろうか。繁殖は人間のすべてを呑みこむものなのだろうか?
たとえば名門家系の繁殖戦略 01/5/15.
繁殖戦略や進化でどんなことまで説明できるだろうか。私はまだまだ社会生物学や行動生態学について勉強不足だし、時期尚早だが、どんなことまで適用できるか考えてみよう。
人間を長い目で見ようとしたら、まずは家系が思いうかぶ。名門家系や老舗家系というのは古くまで歴史をさかのぼれる。適任である。
徳川家や豊臣家、平氏、源氏といった家系はその繁殖・生存の適応度を高め、現在まで有利なポジションを保っているのだろうか。
上流階級や中流階級、労働者階級というものがもし日本にまだあるとしたら、かれらの繁殖戦略とはどのようなものなのだろうか。日本では士農工商といった階層があったが、それぞれの職種に適した性格や行動、興味などの適応進化がある程度はおこったことだろう。ただ職業や富は近代においてめまぐるしく変動してきた運命にあったから、職種適応は袋小路になりはしなかったか。
文化的才能や商業的才能、技術的才能、政治的才能といったものは祖先からうけつがれてきたものなのだろうか。人間は肉体自身よりか、文化的・技術的な表現の延長型に繁殖の有利さや誇示を仮託する傾向が強い。現在、自分に具現しているある種の傾向といったものは過去の繁殖有利性に由来しているのだろうか。
人は幼少のときから固有の趣味や特技をもちはじめる。それは祖先の繁殖選択の結果なのだろうか。二世の職業家が多くいるように有利な資質はうけつがれるのだろう。
メカやスポーツ、文化、ファッションなどに強くなって異性をひきつける。好きでやっていると思っているものも、祖先の繁殖有利性がなせるものなのだろうか。
それにしてもオタクはどうしたものか。異性の好感はあまり得られない。男はコレクションに凝り、女は装いに入れあげ、高じて異性の不満を買うことがしばしばあるみたいである。才能は自己目的に暴走し勝ちなのか。
ヤンキーの繁殖戦略というのもなかなか特異なものである。若くして非行に走り、結婚出産もかなり早い。若年戦略みたいなものが、かれらの非行誇示をうながすのだろうか。高学歴や地位の高さの有利さにこだわらないからだろうか。
逆にOL系や高学歴サラリーマンなどは晩婚化に傾き勝ちである。知識や地位の高さの獲得が晩婚をみちびくのだろうか。表現の延長型戦略は時間がかかるのか。
繁殖戦略によって以上のようなことが考えられないかと思うのだが、どうだろうか。
繁殖の秘密主義 01/5/18.
なぜ人間は繁殖や性を隠したり、恥かしがったりするのか前々から不思議に思っていた。イヌやハトは人前でも平気につがっているし、サルもほとんどそうだということだ。
捕食者にいちばん襲われる心配のない人間がなぜ性交行為をこんなに隠すのか。捕食者相手に隠れるのなら、他人の目をさえぎる家やカーテンも必要ない。
竹内久美子は繁殖戦略を人に見られたら不利になるということをちらっといっている。人の目を欺き、だますためにこの特異な羞恥心があるということだ。
栗本慎一郎は隠すことにより、刺激や快楽が増大するからだといっている。同じように労働や法律もそれを壊す快楽(戦争や破壊)のためにせっせと我慢していることになる。
私はそれは所有の目印のためだと思う。服でハダカを隠すのは所有者がいることを示す。性的関係者や繁殖占有者がだれかいますよという目印だ。つがいの印である。
もちろん所有されていない者も服を着る。ハダカを隠すことはお宝や富の逆誇示でもある。隠すことによって価値がますます高まる。秘匿の開示や共有は、親密性や排他性をペアのあいだに高めるだろう。
ハダカの羞恥心はどちらかというと自慢に思うより、劣等感に近いマイナス感情である。これは男にガードが堅いことを示すだろう。羞恥心を開くために男は多大な経済的献身をほどこさなければならなくなる。固い絆が結ばれる。男は羞恥心の強い女を好む。ほかの男と交配する心配はないからだ。
隠すというのは関係の排除なのである。性的、経済的占有の目印である。性的な羞恥心はそういうところから生まれたのだと思う。羞恥心は繁殖関係を結ぶための関係の拒否である。
羞恥心は服を必要とし、家を必要とし、富の個人所有をもたらした。服や家といった文明の道具は、羞恥心や繁殖の性質から生み出されたものかもしれない。生殖にかかわる隠すという行為が文明をもたらしたのだろうか。
隠すことはまた「自我」や「自分」という感覚をもたらす根源的なものである。子どもは親に隠し事をもって自立してゆく。また秘密の共有が「内輪」と「ヨソ者」をわける境界線になっている。
人間は性を隠すことによって繁殖関係をつくり、また人から秘密を隠すことによって自我感覚を生み出す。服や家、個人所有も隠すことから生まれた。隠すということが人間の根源的なことにかかわっているのである。人は隠し、他人から線を引くことによって「自分」となる。そのもとの一線は性関係の他者の排除によって引かれるのである。性の関係性が人間の自我意識をつくりだしたのだろうか。
■文章のレイアウトが見やすくなりました。
これまでのヘンな改行があらわれて見にくくなるということは、ブラウザの小画面でもなくなりました。
これもひとえに「文芸の扉」のichitaさんがわざわざ指摘してくれたおかげです。感謝します。(世界文学と純文学、ミステリーの書評ならこのHPです。)
<TABLE CELLSPACING="120"><TR><TD>を貼りつけたらいいだけでした。(数値は自由)。念願の余白設定ができてとてもうれしいーです。
モニターが故障しそうです。今のところ叩いて直しておりますが、いつブッ壊れてしまうかわかりません。しばしの「凍結状態」に入ってしまうかしれませんので、お先に謝っておきます。
(最初の報告から一ヵ月たってもしぶとく生きております。)
010520断想集
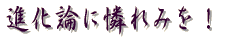
40、50代で仕事がなくなる将来 01/5/20.
リストラされた人たちの迫真のルポ、『こんな人が「解雇」になる』夕刊フジ特別取材班(角川oneテーマ21)を読んだ。いままさにこんなひどいことがこの日本のどこかで進行していると思ったら、暗澹たる気もちになる。
40代になると化石として捨てられるコンピューター業界、非情なリストラ担当者が気がつけば自分の番だったり、塾講師も若者人気でリストラ、ファミレスのバイトで「リストラおじん死ね」とイジメられたり、物置小屋に押し込められたりと、この世のものと思えないほどの悲惨な現況がつたえられている。
こんなリストラ流行りでは会社のなかの人間関係はどうなってしまうんだろうと思う。信頼も信用もなくなるだろうし、いたわりややさしさも消えるだろうし、かつての家族主義とか恩情主義とかのたまっていた会社のバケの皮がはがれたら、いったいあとには何が残るというのか。
なによりも明白なことは、40、50代になると会社内でも会社外でも必要なくなるということだ。年をとるとリストラを迫られ、外の企業も同じように中高年は受けつけない。年をとるだけで罰や罪を背負ってしまうというのか。
こんな将来しかない若者はどうやって生きればいいというのだろうか。40、50代になるとお払い箱の将来が待っているのだ。希望や夢をもてるか。生き残る戦略なんか立てれるのか。年をとれば自動的にお払い箱なら、若いうちに後半生の貯蓄を貯めておくことなんか可能なのか。
いまは過渡期だから将来変わるのだろうか。中高年は給料が高い。長く勤めれば給料が上がったからだ。だから逆にそれは重荷になり、中高年からのクビ切りになった。この年功賃金のしくみが企業内からなくなれば、年齢制限は弱められてゆくのだろうか。年功序列やそういった意識がなくなれば、中高年の門戸も広げられるのだろうか。そんなときまで待っていられるだろうか。
中高年になればリストラと転職先なしの世の中でどう生きていったらいいのだろうか。ただ漫然とその年が来るまで祈っているしか仕方がないのか。忠誠心や会社のためにがむしゃらに働いても報われない。それはいやというほど見せつけられてきたはずだ。しかし好成績を上げないことには企業には残れない。このジレンマのあいだで仕事量をどのくらいに調整したらいいのだろうか。
最初から企業に期待せず、力を抜くフリーターという選択もある。しかしこれは当然低賃金で、安定も保障もなく、中高年の姥捨て年齢までなんの手の打ちようもなくなる。低賃金だから雇われやすいという有利さはある。生活レベルをこの水準に合せて生きるという方法もある。
いわばフリーターは価格破壊のようなデフレ戦略ともいえる。逆に高給サラリーマンは右肩上がり時代に成功したインフレ戦略で、デフレ時代の曲がり角において、見事にその突出分が仇になったわけである。
40、50代になると確実に仕事がなくなる年齢に一歩一歩近づいてゆく。生き残る戦略なんてあるのだろうか。青テントのホームレスは完全に高齢者問題である。企業や市場の姥捨てが老齢期よりはるか先に前倒しされているのである。見殺しにされる中高年の年齢にどんどん近づいてゆくばかりである。
適者生存と資本主義 01/5/22.
進化論が反発を生むのは、淘汰という考え方があるからだろう。繁殖や生き残りに失敗したものはこの世になにも残さず、消えて去ってゆくだけの運命にあると断罪する。生きる望みを断ってしまう。
進化論は市場経済や企業戦略などの考え方にずいぶん転換された。逆にこれは自然界のことではなく、企業戦略の考え方から出てきた思想だといえなくもない。ビジネス社会の一種のルールの基盤であり、正当化のための信念体系でもあるのだろう。
自然界が企業淘汰を正当化するのなら、人間社会はこの淘汰をそのまま習うべきなのだろうか。経済や生計に失敗したものはそのまま見捨てられてしかるべきなのか。
ビジネス界では当然こういったシビアで非情な決断がまかりとおる。必要なきものは去れ、である。この世界で恩情や慈善を期待するのはお門違いであり、絶望と怨恨を生むだけである。この期待を過剰にかけたのが戦後日本の会社であり、日本人の生き方であり、そもそも根本から失敗するのが目に見えていた。
しかしこれはあくまでも経済界のルールである。残念ながら人間社会および人間の心理はそのようになっていない。善意や利他心からそうなっているというより、利他行為をおこなったほうが利益に叶うのである。
貧困に陥ったものは疫病や伝染病という富者にも貧者にも平等におとずれる危機をまねくこともあるだろうし、ひとり勝ちの富者は殺人や略奪、破壊、社会的非難の危険もみちびいてしまうだろう。人間の種内においては利他行為をおこなったほうが、見捨てるより、利益があると考えられる。
貧者を平等に経済的にも政治的にもひきあげたほうが、地域や集団において自集団たちを強めることができるだろうし、じじつ、平等で民主制の国家は自己破壊的な戦力を国民すべてから徴集することができるのだ。経済淘汰が激しい分裂・対立の国には考えられないことだろう。
適者生存、自然淘汰はあくまでも企業間のルールであり、人間の社会すべてには適用できない。慈善的な行為はかつては宗教がおこない、現代では国家がとりおこなっている。その断絶期には市場淘汰が激しくなり、慈善をになう宗教のかわりに国家が富をあつめる社会主義が勃興した。
いまはふたたび経済淘汰の力を借りようとしている時期である。国家の富の分配の方法がどうもうまく働かなくなってきたようだ。こういう断絶の時代には慈善を国家や宗教に一括してまかせるのではなく、富者や有力者がおこなうべきなのかもしれない。
けっきょく、攻撃されたり、危機が迫るのは自分たちであり、身近なものたちが慈善をおこなうほうがより自然に近いかたちなのだろう。われわれ個々人も国家にまかせて、あまりにも慈善心を失いすぎた。利他心が国家に棚上げされたままなら、私たちはたんに利己主義の醜い塊に過ぎない。
子孫存続と人生の意味 01/5/23.
進化論によれば、子孫存続に失敗したものは生きた価値がないことになる。私のような独身者にとってはたいそう気を滅入らせる思想である。また現代の少子化、晩婚化、自分主義の時代にはあまり適合的でないように感じる思想である。
進化論によれば、血縁の繁栄に手を貸せば報われるからいいのだとか、こんにち人類はミームという文化的遺伝子に操られているということになっているそうだ。なんだか自分で考え直さないことにはいまいち納得しない。
子孫存続をしなかった人間は意味がないのだろうか。子どもを残さなかった人間は進化論的には失敗で生きた価値がないのだろうか。遺伝子や進化論の考えを極端にすれば、こういう考え方が導かれるのは防ぎようがない。
進化論がこんな冷厳な選択を告げておきながら、あるいは子孫繁栄が歴史のなかの民衆の願いであったにかかわらず、現代はおそろしく子孫存続をないがしろにしている。
進化論はこんにちの少子化、晩婚化、自分主義をどう説明するのだろうか。文化や科学があまりにも重要になった人種は子孫存続より、こちらのほうが子孫繁栄に手を貸すことになるからだろうか。「遊び」や「創造」のほうが自集団の利益に叶うからだろうか。ミームは遺伝子存続により貢献するのか。
われわれの時代のヒーローはあまり子どもを残さない。哲学者もそうだし、芸術家にあまり子どもは似合わない。社会の風潮からして子どもを育てることの気もちが薄れている。
皮肉なことに「豊かな」先進国ほど、育児の環境や費用は悪くなる一方だし、親が生き残る環境も厳しい。ますますカネがかかり、より多く労働しなければならなくなっている。子どもが息をしやすい環境からかけ離れてゆく一方だ。豊かさは子孫存続という点ではどこかボタンをかけ違えている。
人口抑制のブレーキがかかったのか、それともほかの個体の存続抑制の策略でも働いているのか、あるいは遊びや多様性の模索期でもあるのだろうか。ともかく現代人は子孫存続にあまり興味を示さない。
どうしてなのかはよくわからないが、そういう者にたいして進化論の子孫第一主義はあまりにも手厳しい。意味や価値を創造できる価値判断が必要だと思う。人間の知性なんてたかが知れているから、全部の真理を知ることなんて不可能だと思うから、せめて生きる意味を与える思想が必要だと思う。あるいは子孫存続を第一に考える思想体系にもどったほうがよいのだろうか。
「貧者は死ね」VS「貧者を救え」 01/5/25.
エドワード・ウィルソンの本におもしろい指摘がある。中世に魔女裁判がおこったのは「貧者を救え」という教えと「働かざるもの食うべからず」という教義が衝突したためだというのである。明確な方針を失った社会がその罪の意識を魔女裁判によって正当化したのである。
これはキリスト教と資本主義の衝突だともいえるだろう。貧者を救えといってきたキリスト教は、新しく勃興してきた貧者を見捨てる資本主義の力に打つ手を見出せなかったのである。
「適者生存」「自然淘汰」「弱肉強食」の進化論はとうぜん資本主義のパワーに貢献したのはいうまでもない。貧者や劣者、敗者は自然が淘汰するという思想はすこぶるビジネス的である。この思想が暴走すると優生思想や差別がおこる。
これに対してキリスト教の衣鉢をつぐのが社会主義であり、平等思想であり、福祉国家なのだろう。「貧者を救え」という伝統を継承したためだろう、社会主義はすこぶる強烈な宗教的な様相をもつ。
「貧者を救え」という教義はひじょうに憐憫や良心に訴える。人間は弱いものに憐れみをかけ、助けようという同情や正義感をもつものである。これこそ人間たる由縁だと思いこみたいところだ。
しかしこのような博愛社会では、ほんらいの人間の競争心や優越心が発揮されず、経済や社会は停滞・沈滞するという考えが最近ではかなり強くなってきた。「貧者は足をひっぱるな」というのが現代の「トレンド」である。
人類は利己主義と利他主義のあいだをずいぶん揺れ動いてきたようである。人としては貧者を救いたい、しかしそれでは経済を発展させる優越や競争が働かない。振り子は極端から極端にゆり戻されるようである。
このような時代背景に生まれてきた進化論は自然界の真実を語っているというよりか、もろ資本主義や経済社会のイデオロギーである。目線はちゃんと自然界まで届いているのかと懐疑するくらいだ。「利潤」や「利益」を遺伝子といいまちがえていないか。
進化論はヒジョ〜にひとでなしの思想である。繁殖や生存に失敗した個体、あるいは遺伝子は生の意味や価値を否定される。キリスト教が反発したのは当然である。そもそも宗教は繁殖や生存に敗北することから出発し、権力を得てきた勢力なのだから。
宗教は敗者の利他主義というシステムを完遂させたのである。資本主義は経済的勝者による自然的利他主義を含んでいる。つまり金持ちがまわりまわって社会を潤し、貧者に仕事を与えるだ。社会主義や福祉国家はそれを国家が代替する。
経済的利己心がまわりまわって貧者を救うのか。それとも利他的な国家が富者のカネにより貧者を救うのか。資本主義とキリスト教の亡霊はどちらが社会に受け入れられることになるのだろうか。
資本主義のルールを「抜き書き」したような進化論は冷厳である。ムダや無意味、遊びを許さない。人に「やさしい」思想でもないし、すべての人に勇気や希望を与えるわけではない。「共同幻想論」の立場をとる私としては人間に希望を与える思想のほうが人間にとっては健全で健康であると思うが、もちろん科学的探究心を否定するものでもない。
無欲と禁欲の進化論 01/5/27.
繁殖と遺伝子が人間にとっていちばん大切だとするのなら、宗教はなぜ無欲や禁欲を奨めてきたのだろうか。どうして繁殖にまったく貢献しない性的禁止の教えを広めてきたのだろう。
宗教によると人間に苦しみをもたらすのは愛欲や生存欲であるから、それを断ち切れば苦しみから解放されるといっている。逆説である。しかしそれによってかれは苦悩から解放されたかもしれないが、繁殖と進化の絆からも解放されてしまうのである。進化論からすればまったく意味不明である。
よく似た行為に利他行為や自己犠牲があるが、進化論は血縁の繁栄を利するから、それは損失をおぎなうと説明されている。
自己犠牲を無私の善意や英雄行為からおこなわれたと好意的に盲信するつもりはないが、この説明はなんだか説得性がない。人間は繁殖の道筋をはなれて、頭のなかの「自尊心」や「虚栄心」のために死ぬことができるという隘路に迷い込んでしまっているからである。
あるいはそれすら自集団の有利さを導くからだろうか。科学や芸術に秀でたものは自集団の有利さをもたらし、ひいては血縁の生存を高める。自尊心や虚栄心はちゃんと進化論に適った心の進化なのか。
こんにちでは自己の子孫を増やすことよりか、社会に貢献し、評価されたもののほうが価値ある高き生だとされている。科学や芸術、経済、芸能に優れたものが繁殖に優ると評価される。禁欲主義の宗教も社会的評価のルーツのようなものだ。こんにちの社会システムは繁殖より、評価を第一においている。
人間の社会は繁殖を下等なものとし、脳を高等なものに祭り上げている。脳に快楽や安楽をもたらすものが至上のものなのである。進化論や遺伝子の考え方とは明らかに相違する。
これはいったいどういうことなのだろう? 繁殖は貶められ、ときには禁止されるのである。地上に残すものは子孫ではなく、脳内の評価や安楽であることを推奨されるのである。断種すらほめたたえられる。
しかし宗教のために滅んだ人種がないことから、必ずしも宗教は人種滅亡を企図したものではないことがわかる。脳はときには暴走し、個体や子孫の滅亡を謀ることがあっても、完全な死滅をめざしているわけではないのだろう。
社会的評価は人間の順位を決するものである。順位や地位の増大は繁殖に利するから、この競争が盛んになってきたと考えられる。繁殖のディスプレイが脳の競争にすりかわっているのである。
無欲や禁欲は逆説的に生の安楽をもたらすものだが、生存や繁殖にかんしても同じことがいえるのだろうか。生存や繁殖に激しく固執すればするほど苦しみが大きくなり、生が困難になる。執着から離れれば、生や繁殖に利することになるのだろうか。これは逆説的な教えなのか。
人間は脳に描いた世界観によって極端に人生を左右される。繁殖より、脳内の評価や快楽に重みをおいた現代社会は正しい道、まちがった道のどちらを歩んでいるのだろうか。軍配をあげるのは遺伝子の増大なのか。
オススメ・リンク  進化心理学、行動生態学の膨大な用語集。文献、ネット情報、ニュースなどたっぷりベンキョーできます。興味ある方には見る価値あり。
進化心理学、行動生態学の膨大な用語集。文献、ネット情報、ニュースなどたっぷりベンキョーできます。興味ある方には見る価値あり。
010531断想集
学問バカ 01/5/31.
学問バカというのは視野の狭さ、思いやりのなさ、融通のきかなさなどが批判されるようである。(大塚ひかり『愛のしくみ』角川文庫)
学問知識で頭がガチガチになった人間はガンコで自己中心的で、優越意識で人を差別しそうだと思われている。情緒が欠落していて、人間的な感情に欠けているとも思われそうである。
たしかにこれは学問知識の一面をいいあてている。知識というのは狭量で、ガンコで、思い込みが激しくなければ論者に勝つことができない。真理のためなら、人の感情や想いは削がれても仕方がないと思いこみそうである。
こういうのは受験エリートや理科系、技術系の人にしばしば見かけられそうである。頭のよさをハナにかけたり、人づきあいがヘタで、思いやりに欠け、人を人と思わないようなところがあるかもしれない。
人ギライのショーペンハウアーはこれは精神的優越にたいする凡人の嫉みであるから、優越を見せるべきではないといっている。たしかにこういう面から見ることもできるが、凡人が嗅ぎとっているものは知識の欠陥自体でもあるのだろう。
知識は学問バカが典型的にあらわすように、狭量で融通がきかなく、蔑視意識をもたせ勝ちなのだろう。言葉や見解は固定的なものであり、序列や選別を必要とするものであり、他人の感情や人づきあいを除外してしまうものである。
知識はあまり実践的なものではない。即行動に結びつけられるようなものでもない。書物や活字の中に閉じこめられるように流動的なものでも自由なものでもない。だから知識は実践や行動にはあまり役に立たなく、逆にそれを阻害し勝ちなのである。
知識におぼれる人はこういう欠陥にとくに気をつけるべきなのだろう。知識を絶対視したり、かたくなに守り通そうとしたり、万能視したりするべきではないのだろう。知識は敏捷なものでも、身軽なものでも、柔軟なものでもない。それらを阻害するものである。
知識や学問に縛られるとますます実践や行動からかけ離れてゆくことになる。しまいにはそれを祭り上げて、ガンコさや頭の固さはほとんど石仏なみになってしまう。
知識は敏捷さが必要な現実にはあまり役が立たないのである。学問バカにたいする批判は知識自体がもつ本質を鋭く指摘しているのだと思う。歪んだ性格はそれを目に見えるものにしているにすぎない。
五里霧中の人生 01/6/2.
私は社会に出て、なにをやりたかったのだろう? いまだにわからないし、思い出してみたら、考えてみたことすらない。
将来の夢とか計画をほとんど描いたことがない。計画を描く人生がよい子ぶっているようでいやだったし、そのほうがよいのだと思っていたのかもしれない。
漠然と将来のすがたは思い浮かべていたかもしれない。サラリーマンになって結婚してみたいな人生は、消去法的には描いていたかもしれない。しかし現在、そういった、ふつうでまともな人生すら送れていない。
現在の暗中模索の人生の結果を考えてみるのなら、人生の計画や夢を描くのは大切なことだったかもしれないのかなと心が揺れる。
人生のヴィジョンを描かなかったら、なにも得られないし、なにも果たされないのではないかという気もちがする。いきあたりばったりに流されるままに人生を送っていると堕ちてゆくばかりなのだろうか。でも心の底からわきあがるような人生のヴィジョンを描けないのなら、借り物でしかないわけで困ったものだ。
私は社会人としてなにかをやりたいとほとんど思ったことがない。目先の好きなこと、やりたいこと、あるいは逃げ出したいことばかりにかまけて、なにひとつ得ることがなかったように思える。
趣味としては本をたくさん読んだり、文章を書いたり、人生や社会について考えはしてきたが、社会の中でなにをやりたいとか、なにを得たいとか、なにになりたいとかのヴィジョンはてんで描かなかった。それはいまの五里霧中の私の境遇に結びついている。
私は会社人間のようにはなりたくなかった。会社や仕事ばかりの人生は送りたくないと思ってきた。たしかにそういう人生からはドロップアウトしてきたが、やっぱり心のどこかには社会的評価やきちんとした人間であること、安定した将来をのぞむ気持ちがあるのは否めない。このまなざしが私に再考をうながせる。否定だけでは人生の果実を得られないのではないか。
社会のなかでどんなことをやりたいのか、なにを得たいのか、はっきりと人生のヴィジョンを描くことが必要なのかもしれない。
学生のころにはまったく思い浮かばなかった。企業や仕事のことがぜんぜんわからなかったこともあってと思うが、現在のところもまったくわかっていない。人生の目的や目標、役割すらわからない。
子どものころには恐竜博士やマンガ家になりたいと思ったことがある。しかし飽き性のためそんな夢は潰えた。いまもなにかがやりたいと思っても、自信と持続力がなくてたいがいさっさとあきらめる。ますます人生のヴィジョンは瓦解してゆくばかりである。
人生の計画や夢はしっかりと描いて、その実現に向けてがんばるのも必要なのかもしれない。さもないとただ時間のみがだらだらと過ぎ去ってゆく、なんともとりとめのない茫漠とした私のような人生を送ってしまうことになってしまう。
私は社会でなにをやりたいのだろうか。。。?
労働逃亡者のアンビバレンツ 01/6/4.
仕事と会社ばかりの人生を送りたくないと私は思ってきたが、一方ではカネや将来の保証はほしいし、プライドを満足させる仕事をしたいというものすごい矛盾をもつ。このアンビバレンツがけっこう苦しいし、私をさいなます。
仕事から逃れたり、怠けようとして、いちばんツラくなることは、会社側からまったく信用されないことである。責められたり、批判されるのもツライ。会社に雇われるしか生計の途を立てられない私は、会社からまったく見向きもされないことも恐ろしいことである。
仕事から逃れようとしてるのに、一方では花形的な職業や専門的な仕事なんかにも憧れたりする。仕事を拒否すれば、だれでもできる、どうでもいい仕事ばかりに落ち着かざるを得ないのだが、そんな道を選んでいながら、一方では空しさに耐えられなくなり、仕事の充実やプライドを強くのぞんだりするのである。
ものすごい矛盾である。一方を捨てているのにもう一方を得たいと思っている。片方を捨てながら、両方を得ることなんてできない。きっぱりと割り切ることができないのである。
働くことを減らそうとすれば、とうぜんカネは得られない。消費や生活費を削ることはそんなに苦にはならないが、将来や老後の保証も得られないし、企業から得ようとするのも虫がよすぎる話だ。私も少しばかり結婚や子どもをもちたい気もちがないわけではないが、いままでの信条と経済状況ではいつまでもたっても得ることができないだろう。
ふつうの人は仕事を減らそうなどと考えてもみないみたいである。働けばカネが儲かる、カネが必要だからもっと働き、稼ぎたいと思っているようだ。仕事の条件と前提を疑ってみることなんてまずなくて、カネが増やせるか、がんばればカネがより多く稼げる、そんなことしか考えていないみたいだ。仕事量や会社は変えることのできない自然の絶対条件のようだ。
労働逃亡者はこの経済社会のなかではぜんぜん市民権や容認をうけていない。ぽつぽつと労働の縮小や経済成長からの脱出などを告げる人はいることはいるが、指定席や居場所が与えられているわけではない。企業社会のまえでは太刀打ちも、座席もないのは当然である。ヒッピーなんてものも人々の視野から消え去って久しい。
二兎は得られないのである。一匹の兎を追ってしまったからには、もう一方の兎は得ることをあきらめなければならないのである。私はまだそのあきらめがつかない。たえずもう一方の兎を指をくわえて羨ましがるのである。
経済的富裕や経済的保証はほかのものを犠牲にしないと得られない。労働からの逃亡も安楽のみを得られるのではなく、経済的な犠牲も絶対的について回るのである。社会的なプライドや自尊心だって犠牲にしなければならない。それが労働からの逃亡にとうぜんついて回る犠牲なのである。
労働の縮小はそれを補って余りある人生の時間や充実をほんとうに得ることができるのだろうか。人生の宝はほんとうにそこにあるのだろうか。私は迷いっぱなしである。ひとつの安楽はひとつの犠牲を招く。片方の安楽を得て、もう一方の安楽まで得ることはできないことをしっかりと心に刻むことだ。私は片一方の安楽しか見ていなかったようだ。
金儲けのほかに何もないのか? 01/6/5.
いまの社会は金儲けしかない。金儲けのシステムのみが社会に貫徹し、人生のはじめから終わりまでが目的づけられている。
だから成功した経営者やまじめなサラリーマンなんかてんで尊敬できない。軽蔑の念しか思い浮かばない。
日本社会は金儲けのほかの価値観が悲しいほどぜんぜんない社会である。近代化によって見事にほかの価値観を削ぎ落としてきた。
ヨーロッパでは合理化や効率化がおしすすめられる一方、中世的な価値観や宗教もしっかりと残してきたのである。
日本には金儲け以外の価値観がほぼない。経済化されすぎているのだ。経済合理性に対立する宗教集団や価値集団、もしくは親族、世論といったものがまったくない。おかげで金儲け以外の価値観が容認されず、座席もない。そこが恐ろしいというか、嘆きたいというか、呪いたくなるところだ。
経済合理性のみに一元化された社会に、一生を賭けるに値する価値観や目的はあるのか。金儲けのみに終わる人生に情熱や目標を見出せない。これのみで終わる人生になんの価値があるというのか。
ではそのほかに何があるというのかというと、ものすごく難しい。対立するような価値観――宗教や共同体などはことごとく批判や壊滅がおこなわれてきたからだ。金儲けの価値観はほかの反対勢力に有無をいわせないほどの勝利をおさめたのだ。
論理では対決できないほどである。でもそのほかの価値観があるという思いは拭い切れない。何かあるはずだという思いが強いが、それが何なのかわからない。
文化や芸術なのか。やはり宗教的価値観なのか。それともボランティアや福祉のような利他的な価値観なのか。また経済に抗しうるような武力的な価値観なのか。あるいは経済合理性が壊しつづけた人とのつながり、共同体の一体感なのだろうか。
金儲けだけの社会は人生の崇高な目標がない。生涯を賭けるに値するものではない。日本は金儲け万能社会をつくるさいにほかの価値観をあまりにも壊滅しつづけたために、人生の目標や価値観をも壊滅してしまったのである。情けない、哀れなカネの亡者だけが日本に大量生産されることになった。
いったいこれからの時代はなにが目指されるべきなのだろう? 金儲け以外の、崇高で生きるに値する価値観をわれわれはつくり、そのような姿で楽しむ親たちを子どもたちに伝えてゆくべきなのである。われわれは金儲けだけの人生を子どもたちに誇ることができるのだろうか。少なくとも私はそんな親の姿を軽蔑してきた。
身近な動物の話で一息 01/6/6.
孤独でさみしくてヒマな毎日を送っていると、身近にいる動物がみょうに愛おしく感じられたりするものだ(涙)。ハトにエサをあげる老人の気もちがよくわかる。動く、生き物と関わりたくなるのだ。
公園で休んでいたりすると決まってハトが近寄ってくる。エサがもらえると覚え込んでいるのだろう。そうすると目の前でオスのハトがメスのあとを追いかけて求愛しはじめる。メスが迷惑そうにとことこと逃げる。どこの公園でも同じ光景が見られる。
交尾しているカップルを見たこともあるし、くちばしをつつきあっているカップルもいた。ハトも人の知らないところで愛に勤しんでいるだなと思う。
スズメはハトより人馴れしていないが、だれかがエサをあげていると、すばやくかっさらってゆく。五月ころに軒先に巣をつくるなんて知らなかったが、探してみたら、かわりに近くの軒先にツバメの巣はいくつも見つけられた。ツバメは農村だけで都会にはいないと思っていたが。
カメは近くの神社や寺の池、川の合流点でよく見かける。人が寄ると隠れるばかりか、近づいてくるのは意外だが、よほど餌付けされているんだな。どこのカメもミドリガメばかりだ。むかしからいたクサガメとかイシガメはあまり見かけない。
子どものころは用水路でごろごろ落ちているクサガメを拾ったものだ。黄土色のイシガメは見つけられたら四つ葉のクローバーなみに大喜びだった。私はカメがずいぶん好きだった。のんびりした、ずんぐりした、間抜けな感じがたまらなく愛おしいのだ。
私はイヌ派である。へりくだったり、お愛想をふりまくるのが好きである。もしかして人間より好きかもしれない。いまはマンションで飼えないけど。
飼っていた鳥が馴れた記憶はあまりない。ウサギもてんで馴れず、コードをかじりまくり、憎まれ者は車の下に逃亡してしまった。
ネコはどうも苦手である。馴れないところや傍若無人のところが私の手におえない。まえにノラ猫と仲良くなって、私の部屋にやたら入りたそうにしていたが、じゃれるとツメを立てられるのが困った。私はイヌのほうが好みだが、ネコ好きのほうが自立した人ではないかと思う。
ハイキングで大阪府の近くの山に登ったりしても、動物はほんとうにいない。鳥はたくさんいるが、動物はまず見かけなかった。餌付けされたサルとイノシシくらいだ。残念である。せっかく自然の中に入ったのだから、たくさんの野生動物と会えたらうれしいのだが。でもむかしみたいにオオカミとかヤマイヌとか、クマとかイノシシに出会ったりしたら恐いどころじゃないだろうけど。
まあ、なんでもない話だけど、最近、動物の本をよく読むようになって動物に目が向くようになった。そういうことでちょっと動物のことを話したくなっただけである。
010611断想集
カネとしての知識 01/06/11.
いまは金欠でほしい本がぜんぜん買えない。追究したいテーマの本は高くて買えなくて、すこしでも興味ありそうな100円本ばかりで渇きをしのいでいる状態だ。
金欠のときつくづく思うのが、知識とはカネなんだということだ。カネがなければ知識は得られない。ひとつのテーマを知りたいという深い執着心もたちまちしぼんでしまう。
知識はカネでしかないというのはなんかおかしな気がする。知識はカネとまったく違うもの、もっと高尚な次元の話だと思いたがっているが、知識もやはりひとつの消費や商品でしかない。
私はあえて避けてきた。物質的消費や金銭的商品の無意味さや無価値さはいつも批判視してきたが、知識もそれと変わりはないということだ。
物質消費と違うと考えたかった根拠のひとつは、知識はファッションやモノと違って、内面的な豊穣さや知恵をもたらすということだ。かんたんに目に見えるモノで誇示したりしないから、物質消費とは違うというわけだ。
でもやっぱり知識も商品にほかならない。私が批判視しているファッションやブランド品とほとんど変わらない。金欠のときにそれをつくづく思い知らされる。
ファッションやブランド品を買うというのは、「私はカッコイイ」とか「私はブランド品のように価値がある」というメッセージや記号を買っているということだ。私にとってはそういう物質的な誇示にたよる浅はかなナルシズムが羞恥をもよおすのだ。
知識も商品である。街を歩いて見せびらかすような大々的な誇示はないが、やはり「私は頭がいい」とか「知識を理解したり、洞察したりする能力がある」という満足やメッセージを買っているのだろう。他人向けではなくて、自分向けにである。
ブランド品には人に見せる満足と自分に対する自己満足があるのだが、知識は自分自身に内閉する自己満足の要素が強い。人に見せなくても、「自分ってけっこう頭がいい」とか、「理解力がある」だのという自己満足の無限循環である。知識はかなりのところ自己満足の商品なのだろう。
知識追究、またはカネ使いがとめられないのは、物知りというのはどこまでも他人との知識量競争があるからだ。知識で人に勝ったり、意見をいったりするためにはどこまでも知識を得なければならない。つまり湯水のごとくカネを使わなければならない。知識はカネや商品となんら変わりはなくなる。
知識は知識のためにある、知識自体が目的だと思いこみたいところだが、カネがなければ知識が得られないという現状は、やはり知識は商品やカネに相当するものなのだろう。頭脳や能力の優越を買っている。ときには他人に優るための優越として購入されることもあるのだろう。
知識は優越や競争である。仏教や老荘がいうように、私はいつこの消費競争から降りて、知識の囚われから自由になれるのだろう。そのためには知識の無意味さや欠陥、弊害が知られる必要があるのだろう。
怖がらせる男――大阪小学生殺傷事件の犯人像 01/6/13.
すぐケンカをしたり、怒りやすかったり、にらめつける、といった男はたいていどこにでもいる。そういう被害をうけた人はいくらでもいることだろう。
人に恐れをもよわせたり、不快感を与えたりして、他人を怖がらせる。そういうことを目的にした男はできれば関わりたくはないが、いることはいる。
価値観や人生観といっていいかもしれない。他人を怖がらせることによって自分の優位や安全をガードできると思い込んでいるのだろう。まわりの者はたまったものではない。
大阪池田の小学校乱入殺傷事件の犯人はそういう人物ではないかと思う。経歴や人物像が明らかになってきたが、起きるべくして起こった犯罪の感を強くする一方だ。
この人物は職場の数々で問題をおこしている。人生観の根底には自分の気もちや思いに忠実にならないと、攻撃してもよい、といった思考タイプをもっていたようだ。自分は正しく罰したのだという思いをもっているから、行く先々で人々を傷つける行動パターンを示すことになる。
こういう人物は身近によくいるはずである。そしてなんでも他人のせいにする「他罰的」な性質が、精神障害者は罰せられないという法的な知識と結びついたときに、犯罪を容認する怪物ができあがったのではないかと思う。怪物は自己を正当化する隠れ蓑を見つけたわけだ。
こんな危険な人物がバスの運転手や小学校の職員などの公務員として暮らしてきたというのが信じられない。犯人はなぜか国家とか政府の関係が好きだったようだ。安定や国家のトラの威を借りたがるタイプで、そこから脱落すると人生も終わりだと逆恨みする。
結婚や離婚も四回も経験し、よりを戻そうと裁判もしている。ストーカー的な行為にもおよんでおり、前妻や親に被害を与えるために犯行をおこなったという自供もしている。
なんでも他人のせいにする他罰的な人間は、憎悪の雪だるま状態に生きざるをえない。他人が自分の思い通りにならなかったら、憎悪はやまないからだ。そして自分を自分自身で痛めつけ、傷つけているということに気づかない。
「復讐するはわれにあり」である。犯人は妄想ではなく、他罰的な思考パターンをもったがために自分をさいなまし、その回復をはかるために他人を憎悪し、懲罰しようとし、ますます自分を不快と怒りの地獄に追いこんだのである。怒りの火は他人を燃やしたのではなく、自分自身を燃やすのみなのである。
これは妄想ではなく、思考パターンであり、世界観の問題である。われわれの社会はこの思考のパターンをチェックしたり、矯正したりする社会精神をもたない。思考のパターンはある方向に流れつづけ、とどまることを知らない。心理的な知恵はなぜか宗教嫌悪によって日常に流布しない。日常の社会にこのような知恵がないことは危険なことである。
小学生の殺傷事件は神戸、京都とつづき、大阪におよんだ。関西ゆえんの事件なのか、それとも因果はないのか。不満の表出や解消方法に問題があるのだろうか。人生の不満や怒りはどのように解消されるべきなのだろうか。それらを吸収する機能はわれわれの社会にあるのだろうか。
女性は企業戦士をどう思っているのか 01/6/14.
女性たちは男を哀れに思っているのではないだろうか。朝から晩まで会社に人生を捧げる生き方を「ヒサンだな」、とか「よくやるよ」とか思ったりはしないのだろうか。
あんな人生を送りたくないと思う女性は結婚や専業主婦の道を選ぶ。女性はまだ逃げる道があるからいいけど、男は逃げ道がない。
もし逃げるとすると経済力のない男は見下げられ、失敗した人生だとして相手にもされない。女性は三高とかいわれた経済力のある安定した男性をゲットし、主婦生活を謳歌する。午前帰りの夫をかわいそうだなと思いながらも、経済力の見返りを期待する。
そして子どももその夫のようによい学校に行かせ、よい会社に勤めさせ、企業戦士化させようとする。この企業社会の元締めはじつは女たちだったのだろうか。自分は激しい競争社会を避けておいて、安定した経済力だけをいただく。
もちろんこうしたラクな生活の見返りには自由や自立、人格の尊厳や平等といった大切なものが女性からとりあげられてきたわけだから、一部の女性は自立やキャリアをのぞんできた。
こういう流れがある一方、大半の女性は経済力のあるブランド男をゲットし、これまでの安楽な主婦の立場を手に入れようとする。どちらかといえば、こういう女性のほうが大半で、身近にもたくさんおり、主流ではないかと思うのだが。
そのような女性に対応して地位と経済力をのぞみ、専業主婦タイプの女性を手に入れようとする男性もたくさんいる。男の主流もこのようなものだと思うが、私は女性を経済的にサポートしたいという気力は希薄だけど、そういう経済力のない男性は女性を手に入れる資格はないという思いこみも拭いがたい。
自立と依存が奇妙に同居しているのである。自立をのぞむ女性がいる一方、是か非でも依存にしがみつく女性もいる。依存する女性がいるから、自立を叫ぶ女も信じられない。一方では依存と自立を両方都合よく手に入れようとしているんじゃないかと勘ぐってしまう。
私としては女性は自立と自由を勝ちとってほしいと思う。それは「男の解放」につながる自立であってほしい。一方では男の犠牲のうえに築かれた依存を必要とするのなら、そんなのは自立ではないと思う。
女性は自立して、男を企業戦士化される人生から、ぜひとも解放してほしいと思うのだ。そんな会社人間を女性は見限って、捨ててほしいと思う。そのような女性の自立は男の解放と自由をもたらすだろう。そして幸福になれない日本のシステムから解放されて、男女ともどもの幸福がもたらされると思うのだ。
男を幸福にしない企業中心システムはもちろん女性の一方的な企みによってつくられたのではない。ただ支持や順応があったのはまちがいない。企業戦士に依存する女性がこのシステムを支持するかぎり、男は生涯を企業に捧げて幸福になれない。女性は不幸なこのシステムを下支えしているのだ。自立と自由をのぞんでいるのなら、ぜひともこの哀れな企業奴隷の男たちも救ってほしいと、私は女性に願うばかりである。
月並みで平凡な幸福 01/6/16.
月並みで平凡な望みをもてるほうが幸せなんだと思う。
人はそれを軽蔑したり、バカにしたり、向上心がないとけなしたりするものかもしれないが、望みがかなわない不幸を背負わなくてもいい分、よっぽど幸せなんだと思う。
月並みで平凡な望みをもっているとたいていはかなうし、競争やムリな努力をしなくてもいいし、欠如や欠点ばかりに目が向きがちになるということはない。
月並みで平凡なことに幸福を見いだせる人のほうが、成功やエリートになることのみにしか幸福を見いだない人より、よほど羨ましいと思う。そういう人であったら、苦しむことも少なかっただろう。
私は成功やエリートになる望みなんかはほとんどもたなかったが、軽蔑や批判ばかりを育んできたように思う。ブランドの会社や一流企業、安定した公務員になることを軽蔑してきた。
エリートに反逆する意識は強かったが、裏返してみたらそれは主流のエリート志向とは違った傍流のエリート志向にほかならないんだろう。エリートコースをつっぱねることによって、違う優越や自尊心を手に入れることにほかならない。
勝ったり、優越したりすることを望んできたわけだ。いまさらながら、自分の浅はかな望みに気づいたことが、われながら恥かしい。主流に対する軽蔑や反抗は、優越や勝利の望みだったわけだ。主流のように隷属的でラクなものなんか目にもくれない強さがあるということである。
軽蔑することによって、自分をほかと違う高い位置におくというからくりである。いろいろな人や物事を軽蔑してきたから、平凡でささいなことに幸福を見いだない体質になってしまったように思う。
われながら奇妙なからくりにはまったものだと思う。自分では主流的な優越志向は強くないと思っていたから、逆説的な優越志向にはなかなか気づかないものである。そしてそれが平凡な位置に不満や不幸しか見いだない原因をつくりだしたのだと思う。
軽蔑や反抗が自分を高い位置におくというからくりは、なかなか気づきにくいものだな。そしてそれがますます自分を追いこんでゆくのである。
優越心や自尊心をどこまでも育んでゆくと、どんな位置でも満足しないし、どこまでいっても不満と欠如をかこいつづけてしまう。
軽蔑は成長志向と優越志向に火をつける原動力である。いろいろなことを人は軽蔑し、蔑んでみてしまうから、どこまでも上昇や競争をやめることができない。
月並みで平凡な位置に満足し、幸福を感じる力というのは偉大である。踏みとどまる力も必要だろう。
ましてや現代のように成長や上昇が重視される時代に、しかもそれが「軽蔑」や「みじめさ」に煽られる時代に、平凡なことに幸福を見いだしつづけられるのは容易なことではない。とどまりつづける力が必要なんだろう。
優越や成長、上昇を自分のなかに組み込まれた人間はなかなか安住の地を見いだせないだろう。それこそが安住をはばむ原因なのだから。自分のなかの抜かりない優越心や自尊心に警戒すべきなのだろう。いいや、軽蔑するまなざしがいちばんの元凶である。
干潮があり、風は吹く 01/6/17.
「潮には干潮があり、風は吹く」――アン・バンクロフト『20世紀の神秘思想家たち』(平河出版社)にこういう文章がある。「だがその原因は私ではない」
「それと同様に足は運ばれ、食物は食べられ、本は読まれる。しかし、そこに自己は関係していない」
「行為者としての自己がないという感覚は、みごとな解放感をもたらしてくれる。不必要な重荷を捨て去った感覚だ」
同じようにこうもいえるだろう。川は流れる。その原因は私ではない。
雲は流れる。私が動かしたのではない。
雨が降る。私が降らしたのではない。
太陽は昇る。私の意志によるものではない。
私という存在も、行為も、そのようなものだと見なせるだろう。
なぜ労働は「善」で、怠慢は「悪」なのか 01/6/18.
なぜ労働は「善」で、怠慢は「悪」なのか。労働は無条件に「善」であり、太陽が昇るから会社に行くみたいに自然なものだろうか。
われわれはなぜ労働を無条件におこなうもので、「善」であると信じてきたのだろう。われわれは蓄えが少しばかりあるとカネを稼ぐ必要に迫られないわけだし、毎日毎日働いて得なければならない必要なものってそんなにあるものだろうか。
そもそも労働って絶対的に「善」なるものだろうか。労働はみんなが評価し強制させるに値する、社会や自分にとって絶対不可欠で、神かがり的に「善」なるものなのだろうか。
サギ商法まがいや押し売り販売的な労働も多いことだし、企業の利潤追求や売り上げアップがまさか他人のためになされるとは思えないし、人がおこなう労働の多くは人の不幸や弱みにつけこんだものである。
なぜ労働は善的なものとして評価されてきたのだろう。もちろん個々人が生計を立てるためだったのだろう。しかし今はその範囲をはるかに超えて、「労働」と「会社」に囲われることが「正義」であり、「人間の条件」になっている。
労働ではなくて、「会社」や「集団」に強制的に所属させられることが「善」になっている。むかしはそれが「戦争」であったりして、いまはそれがたまたま「労働」になっているだけかもしれない。
かつては労働はできるだけ逃れたい悪であったはずだ。こんにちでは人生を捧げるに値する善だとされている。ホンマだろうか。会社に洗脳されたり、首根っこをつかまれているために仕方なくそう思い込んでいるだけではないのか。労働はできれば逃れたい何かではなかったのか。
マイホーム・ローンや社会保険、教育費、車などのローンのために人々は労働から逃れられない。ステータス競争にまんまと捕まってしまった者が、逃れられない腹いせに労働善説を叩きこんでいるのだろうか。
私は労働は善だとは思わない。社会の片隅にはめこまれたり、断片的な機能に同一化させられる不幸は救いがたいと思うし、人間は労働のほかにもっと大切なもの、文化であれ芸術であれ人生の哲学であれ、また人のつながりであったり、休息やゆとりであったり、もっと重要なものがあるように思える。
ぜひとも労働が善であるという不文律は解体されるべきだと思っている。そこから人間らしさや人間としての幸福が生まれてくると思っている。労働と消費というサイクルのみに人生の目的や安寧のみを見つけようというのはまちがっていると思う。
モニター故障はなんとか免れていますが、
叩いて直す時間は長くなっております。
いつまでもつかわかりません。。。