020130断想集
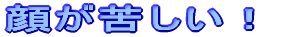
顔がくり抜かれた男の姿 02/1/23.
どこかで顔がくり抜かれた男の姿の絵を見たことがある。もし心を無念無想にしたり、自我を無にしようとするさいには、この男の姿は「理想」としてイメージされるべきではないのかと思う。
もし自己のイメージから顔を抜き去ると、自分にはなにが残るだろうか。「顔がない私」は想像できるだろうか。「顔がない私」ははたして「私」だといえるだろうか。そしてこれこそが人間ほんらいの姿ではないのではないかと思う。「顔なし顔」を自分の姿としてイメージできたとき、私は凝り固まった「自我の病」から脱却できるのではないだろうか。
「顔がない自分の姿」は異様であると思う。不気味であると思う。恐ろしくもある。そもそも「自分らしさ」をそこに見出せるだろうか。自己の認識や個別性を識別することができるだろうか。おそらく自分は顔を失った体のみの存在としてイメージされ、自己は体や世界のなかに溶けてゆくだろう。自我を捨て去るとはこういうことではないだろうか。
顔にはいろいろな意味がより集められている。「自分らしさ」や「個性」、「個別性」、「自我」、または「人間らしさ」といったものまで含まれているだろう。顔がなくなったら、そういった「人間らしさ」の総称はすべて葬り去られる。逆にいえば、私たちは顔に異様で過剰な意味づけや内容を与えており、「自分らしさ」や「人間らしさ」という意味や表象は、すべて顔につみ重ねられているのである。
そしてこれは意外かもしれないが、これらはすべて頭の中の「空想」や「イメージ」にしか過ぎないという現実がある。つまり「絵空事」や「虚構」であるということだ。それらの「空想」はすべて「まやかし」であり、そしてすべて葬り去ることができる。われわれがあたたかく、大切に、重要な重みを与えてきた「自分らしさ」や「人間らしさ」といった表象=「空想」は、無残にもうち捨てられるのである。そのあとになにが残るだろうか。
ただ、「自分なし」の世界が残るのみである。そしてこれがほんらい私たちが生まれてきた世界であり、幼児のころはこのような世界を知覚しており、われわれはこの顔の表象=空想を捨て去ったとき、この世界にふたたび還ることができるのだろうと思う。
この方法を顔の感覚からもすすめてみよう。顔からの「脱同一化」である。私たちは一日のほとんどを顔の感覚に集中している。足や胴、腹や胸などの感覚に焦点を当てることはほとんどないといっていいだろう。「顔をなくす」というのはこの感覚集中を逸らすことである。
私たちの多くの人は顔に感覚を集中させて、おそらく顔の筋肉を緊張させたり、こわばらせたり、つっぱらさせたりしている。表情を、心の中の思いを、外にもれないよう、出ても他人の機嫌を損ねたり、悪くとられないような表情をとりつくろうため、たえず顔の動きやありかたに注意を払い、監視し、統制し、支配しようとしている。そうして心の中がもれ出ないようにずっと気遣っているために、顔の筋肉はあちこちがずっと緊張したままだったり、こわばったりしたままだったりする。
私たちは緊張の仕方をまちがっているのである。心の中の思いや感情、顔の表情などは顔の筋肉を緊張させることによって、ガードしたり、防御できるものだと無意識に思い込んでいる。しかし顔の緊張はただの筋肉の緊張にしか過ぎない。こわばった、緊張のとれない、重みが去らず、しなやかな表情のとれない、自由のない顔が生まれるだけである。
顔が自由にしなやかに軽やかになるためには、顔を「くり抜か」なければならない。つまり無感覚、感覚のない状態にしたほうがいいのである。体の感覚というのは調子のよいところはまったく無感覚で、調子が悪くなったときにだけ、感覚が向かう。だから感覚がないほうが、より自然で自由な活動がおこなえるのである。
顔の表情や感情は筋肉によって制御するのではなく、感覚をなくすことによってその自由さやしなやかさを手に入れられる。顔の感覚は、感覚の正体を見据えることによってしぼんでゆく。つまり感覚というのは「実体」のあるものではなく、「ない」、「存在しないもの」といっていい。「存在しないもの」と見なすことによって、感覚は陽炎のようにしぼんてゆくものである。
これを筋肉によってむりやりなくそうとしたり、ある感情や表情をむりやりとりのぞこうとしたりしたら、顔の筋肉の緊張やこわばりはずっと継続したままになってしまう。「なにもないもの」をとりのぞこうとして、ただ筋肉の緊張のみが「虚空」にとり残されるのである。
顔を、「無感覚」に、「無」にしてゆくにしたがって、われわれは顔の自然さや自由、安らぎを手に入れてゆくことができるのである。
顔について問う 02/1/30.
顔について問いたいのだけれど、意外や意外、顔を主題にあつかった本はかなり少ない。顔は哲学的にも、社会学的にも、心理学的にも深く鋭く問えるはずなのだが、昨今の書店にはほとんど見かけられない。ものすごく不満だ。心について語った本はたくさんあるのに、顔についての本はどうしてこう少ないんだろう。
書物が頼りにならないのなら自分で考えるしかないのだが、顔について考えることはかなり難しい。どのような問いを発したらいいのかすらも、そもそもわからない。とりあえずは間違ったことをいう懸念はともかく、やみくもにはじめるしかない。
私は顔を「消したい」と思っている。顔には「私」や「自分らしさ」、「人間らしさ」といった過剰で饒舌な意味が込められていると思う。この過剰な意味を――無意識的な思い込みを剥がしたいと思っている。人間の「幻想」の起源はここから始まっていると思うからだ。
いわば顔を「異化」したいのである。あるいは「脱擬人化」したいのである。当たり前に思っている自分の顔を、異物を見るかのように、あるいは人間についての過剰な意味づけを葬り去りたいのである。顔には過剰な意味づけも、「私らしさ」も、「人間らしさ」も、もともとは備わっていないと思うのである。それらは後からつけられた「思いこみ」や「錯覚」に過ぎないのではないのか。
人間は顔に「私」が宿ると思い込んでいるのではないだろうか。顔が「私」である。表情があらわれ、感情があらわれるところだからだ。しかし顔の筋肉の動きやひきつりが「私」であるわけがないし、感情や気分のみが「私」であるわけがない。
「私」を主体的に思い浮かべるとき、だれもが自分の顔を思い浮かべるだろう。しかし顔は「私のすべて」ではなく、一部分であり、身体のひとつのパーツにすぎないはずである。そもそも意味すらない物体であったかもしれないのだ。
たしかに顔は「心の窓」といわれるように感情や気分がもっともあらわれるところだし、視界や嗅覚、聴覚などの感覚器官も集まっているが、だからといってそこに「私」がいちばん集まっているとはいえない。視界の中心は目であり、顔だから、私の中心と感じやすいのかもしれない。しかし視界の中心が「私」というわけでもないだろう。
顔は意味であり、情報であり、メッセージである。怒っていたり、悲しんでいたり、恐れていたりする表情をしていると他人がその意味を読みとる。顔は自分の思考や感情が図らずもあらわれるところである。本心や本音を悟られないように私はあわてて表情をとりつくろうとする。あるいは他人受けするように表情をつくろうとする。
顔とは戦場である。自分が心の中で思っていることと、他人に読み取られたい思いや感情が拮抗する戦場である。本心のまま表情が現れたら社会上都合が悪い。顔を抑えつけようとする。感情を抑えつけようとする。微笑みや愛想笑いを心がけようとする。そして失敗する。顔はひきつり、緊張し、硬直する。顔をとりつくろうとすればするほど試みはドツボにはまってしまう。
顔に本心が現われてしまうことはもう仕方がないことなのか。とりつくろうことは不可能なのか。思ったり、感じたままの表情で生きることもできるが、よほど度胸が座っているか、天真爛漫でないかぎり、社交上、あまり好ましい方法ではないだろう。表情の現れる元となった思考や感情を消してしまうという方法がある。なにも思っていない心には表情は現われないからだ。これもひとつの方法だろう。
あとひとつ模索したいのが、心と表情のつながりを切ってしまうことだ。顔や表情の過剰な意味や情報を無化してしまうことにより、心と表情は断ち切れるのではないかと思う。表情というのは社会的な産物ではないのか。この社会的な意味づけを断ち切ってしまうことにより、表情はその役割や機能を失ってしまうことができるのではないかと思う。
顔には過剰な意味や役割が集積されている。そのために顔はある人にとってはやっかいな、手に負えない代物に化してしまうこともある。そうしたときに顔の意味をひとつひとつ剥ぎ取ってゆくことは、顔からの解放と癒しにつながってゆくだろう。そのためには顔とはなにかを問わなければならないわけである。
「防壁」としての顔の緊張 02/2/2.
他人によからぬ思いを抱いたとする。もし私が自己によい人のイメージを抱いていたり、他者の悪意を抑圧する習慣をもっていたりすると、顔はなんとかしてその表情を読みとられまい、禁圧しようとする。しかし顔にできることは筋肉の緊張であり、顔のこわばりであり、ひきつりである。
私たちは無意識に自分の感情を追い出そうとするとき、顔の筋肉を緊張させていないだろうか。顔を緊張させれば、その「不都合」な感情は防げると思っていないだろうか。
人はなんとまあ自分の感情を禁圧することだろう。他人の軽蔑や怒りはともかく、恐れや悲しみすら禁圧しようとしているのではないだろうか。他人への配慮から、私たちはその場の雰囲気を悪くさせるような感情をいっさい漏らさまいとするのである。
思いの最終局面はすぐに表情として現れるから、「不都合」な感情が現れるとたちまち、それをとりのぞき、あるいはガードしようとする顔の緊張が自動的に現れることになる。
顔は感情の防壁として筋肉を瞬時に固めるのだが、やっかいなことに今度は顔の緊張が当人にとっては人前で見せたくないものになり、隠そうとし、そしてその隠そうとする気もちがまたまた緊張の注目とエネルギーの増強をもたらす悪循環に陥ってしまうのである。
われわれはどこで感情の防御は顔の緊張で防ぐものだと覚えこんだのだろう。感情を物体のように力づくでなくすことができるといつ信じ込んだのだろう。われわれはほとんど無意識のうちに不都合な感情のガードには顔の筋肉の緊張を使うのである。
感情はモノではない。思いは物体ではない。思ってしまったものはもうなくせない。「空気」や「虚空」のようなものだから、それを筋肉や力づくでなくそうとするのは不可能だ。思いが表情にすぐ現れるとしたら、それはもう防ぎようがないのだろう。
他人に悪意をもつ人はもうあきらめて他人に自分の極悪ぶりを悟らせてありのままに生きるしかないし、悲しみや恐れのツラ構えでまわりを重い雰囲気にする人もそのままに生きるしかないだろう。
そういう自分も受け入れて、許すしかないのである。本心のまま、本音のまま生きるのがよいのだろう。われわれは社会上、そういった自分の片面を受け入れることができないから、顔の緊張や身体のこわばりや痛みなどの「鎧」を身につけざるをえないのである。
しかし表情ではなく、感情をなくす方法はある。感情というのは思いや思考によってつくられるものだから、それを消したり、無視したり、流したりすることによって、感情はなくすことができる。なにも考えず、なにも思わなかったら、なんの感情も生まれないのである。感情のガードというのは表情という「結果」ではなく、思考という原因から断たなければならないわけである。
それからいくら筋肉を緊張させたって、怒りや恐れ、悲しみなどの感情は去らないと自分と自分の顔に言い聞かせることも必要なのだろう。ガードしての顔の緊張は拭いがたく私たちの自動回路として定着してしまっていると思う。
顔の緊張はなにも防げないし、なにも隠すことができない。そのことを体でしっかりと覚えこんだとき、顔は「ほどかれ」、やわらぎと安堵の表情がわれわれの顔に戻ってくるのだろう。
筋肉で苦しみはこらえられない 2002/2/4.
なぜ、われわれは筋肉の緊張によって、苦しみや怖れなどの感情をこらえようとする間違いを犯すようになったのだろう? どうして筋肉の緊張が、感情を抑えこめると信じるようになったのだろう?
「唯物論」の時代のせいなのか。世の中、「モノ」と「物体」しかないと思いこむ時代では、すべてモノと同じ力学をもつと思い込んでしまうのか。
それとも単純な初歩的な過ちか。心や感情は「モノ」や「物体」ではないと知らなかったからだろうか。心や感情というのはモノでも物体でもなく、なんら「実体」のあるものではなく、「虚空」や「なにもないもの」なのである。
子どもは泣くのをこらえようとするとき、アゴの筋肉を緊張させることによってこらえようとする。泣いてはいけないといわれると、子どもはあわててアゴの筋肉でこらえようとする。泣くことや悲しみの感情は、子どもにとってはモノや物体のように圧倒的な力をもつものに感じられ、それに抗するには筋肉の力しかないと思い込むのである。
それは大人になっても変わらない。苦しみや悲しみを歯を食いしばることによって我慢しようとする。怒りは首や肩の筋肉を緊張させるといわれるが、この緊張だってもしかしたら怒りを抑えこもうとして力が入れられているかもしれない。
この筋肉の緊張のやっかいなところは、自分で自分の筋肉を緊張させておきながら、無意識であり、なおかつ自分でなかなか解くことができないことである。不安や悲しみ、怒り、ストレスなどを抑え込もうとすると、知らず知らずのうちに緊張が継続し、自分でとれなくなってしまうのである。
原始時代には獣や人間の敵と戦うときには筋肉の緊張は鎧となって身を守っただろう。しかし現代の敵というのは、なんら「実体」のあるものではなく、不安やストレスや怒りといった「虚空」のものである。そういった「すがたかたちのないもの」を筋肉の鎧によって戦おうとするのは完全に間違っている。筋肉の鎧は、じわじわと自分を絞めつけるばかりなのである。
筋肉の緊張はなにも防げないことを知らなければならない。それは誤った方法なのである。緊張によって苦しみを抑え込もうとしたり、ストレスをなくそうとするのはおおよそ不可能であることをしっかりと理解することである。
怖れや不安、怒りといったものは「なにもないもの」である。なんら「実体」のあるものではないし、目に見えるものでも、手に触れるものでも、すがたかたちのあるものでもない。こういうものには筋肉や力づくで抑え込むのはまったくムリであって、「空気」相手に闘いを挑んでいるようなものなのである。
感情をなくすいちばん手っとり早い方法はもう頭を「空っぽ」にするしかないだろう。頭を「真っ白」にするしかない。考えや思いのみが、不安や怒りをつくるのであり、だからそれを消すしかないのである。
そうやってどんどん思考を消していったところに緊張のゆるみがあり、緊張のほどきがあり、快適さとリラックスの証しである無感覚の状態がある。思考の消去の延長線上に筋肉の消去の感覚がある。
思考を消すしか方法がないというのは、ものを考えるしか「自分らしさ」がないと思いこむ現代人にとっては、たいそう屈辱的で虚無的なことかもしれないが、筋肉の鎧兜を脱ぐにはその回路の元である思考を捨てるしかないのである。さもなければ、ずっと解けない筋肉の硬直と痛みとともに過ごさなければならなくなるだけである。
顔はだれのためにある? 2002/2/6.
顔は自分には見えない。表情も自分で見ることができない。身体のなかでいちばん重要な部位であるはずなのに、自分に見えないとはいったいどういうことだろう?
顔は自分のためにあるのか、それとも他人のためにあるのか。自分には見えないということでは、まさしく他人のためにあるといえるだろう。
顔も、表情も、他人に見られるためのものとして、他人に差し出すものとしてある。他人のためにあるものなのに、顔は自分にとってもものすごく大切な部所である。
顔は「私」であり、「人格」であり、私の「個性」である。そのような精根こもった顔が自分に見えなく、他人に見せるためにあるとはどういうことだろう? 顔や表情という自分にとっていちばんこだわりや神経をそそぐ箇所が、他人に見られるためだけにあるとは、いったいどういうことだろう?
顔とは、通りに面した壁一面が開いている家のようなものである。思ったり、感じたりすることはすぐに顔に表われ、他人は容易にその表情を嗅ぎ分ける。見せたくない、隠したいものに限って、壁は大きく切り開かれているのである。トイレやシャワー室の壁に穴が開いているようなものである。
顔とはひじょうにやっかいなものである。読み取られたくない思いも感情も、すべて壁の開いた部屋――表情として丸見えになってしまうものである。そもそも顔や表情は他人に見られるために存在しているのである。
そんな穴の開いた壁のような顔なのに、われわれはさまざまな思いや感情を隠さなければならない。見せたくない。知られたくないのである。そうしてわれわれは筋肉の緊張を顔じゅうにはりめぐらせて思いや感情の露出を防げうとするのだが、こんどはその緊張がとれなくなり、その硬直した顔をさらに隠そうとするのである。
顔というのは自分のためにあるというよりか、他人に秘密をバラすためにあるような裏切り者といっていいかもしれない。図らずも顔から秘密がぼろぼろと露呈してしまうのである。
もし思いや感情が自分のためだけにあるとするのなら、顔や表情として外に表わす必要がない。顔も表情も必要ない。そうすれば秘密が外に漏れる心配はないし、思いや感情は自分のためだけに存在するといえるだろう。
しかしわれわれの顔と表情はわれわれの秘密や不穏な感情をダイレクトに外に漏らしてしまう。まさに顔とは他人が私の弱みを握るために存在するようなものである。
いっそ顔や表情がなければいいのにと思う。なぜわれわれには顔という心の漏洩装置があるのだろう。
ところでカエルには感情はあるのだろうか? かれらは顔ひとつ変えない。表情がないということは、感情もないということなのだろうか? つまりわれわれの感情というのは、表情があるから存在するのか? 表情がなければ感情は存在しないのか?
「表情=感情」とするのなら、感情も顔と同じく他人のためにあるということになる。自分の感情すら他人に見せたり、知らせたりするためだけに存在するのだろうか。自分のためにあると思っている感情や顔が、他人のための「伝達記号」にしか過ぎないとすると、われわれの「本質」や「核」となるものとはいったい何なのだろうかと猜疑心に襲われる。たんなる「伝達情報」を「自分」だと勘違いしているのか。
われわれは顔をたいそう大切に自分の核となる中心だと思い込んでいる。しかしこれは「他人にとっての自分」を大切にすることである。つまり他人の評価や思惑を奉るということである。他人にどう思われるかということを気にしすぎると、私は他人の奴隷や哀れな被虐者にならざるをえなくなるし、自分の自由や好みを剥奪されてしまうということである。
だから顔にあまり重要性や価値や意味をおいてはならない。顔に重みをおくということは、同時に他人の思惑や評価をどこまでも重要にするということである。顔の重要性を落としてゆくこと。「他人の見た目」という牢獄から解放されて、自由な境地を手に入れられることだろう。
顔が「私」なのか? 2002/2/10.
顔は自分のためにあるというか、他人のためにある「伝達記号」のようなものである。そういう顔を「私」だと思っている。他人に伝わる個性や表情がいちばん現れるところだからだ。
しかしたとえば手のかたちや足のかたち、指紋の違いが「私」だといわれないように、顔のかたちや違いのみが「私」だというわけではないだろう。
また、表情が「私」だというのはどうだろう? たしかに表情は私たちの心や感情をいちばんよく伝える。だが、まさかあいさつの手やOKの手のマーク、手旗信号などのジェスチャーが「私」だという人がいないように、表情もひとつの「伝達信号」にしかすぎないはずである。
また、眉の上げ下げや目の開閉、口の上げ下げ、などといった個別の表情筋の動きが、「私」だということもできないだろう。
腕の力こぶや筋肉隆々の体つき、胸や腹の筋肉が、とても「私」だとはいえないように、それはあくまでも、やっぱりひとつの筋肉の動きにしかすぎない。
そういう物体や筋肉の動きにすぎないものに、われわれは思いや気もち、感情といった心の過剰な意味や価値をまとわりつかせて、そこに「私」が宿り込むと思いこむ。
他人との関係に生きるわれわれにとって顔は重要である。しかしそれはあくまでも「伝達記号」にすぎないはずである。他人に見せる「看板」や「玄関」が、私たちにとっていちばん重要なもの、あるいは「私そのもの」になってしまっているのである。
顔に過剰な重要性を与えるとやっぱり問題がいろいろ起こってくる。他人との関係の問題が集中的に、あるいは象徴的により集まってくるのである。顔は他者との関係の「修羅場」になる。
ある人は自分の心が漏れるのを怖れ顔面を緊張させ、ある人は他人に嫌われる怖れを顔に集中させ、ある人は他人とうまくやれない関係を顔の表情に集中させたりするだろう。つまり、なんでもかんでも「顔のせい」にしてしまうのである。心の問題の「物体化」「肉体化」である。
まったく顔の「脱中心化」が必要だと思う。顔の「脱私化」、「脱人格化」というものが、だから必要となってくると思うのである。顔の「重要性」や「価値」というものを降ろしてゆくこと。
そうすれば顔という物体に集中させられていた心の問題がにわかに現われてくるかもしれないし、あるいは問題それ自体が消え去ってしまうかもしれない。「顔よ さらば!」である。
■パソコンにウィルスが感染してしまいました! メールに送った覚えもない相手から、「Re: 」という空の添付ファイルが送られてきて、たぶんそこから感染したのだと思います。それからパソコンを立ちあげると、勝手にメールに接続されるようになりました。
親切にウィルスに感染したことを教えてくれる人がいて、「W32/Badtransの亜種」に感染しているということと、対処ソフトのアドレスまで教えてくれました。
http://www.ipa.go.jp/security/topics/newvirus/badtrans-b.html
駆除ソフトを使ったのですが、でもなぜか駆除されませんでした。もういまはめんどくさいし、自動的なメール接続はこらちで止めることができるので、放ったらかしです。早く何とかしたいと思いますが、私のような技術オンチはめんどさくてたまりませ〜ん。。。(涙)
ご意見、ご感想お待ちしております。
 ues@leo.interq.or.jp ues@leo.interq.or.jp
前の断想集 020113断想集 2002/1/23.
書評集 020203書評集 チャネリング・アナザーワールド――顔の哲学 2002/2/3.
|TOP|断想集|書評集|プロフィール|リンク|
|