2001年桜の季節の断想集
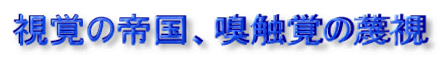
メディアは世界からの疎外をもたらすのか/知性=言葉の欠陥/メディアVS現場と行動/五感と身体感覚の価値/唯一無二の存在である自分/感覚のヒエラルキー/触わることの禁止/
メディアは世界からの疎外をもたらすのか 01/4/7.
メディアは遠くの出来事や遠くの人の思想、あるいは過去の出来事や思想をつたえ、保存するひじょうに重要な機能をもっているが、同時にメディアは人間のひとつの感覚器官しか使用しないというひじょうに欠点の大きい面がある。
言葉は耳しか使用しないし、文字や印刷物、写真は目しか使わない、レコードやラジオは耳だけ、TVや映画は目と耳だけといったふうに、人間の諸感覚の欠落をもたらす。
空間と時間を超えた情報や知識は、人間に歓喜と情熱をもたらし、とうぜんその感覚への傾斜や特化、至上化がおこなわれる。五感を排した一器官の特化はおそらく世界からの分離や分断をもたらすのだろう。これが集合的無意識の幸福な合一からの脱落をもたらしたのかは私にはわからない。
活字文化と印刷文化においては視覚が感覚の王座を占め、聴覚は重要視されなくなり、嗅覚や触覚、味覚は動物に近いものとしておとしめられた。言葉や活字がこの世界の全構造を知るのに最高のメディアとなり、ますます視覚への特化と深化がおこった。
言葉や印刷文化、または視覚至上主義がもたらした世界観とか考え方のありよう、偏りとかはもっと深く追究したいと思うのだが、なかなかつかみ切れない。言葉や視覚の世界がほかの感覚器官の世界とどう違うのか知りたいと思うのだが、まだこれからの課題である。
ある感覚の特化や欠落は、世界の知覚にも影響をあたえる。われわれは世界をありのまま知覚し、物理的世界を写しとっていると思っているが、すでにしてわれわれは文化と社会のフィルター濾過をおこなった世界を見ているに過ぎないのである。母国語が世界観を規定するという「サピア=ウォーフの仮説」は有名だが、言葉だけではなく、感覚器官の活用や比重も文化によって規定されているのである。
感覚の世界というのはすでに文化規範の産物なのである。世界をありのまま見ているわけではない。われわれの知覚する世界というのは西欧化社会の視覚主義に染められた世界を見ているのであって、全感覚をフル活用した知覚世界を見ているわけではない。視覚主義になってから、われわれは聴覚世界や嗅覚世界、触覚世界の豊穣な地図や模様をどれほど失ったか思いもよらなくなっている。
人間というのは全感覚を最大限に活用してはじめて人間として生きられるのだろうか。あるいは感覚の偏りや特化をうけいれつつ、そこから最大限の果実を得るように生きたほうがいいのだろうか。
人間はいつだって全感覚を味わおうと努力してきた。印刷文化からはレコードやラジオがうみだされ、TVがうまれ、触感を味わうバーチャル・リアリティーもうみだされてきた。五感を全部味わおうとするのが人間の本性である。感覚の欠落は人間に埋めがたい飢餓をもたらすようである。排除されてきた感覚器官の豊穣な世界を探る必要があるようである。
知性=言葉の欠陥 01/4/8.
メディアの感覚欠落は知性の欠陥でもある。知性や言葉はひじょうに便利で卓越したメディアであるのはまちがいないが、五感のセンサー世界を排するし、言葉独特の偏狭で偏った、底知れぬ欠落をもたらす場合もあるのだろう。
言葉の欠陥をまとめてみよう。マクルーハンによると活字文化は画一性、規格性、同質性、反復性、連続性をもたらしたという。未開民族にとってこの世にはひとつとして同じものがないのだが、印刷された活字は同一のモノを大量につくれる。この驚異がこんにちの大量生産社会、または均質化・画一化された計ることのできる空間と時間の発想をうみだした。
これは近代科学の大元になった近代合理主義の考え方である。均質化、客観化された、測定可能な世界観というものがなければ、近代合理科学はうまれなかった。しかし世界は自己をはなれて客観的に存在するという発想はドグサ(臆見)にすぎないとフッサールはいっている。言葉は対象を捉えるためには、対象を分離=客観化しなければならないのである。
分離・分断は言葉が成り立つために欠かせない作業である。切り離し、切りとらないかぎり、言葉は言葉としてなりたたない。「頭」と「首」は線を引かなければ分けることができないし、「水」と「湯」は区切りをつけないと区別ができない。ほかのすべてもつながり、連関しているものにむりやりメスを入れ、切りとらないかぎり、言葉としては意味を成さない。これらはすべて切り離して存在できるかは疑問であるが。
物事や事象には無数の相・瞬間・側面があるのだが、言葉は単一の相を切り出す。世界には二度と同じもの・現象はないと考えるのが妥当であるのだが、同一性に固定する。活字ももしかして矛盾や変化の激しかった意見や考えを、固定した見解にしばりつけたかもしれない。一時的な現象もまた固定した「モノ」として表現されるのがしばしばである。
固定した見解は即時性や即座の参加の拒否をもたらした。行動や参加の融通がきかないのである。それは自己と対象の分離・客観化からはじまっているのだろう。それは存在と行為の分離でもある。
なによりも最大の欠陥は、言葉を対象そのものだと思ってしまうことである。言葉でイメージされた世界が世界「そのもの」に勘違いされてしまうのである。頭で描いたにすぎないものが世界そのものになってしまうのである。愚かなことだが、人間はこのカン違いからなかなか抜け出せないのである。
だからわれわれは怒りや悲しみからも自由になれない。頭で描いたり思い出したりしたものを現実だと思ってしまい、言葉からわきあがる感情の牢獄に囚われる。それがただの想像や虚構である――存在しない絵空事であるということに気づけないのである。
言葉=活字文化は視覚主義をももたらした。嗅覚や触覚、皮膚感覚などを侮蔑や感覚ヒエラルキーの劣位に追いやったのである。活字は視覚以外の諸感覚をいっさい必要としない。そのために豊かな五感の世界は失われ、五感センサーの多彩なる地図や情報は忘れさられることになった。
言葉は人間を世界や身体感覚から、分離し、分断し、切りとり、切り離すのである。断片やこまぎれとなった人間は、世界や身体の全面的な関わりから疎外され、抑圧され、分断されるということわけである。この決裂した人間のありさまは、言葉や活字文化、視覚主義によってうみだされたものである。深く胸に刻み、思い出す必要があるのだろう。
メディアVS現場と行動 01/4/10.
五感の全情報から、言葉や視覚、聴覚だけを切りとってくるのがメディアの仕事である。現場にはもっと多くの情報や感覚があり、においや騒音、風や温度感覚などさまざまな感覚が渾然一体となってそこの状況をかたちづくっている。そこからほんのわずかな切りとれるだけの情報を切りとってくるのがメディアである。
そして運送可能な情報や知識の価値ばかりが高まる。輸送できない、切りとれない感覚の価値――たとえば、においや体感、触感、皮膚感覚などは忘れられてゆく。なくても困らないものかもしれないが、それらの感覚は人に多くの情報や好悪の判断をつけくわえていったはずであり、人に快楽や喜びの感情、さらには生きている実感すら与えていたものかもしれない。
たしかにメディアはすばらしい、とてもよいものである。空間と時間、選択と編集の壁を飛び越える卓越したテクノロジーである。言葉がなければ一日たりとも社会生活を過ごせないだろうし、TVやCDがなければ豊かで楽しい日々を暮らせないだろう。
しかしメディアはある感覚機能しか輸送できないという点で、大いなる欠点をもっている。これは忘れてはならないだろう。目と耳しか輸送できないメディアはたしかに五感をもつ人間には欠陥商品である。人は五感全体で対象を知り、味わいたいのである。それこそが生きている実感と楽しみというものであり、その欠落をもたらすメディアの不完全さには警戒を怠るべきではない。
われわれは輸送可能なメディア情報に頼るばかりに現場感覚や体感、五感の大切や意味を忘れてしまったのである。生きることの楽しみや喜びはそれらの五感や身体に多く根づいているものかもしれないのである。
メディアはまた人々から行動することや反応すること、応えることなどの価値と実践力をも奪ってしまった。現場や対面において人々は即座の行動や参加を必要としていたわけだが、メディアはそういう行動をいっさい削ぎ落としてしまい、われわれを姿の見えない観客や聴衆、傍観者にしてしまった。われわれはのぞき部屋から世界の出来事をずっと覗きつづける無力で透明な存在になってしまった。
情報や知識はメディアから輸送されるばかりになり、われわれは現場にいることがなくなり、行動や参加の体験や経験はますます遠のいてしまった。われわれはメディアによって五感を失ったのみではなく、まずは行動を失ってしまったのかもしれない。
メディアと行動の分離は、言葉の性質ゆえかもしれない。言葉は主観と客観的世界を分け、存在と行為者を分けてしまう。出来事や物事から、行為を切り分けてしまうのである。
客観的世界を極めようとする近代科学観も主観と行為の分離によって成り立っている。そもそも思考することや観察することは、行動をやめることである。言葉の発展メディアである本やTV、レコードなどは、行動を滅却する大量生産・大量販売ともいえなくもない。
メディアは五感の人間にとってずっと欠陥商品でありつづけてきた。目や耳の機能に特化したその欠陥メディアのためにわれわれの意識形態や社会形態はどんなに歪まされ、欠陥的な生き方を余儀なくされていたかわからない。それは言葉の性質や機能自体から始まっている。深く反省する必要があるようである。
五感と身体感覚の価値 01/4/13.
メディアによって伝達できない五感にそんなに価値があるのか、いまの私にはよくわからない。嗅覚や触覚などの五感はとりもどされるべきものなのだろうか。それともこれまでのメディアによって仕込まれた視覚や聴覚中心でもべつに問題はなく、使われない器官はべつだんそのままでよいものなんだろうか。
トータルな五感で世界を味わうことはそんなに重要なことなのだろうか。まあ、いまのところは人はからだ全体で世界を感じとりたいのであり、技術や芸術などがそれをめざしてきた歴史があるとしかいえない。
メディアはとりわけ視覚を特化させてきた。視覚によって世界を知り、世界の構造を見極めようとしてきた。視覚中心の社会では視覚ばかりを用い、視覚のみで世界を知ろうとする傾向が強く、ほかの感覚世界を無視する。視覚の断片感覚だけが鋭敏になった人間ははたして人間の全能力や可能性を活用としているといえるだろうか。
ほかの感覚を抑圧することの意味はどのようなものなんだろう。たとえば匂いを忘れた人間は匂いによる世界のありようとか状態、判別や識別の能力や世界を忘れ去ったことだろう。匂いによって人は他人の健康状態や精神状態、あるいは病気すらわかったということだし、階層や外集団との区別すらそれで知り得ていた。
触覚は人との安心や一体感をもたらしていたし、心を癒す役割ももっていた。体温で人の状態がわかったかもしれないし、皮膚の質は知見をひとつ増やしていたかもしれない。触感や味覚というのは世界を知るための最初の探索であったし、いちばん深い安心や不快を鋭く分別するものであっただろう。
皮膚やからだの感覚というのは外の空気や天候、温度などをかくべつに感知するセンサーであり、気もちよい風や空気、晴れ渡った空気の爽やかさなどを直に感じとるものであり、同時に閉め切った部屋の空気のよどみ具合や梅雨のじめじめした湿度を感知する、いちばん基本的で原初的な感覚であり、自然の中で生きる人間たちはこの感覚から多くの情報や知見を得てきた。
そういう世界のありようを多く知り得て、かつ快不快の土壌であった身体感覚というのは、視覚特化をみちびいたメディア装置により、その役割や用途を抑圧させられてきた。視覚主義においては意味や価値が貶められ、その感覚によるコスモロジーは描かれなくなった。
メディアの情報というのは伝送できるものである。世界に一つしかないものではないし、唯一無二のものでもない。コピーできるし、同じモノをいくつでもつくれるし、とりかえがきき、大量生産でき、時間と空間を超えて伝達できるものである。
しかし伝達できない、輸送できない感覚や体感というものが、人間の生きている実感をより深く感じさせるものではないだろうか。感覚というのは唯一無二のものであって、言葉では伝達可能であっても、その感覚自体を他人に感じさせることはできないし、自分にしか感じることができないものである。
メディアは伝達できるものの情報や価値を高めた。共通の感覚や体験が重要なものになった。唯一無二のものより、数が多く、どこにでもあり、とりかえがきき、多くの人が共有するものに価値が高まった。つまり自分しか体験できない感覚の価値は弱まり、共同的な感覚共有の価値が高まった。
これは個々人の感覚より、共有感覚のほうが意味があり、価値があるということである。自分独自の感覚より、共通した、均一化された共有感覚のほうが重要であるということである。
このことによって個人の生は転落した。個々人の唯一性や自分しか感じることのできる身体感覚は重要でなくなった。つまり人間の生の根源である身体感覚や個別性といったものが重要視されなくなったわけである。メディアは共有感覚を高めるがゆえに、個々人の唯一性である身体感覚の抑圧や鋳型にはめこむこと、パターン化をもたらしたのだろう。
メディアは言葉も含めて、人間をどこにもであり、共有でき、複製でき、とりかえのきくものに仕上げる装置なのだろう。唯一性は言語からはじまって暴力的に駆逐され、唯一独自な生の土壌たる身体感覚は弱められ、薄められ、感じられなくさせられてしまうのだろう。
五感や身体感覚というのは、生の土壌であり、生存の実感を深めるものである。それらの鋭敏な感覚を用いないで、どうやって生の実感を感じられるというのだろうか。
唯一無二の存在である自分 01/4/14.
自分にとって自分はとりかえのきかない、かけがえのない存在である。自分がいなければ世界は消滅してしまう。生の実感や根拠のもとになるものである。自分は唯一無二の存在なのである。
しかし人は他者や社会のなかでも唯一無二の存在になろうとする。人々から認められたり、優越しようとしたり、偉く見られようとする。社会のなかにおいても、とりかえのきかない、かけがえのない存在になろうとして躍起になる。
そもそも人は生の基盤を与える唯一無二の存在なのであるが。なんでこんなことになってしまったのだろうか。社会に認められなくとも、自分は自分にとって生の実感や世界の現実を感じさせる唯一の基盤であり、存在なのだが。
どこから生は転落したのだろう。自分がどこにでもいる、大勢のなかの同じような人間のひとりに過ぎないと知るのは概念上のことである。頭のなかで知ってゆくのであって、身体感覚で知るのではない。言葉や自我が、自己の矮小化や卑小化をもたらしたのだろう。
メディアはもっと自己の矮小化を押しすすめる。大量伝達による画一化、均質化、規格化の波をかぶって、ますます自己はとりかえのきく、どこにもでもいる、似たり寄ったりの群集のひとりにすぎない卑小な存在に貶められてしまう。頭のなかの自己像はますます弱く、卑小なものになってゆく。
言葉が自己の客観化をおこなう。そこから自己の転落は起こっているのだろう。言葉は自己のなかの伝達できるもの、とりかえのきくもの、人と共通したものをとりだし、ますます自己の唯一性は少ないものになってしまう。
感覚の重心も身体から目や耳と移り変っていって、自己の唯一性は失われ、客観性や概念化による理解が進んでゆく。生の基盤や実感を与える身体、あるいは身体に関わる皮膚や筋肉、触覚、味覚、嗅覚などの感覚は重心が弱められてゆく。つまり自己の唯一無二性からかけ離れてゆくわけだ。
身体から感覚比率が目や耳、頭に移り変わるにしたがって、概念的・客観的理解がすすんでゆき、ますます自己の唯一性は失われ、自己はとりかえのきく、どこにでもいる画一大衆のひとりになってゆくのである。目や耳を使い、身体感覚を用いない言葉、活字、映像がますますそれを押しすすめてゆく。
そしてわれわれは自己の矮小さや卑小さ、画一・均質さから逃れようとして、比較や優越のチキン・レースをおこなうというわけである。唯一無二性を証明してくれるのは、他人の評価や認知、称賛だけだと思い込むようになってしまう。自分を群集のひとりとして見なした他者の心に自己の存在を植えつけることにより自己の唯一性を手に入れようとするのである。他者にとって無意味で無価値である自己の存在はそれによって補われるのである。
しかしそんなことをしなくても、自分は自分にとってかけがえのない、とりかえのきかない、生の実感や基盤を与える唯一の存在である。自分がいなければ世界は消滅してしまう。他者も存在しなくなってしまう。宇宙すら終わってしまう。
自分は生まれたときから、自分にとって唯一無二の存在なのである。努力も比較も優越もクソも必要ない。そもそもはじめからそういう存在なのであるから。なんて愚かなことなんだろうと思う。客観的な概念だけが否をいい、不安に火を点ける。この世界の実感や根拠、ありようを感じとるのは自分の感覚しかなく、自分の身体でしかない。安心すればいい。これだけでじゅうぶん唯一無二の存在であり、これ以上かけがえのない実感はないのである。
感覚のヒエラルキー 01/4/17.
人間は外界を支配・統御しようとしてきたが、自らの身体においてもその手綱をかけなかったわけがない。世界と接し、世界の状況を知る各種の感覚も、社会や文化のヒエラルキーづけをほどこされて、支配と統御を受けてきた。
ある感覚はもちあげられ、ある感覚は貶められるといったヒエラルキーである。視覚は活字・印刷文化においてますます重んじられ、嗅覚や触覚はどんどん貶められた。
いまでは鼻でにおいを嗅ぐ行為は動物的なものと蔑まれているし、触覚は性的なものとして遠ざけられている。しかしこれはどこの文化・時代圏においても通用する感覚秩序ではなく、西洋近代にあらわれたひとつの特殊な文化規範にほかならないようである。そしてあるひとつの感覚で捉えられる世界観はその感覚に限定されるというわけである。
あきらかに「文明/動物」の単純な対比の網目が身体感覚にかけられているだけである。また「理性/本能」といった対比ともいえるだろう。これはどういうことかというと、文明化、理性的であろうとしてきた近代人の価値観のヒエラルキーが五感のヒエラルキーと活用度合いをも決めてきたということである。
目や耳は文明や理性の旗印であり、嗅覚や触覚は動物や性欲の権化というわけである。したがってもっと目や耳をもちいて文明人になりなさい、鼻や手、皮膚は動物的な感覚であるから遠ざけなさいというメッセージを発してきたわけである。
多田道太郎によると、目や耳は明晰化・分節化の器官である。これらはスペクトルや音符によって分節化される。これに対してにおいや香りは多くが比喩で表現されるように、分節化されにくい。したがって「低級」な感覚であるということだ。明晰化・分節化をめざしてきた西洋近代はそれの劣る感覚を隠蔽してきたわけだ。(『しぐさの日本文化』角川文庫)
触覚が貶められるさいには、心の触れあいを「愛情」に、愛情を「性」に局所化してきたと多田道太郎はいっている。つまり触ることは「エッチでいやらしい」ことになり、心=身体の触れあいは性器に一本化されたというわけである。皮膚や身体の感覚はこうして抑圧されていった。SMやラバーマニア、においフェチというのは、性的色づけのむこうにある五感の感触や心の触れあいを無意識に求めているといえるかもしれない。
これで思い出すのが、フロイトのあの奇怪な幼児の性欲理論である。幼児には口唇期、肛門期、男根期といったそれぞれの快楽の段階があるそうである。これはたんに自文化の感覚ヒエラルキーの色づけをかぶせただけであって、ヨーロッパの感覚抑圧の機構をなぞっただけかもしれないといえなくもない。感覚の局所化というのははたして人間の順調な成長なのか、退化や不具化ではないのか、疑問である。
われわれの身体感覚や五感というのはあまりにも分化や分断化、局所化がおこなわれているといえる。そのような局在化がはたしてよいことなのか、全感覚をすべて用いるということがどのようなものか、あらためて考えてみるべきだろう。あるひとつの感覚器官による世界はとうぜんその感覚の限界内のものしか捉えられないし、感覚の分節化により縮小された感覚は全体の連関や活用を疎外してしまうものである。
これは社会において分業化がすすみ、断片化・専門化された人間は偏り、疎外され、充足した生を生きているとは感じられないことと同じである。文化の拘束着といったものを脱ぎ捨てるためには、見えないそれを知ることが必要なようである。
触わることの禁止 01/4/18.
深い悲しみや不安に襲われたときに私たちは言葉をかけるより、そっと抱きしめる。ひさしぶりに再会したときや、ものすごくうれしい出来事があったときには抱きしめ合う。親密にありたいと思う相手には触れたいと思うものだし、愛する相手にはとうぜんからだを触れたいと思う。
触れること、肌と肌を合せること、からだを合せること、といった一連の接触は言葉より多くの気持ちや思いが込められている。皮膚や触覚、身体の感覚というのは言葉より雄弁に私たちになにかを語りかける。
しかしわれわれの社会においては触れることは多くのタブーに囲まれている。見知らぬ人を触わるのはとうぜんにご法度であるし、女性なら性犯罪になるし、男同士で手をつなぎ合っていたりしたら、あらぬ関係を疑われかねない。
触わることというのは高度に社会規範や秩序、所有などの関係の網の目がかけられている。そして男同士でキスする国があったり、または男同士で手をつなぎ合うことが普通の国があったり、また女同士で手をつなぎあってもべつにおかしくはない国もある。つまり触わるという行為は、ある文化によっては許されたり、許されなかったりする文化規範なのである。
日本はほかの文化圏にくらべてかなり非接触の国であるらしいが、メディアの発達とも関わりがあるのだろうか。活字を文化の要にする国はとうぜん目の感覚比重を増やし、触覚や嗅覚などのあいまいなものは貶めてゆくことだろう。いっせいに視覚人間(つまり文明国)にするためには触覚や嗅覚の快楽や愉楽は狭め、禁止し、触れられないようにしたほうが都合がよいだろう。
どの感覚に比重をおくかは環境や文化に多く規定されるようである。視覚で知覚されるものに価値をおく文化は視覚に比重をおき、聴覚中心社会では聴覚、触覚には触覚といったようにその感覚に焦点をおく訓練や訓化がしぜんにおこなわれることだろう。こうしてあるひとつの感覚に焦点が当てられつづけ、それが研ぎ澄まされ、習い性となる。断片的になった人間が幸せかどうかはわからない。
視覚中心のこの社会では触覚や皮膚感覚はずいぶん貶められ、性的嫌悪のレッテルを貼りつけられてきた。そうして視覚比率の高い人間や社会はできあがってゆくのである。
肌の触れ合いや触覚というのは乳児期にその満足が得られなかったら、のちに暴力的な傾向が強くなると最近ではいわれている。接触や触覚というのはそれほどまでに人に深い安心ややすらぎ、愛情をもたらすもののようである。
その接触は性的レッテルのもと多くの範囲を禁止されている。また性感帯というのも全身の皮膚から性器だけに感覚の局所化がおこなわれてきた。狭めたり、局所化したり、また時間限定的なものにされた身体感覚の快楽というのはどうしてこう不運な目に会ってきたのだろう。おかげでわれわれの身体は多くの能力や快楽、活用度合といったものを失ってきたのである。
視覚ばかりに感覚比重をおく人間はとうぜん感覚の回線ができあがる。触覚や嗅覚の回線はますます使われなくなり、廃れてゆく一方である。断片的な存在になってゆく人間はやはり足や腕を失ったみたいに不自由で不幸なのかもしれない。全身で全身の感覚をもって生きることこそ、十分な生とはいえないだろうか。
【ご注意】最近モニターの調子が悪いです。まっ暗になります。とつぜん更新がとどこおったり、メールの返信をお届けできなくなったりする場合があるかもしれません。その際はモニターが故障した旨をご了解いただきたい。
復旧はなるべく早くしたいと思いますが、金欠と明日も危ぶまれる身の上のゆえにどうなることかわかりません。まことに申し訳ない。ガンバリマス。
(これは故障にそなえての一応のご報告です。) 01/4/7.
メールはこちらに。  ues@leo.interq.or.jp ues@leo.interq.or.jp
前の断想集「童話の解釈と感覚の復権」
2001年初夏の書評集「感覚の文化論」
2001年春の書評集「物語を読む――童話分析」
|TOP|断想集|書評集|プロフィール|リンク|
|