つぶやき断想集
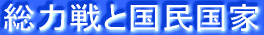
美人と市場原理 00/9/3.
美人も市場経済に従うということを井上章一の『美人論』(朝日文庫)は思い知らせてくれた。
やはり美人は結婚市場においてよく売れる。明治・大正期において美人は学業のとちゅうにおいても嫁にもらわれてゆき、さいごまで学校を卒業することは少なかった。
明治になって華族と平民の結婚が認められるようになって、女学校に授業参観と称して親たちが露骨な嫁選びにやってきていたそうだ。女学校というのはまるで商品市場のようなものだったワケだ。
明治の立身出世男や成金男たちは、伝統や歴史がないだけにあって美人という「見せびらかし」のシンボルを必要とした。美人という価値観は、明治の市場経済においてその値打ちを立身出世的にのばしたわけである。
したがって卒業まで学校にのこる女性は売れ残りということになり、倫理的な要請からも、また美人は卒業までのこらないということで、美人はバカだという流説がささやかれることになる。美人は結婚市場の勝ち組であったが、学業においてはそのおかげでおろそかになった。
時は流れていまはだれもが美人になれるという時代である。美人は特権的なものではなく、磨いたり、装ったりして、だれもが「平等」に「民主主義的」に手に入れられるものになった。
こういう言説を必要としたのは、化粧品や美容品、ファッションなどの産業が大衆市場の拡大をもくろんだことによるものである。だれもが美しくなれると思わなければ、それらの産業に女たちが群がることはないからだ。ここからも平等とか民主主義というのは市場マーケットの要請と必要によるものだということがわかる。
さて結婚市場は美人がかなり有利であったわけだが、美人をバカだとか罪悪だとかいって慰められてきた市場の売れ残り組たちは、知能や技能によって経済的自立の道の先鞭をつけ、切り開いてきた。
女たちは結婚市場において美人のひとり勝ち状態から、平等と民主化、あるいは社会主義化という「社会的進歩?」をへてたわけだが、どちらかといえば、男に選ばれ、買われるよりか、自分で経済的自立をはたしたほうが楽しめるという方向に進んできつつある。かつての負け組は勝利を得つつある。
これから女たちは恋愛・結婚市場というくびきから逃れる方向に進んでゆくのだろうか。もし女性が美貌や性といった商品を売らないようになるとしたら、男と女の関係は経済の関係から抜け出すのだろうか。そうなると美とか性といったものはどのような価値や意味づけの変貌をこうむることになるのだろうか。
終身愛と国民国家と大衆市場 00/9/4.
恋愛においてひとりの異性を生涯愛しつづけることがこんにちの理想である。崩れかけているかもしれないが、意外と根強い崇拝をもちつづけている。
これは企業と労働者のあいだにおいても終身雇用という関係としてとりかわされてきた暗黙の約束である。
また国家との関係においても、労働と税金の報いとして老齢年金という生涯保障が約束されてきた。
このような生涯をまるごと保障するという関係は、国家同士の争いが盛んになってきた近代という時代の要請によるものである。
つまり国家同士の争いにおいては軍事力、経済力、知識力とともに優れていなければ勝つことができない。したがって国民をそれらの武・富・知のジャンルにおいて総動員する必要がある。
国民をそれらの用途として役立てるためにはなんらかの見返りが必要になる。ということで終身保障というまことに親切であたたかい約束がもちだされてきたのだろう。国民は喜んで国家のために働くだろう。
前後は逆になるかもしれないが、経済が発展するためには階層社会というものは撤廃しなければならない。マーケットがそれぞれ士農工商という身分にわかれていたら、すぐに限界はくる。
ということで階層は撤廃され、平等が標榜され、マーケットはいっきょに大衆規模にふくれあがるが、なおいっそうのマーケットへの貢献と国家への献身を得るためには人権や民主主義のような見返りを与えることが必要になる。
平等で大規模なマーケットができたのはいいが、こんどは市場競争によってふたたび貧富の階層をうみだすことになってしまう。これではマーケットは縮小し、また国家への経済的寄与は少ないものになってしまうし、国民の献身をうみだせない。
そして終身保障という社会主義的理想がもちだされてくるわけだ。このことによって国民はよりいっそう国家のために働き、あるいは企業のために働き、平等のために消費をし、マーケットに貢献するというわけである。
しかし終身保障は堕落と衰退をもたらす。パンとサーカスが与えられれば、人々は努力することも、向上することもなくなるからだ。人々の重みで国家はつぶれ、経済はたちゆかなくなる。
したがって国家も企業も人々を放り出すようになった。人々を結集する目的や用途がなくなってきたということもあるだろう。あるいは労働者も国民も女性も、終身のくびきから逃げ出すようになった。
国民国家と国民総動員の時代は終わったということだ。国家や企業は終身を保障するということがなくなり、男と女は終身愛という約束を必要としなくなる。それぞれはご勝手に、生涯の面倒は見ません知りませんという具合だ。
政治や経済、愛などの関係はそれぞれ連動している。まったく無関係のべつべつの事柄ではないということだ。
いつの間にか年をとるだけ 00/9/6.
私は今年で33才になるのだけど、いつの間にかこんな年になっていたという感じがする。結婚もせず、家庭ももたず、ただ、たんたんと日常を送っていたら、いつの間にか年をとっていたという感慨だけがのこっている。
人生というのはこんなものなのだろうか。いつの間にか年をとっていて、そういう感慨をもちつつ、40才、50才となってゆくのだろうか。
べつに子どものときになにかになりたいだとか、こんなふうな人生を送りたいだのとか、こういう家庭を築きたいだの、そういった夢や希望はほとんど抱かなかった。そういうものをもたない人間は、ただ年をとっていただけの人生を送ることになるのだろうか。
でもなにか夢や希望をつかんだとしても、たぶん人生の感じ方というのはそう異ならないと思う。なにかをつかんだとしても砂のようにこぼれ落ちてゆき、つかまなくても砂のように流れてゆくものなんだと思う。
なにかをつかめると思うのは幻想なんだと思う。家庭をもったとしても、社会的に業績をあげたとしても、それは砂をかむような思いがするものだろう。それらをもっていない者のみが、もつことの幸福を夢想できるのだろう。
べつに私は感傷に流れるつもりはない。でもたまにはそういう気分や感傷にひたりたいときもある。
こういう感傷は人生に害をもたらすものであり、人生に苦悩と苦痛をつけたすだけであるという心理的な知恵をつけているので、これいじょう感傷を拡大させるつもりはないけど、たまには過ぎてゆくだけの人生というものを反省してみたくなる。
感傷と苦悩は、夢や希望、欲望といったものに安易に結びつくのだろうけど、これは戒めるべきだろう。
なぜなら感傷や苦悩といった感情の反対側に希望や夢といった救いがあるのではなく、それらは同じコインの表裏であるからだ。裏がなければ、表がないといったひきはなせない関係である。
感傷や苦悩は反対側の希望につなげるのではなく、それ自体を消すべきなのである。消してしまえば、「砂上の楼閣」としての夢や希望をつくりださずにすむ。
「思い出」に生きる人 00/9/9.
思い出というのはすばらしいものかもしれない。うれしかったこと、楽しかったこと、よい出来事というのは何度も何度も思い出したいものかもしれない。
しかしいまの私は思い出を思い返すことはほとんどない。よい思い出とかすばらしい過去だとかもほとんど思い起こすことはない。
過去を反芻すること自体、ほとんど捨ててしまったからだ。なぜ捨ててしまったかというと、過去は幻であり、それにしがみつくことは苦しみを足すだけであり、捨てるべきだというリチャード・カールソンのセラピーとかカーネギーとかウェイン・ダイアー、ピールなどの自己啓発、あるいは仏教を読んだ影響からである。
思い出を思い描くということは過去を反芻する習慣をかたちづくってしまうものである。そういう習慣を堅固にしてしまうと、かならず過去のいやなこと、つらいこと、傷つけることをひんぱんにくり返す習慣をもかたちづくることになる。
ましてや思い出というのはすべて幻である。終わってしまい、どこにもないものである。そんな存在しないものをいつも追いつづけるということは、失って二度ととりもどせないものを追い求める哀れな憔悴しきった人のようなものである。
そういう過去や思い出を捨てると、苦痛や苦悩の感情も大半はとりのぞかれる。私は以前はよく過去を反芻するタチだったが、いまはもうすっかりそういう習慣は愚かなことだとしてやめてしまった。
甘くて楽しい思い出を捨ててしまって、幸福になったのか、ふしあわせなのかはよくわからない。ただ過去のつらい思い出のために悲しんだり、苦しんだりして、ムダで苦痛の多い時間を過ごすことはほとんどなくなった。
そういうふうに自分を変えてみると、見えてくるのが恐ろしいほど過去の思い出にしがみつき、思い出に生きようとする人たちやその試みが、この世の中にはくりひろげられているという事実である。
ドラマや映画では何日も前のことや何年も前のことをまるで今日おこったかのように蒸し返したり、過去とともに生きている人たちがわんさかと現われてくるし、ビデオやカメラ、車のテレビ・コマーシャルなどでは思い出を蓄積するのがすばらしい生き方であるとメッセージしつづけている。
写真やビデオは思い出をいつまでも残しておくことができる。楽しい、なつかしい思い出がたくさんあることはいいことかもしれない。しかし過去は二度と体験することができないし、思い出はもうすでに存在しない幻であり、そして逆に思い出のために旅行したり、遊びに出かけるという逆転した行為がおこなわれるようになる。
これは違うと思う。思い出のために今日を生きるというのはまるで人生の終わりの老人のような生き方だ。思い出に生きる人生というのは、すでに行動や喜びが実体験として得られないから、頭のなかの想起によって充足する生き方なのであって、すでにひからびた生き方である。
喜びや楽しみなどの感情はいまの一瞬しか感じることができない。過ぎてしまえば、二度と同じ感情、同じ体験を得ることができない。思い出はたんに頭のなかの思い出にしか過ぎない。幻である。
すべては一瞬にして終わってしまい、二度と体験も感じることもできないものである。だからいま一瞬の出来事や感情をもっと大切にしようという気持ちになる。過去のいやなことやつまらないことで悩んでいる暇なんかない。どんな一瞬も二度と同じ瞬間をくり返すことはないし、二度と体験できないものである。思い出を捨てよ。
「平凡を軽蔑する教育」 00/9/10.
「偉い人になれ」という教育は「平凡を軽蔑する教育」である。こんな教育をうけた平凡にならざるを得ない大半の人は不幸なことである。平凡な自分を呪うような人生がはたして幸福になれるだろうか。
私も子どものころ、歴史のなかに無数に消えていった無名の人生といったものに怖れをなしていた。歴史に残った有名な人に比べて、この人たちの人生はいったいなんだったんだろうと思っていた。
そういうふうに育てられた人間が、無数の平凡な人の群れの中に埋まってゆく人生が耐えがたきものになるのは想像に難くないというものだ。
歴史で将軍や皇帝だけの生涯が語られるということはふつうの庶民を無に等しい存在と見なすことを教え、成績の序列は平凡を忌み嫌う心をつくりだすのである。
そもそもこんにちの教育の基礎をつくった明治政府は「革命」政府であって、世の中を変えた人だけに価値を見出すものだ。革命家と優秀な人だけを称賛する教育がおこなわれるのはとうぜんのことだ。だから学校の歴史だって有名人の称賛である。
こうしてわれわれは平凡を軽蔑する人間として洗脳され、平凡から脱け出そうとする教育序列によって平凡さを恐れ、上昇を願うエネルギーにたえず駆動づけられるというわけだ。
ニュースもテレビも書物も、有名人と優秀なものばかりをとりあげられる。平凡な者はほとんどかえりみられないか、無視されるか、軽蔑されるだけである。世の中の大半の人はふつうの平凡な人ばかりで構成されているというのが現実であるのだが、メディアや教育においては平凡人はほぼ抹殺されている。
この世はこぞってエライ人をほめたたえる社会である。この価値観を基盤にメディアや社会は階層づけられ、人々の常識となり、人々の心の色メガネとなっている。
そしてこの価値観、ヒエラルヒーによってわれわれの競争社会や優劣競争は永遠にとまることがないというわけだ。競争はエライ人をほめたてるメディアと教育によって日々再生産され、増幅されているわけである。
これを逆にひっくりかえすと、「賢者を尊重する者がいなければ、人は競争しないだろう」(老子)ということである。
そういう試みをしたのが民俗学者の柳田国男や宮本常一である。かれらは日本の名もないふつうの人たちの歴史や生涯を追った。
われわれはこういう名もなき民衆たちの歴史や生涯を学ぶべきなのである。それでこそ、名もない一般民衆にたいする誇りや尊敬の念がうまれるというものである。しいては、平凡に生きざるをえないわれわれ自身への讃歌と応援歌にもなる。
歴史は政治屋のドンパチをとりあげるのではなく、名もなき一般民衆の苦しんだり、つらい思いをしながらも懸命に生きてきたかれらのすがたこそをとりあげるべきなのである。
そういう本としてふさわしいのが宮本常一の『生業の歴史』(未来社)である。名もなき民衆たちのたくましくも懸命に生きてきたすがたがいきいきと描かれている。
ついでに歴史に名を残すことが永遠の生を得るような錯覚をいだいている人は、マルクス・アウレーリウスの『自省録』(岩波文庫)が解毒剤となるだろう。
「無職」が尊敬されていた時代? 00/9/14.
山田霊林という禅仏教者によると、明治の終わりころには「無職」であることが尊敬されていたそうだ。職業は軽蔑されていたそうである。
初耳というか、現代の一般常識ではまず耳を疑う話である。無職は憐れみか、白い目で見られるかのどちらかだ。(江戸時代には武士が支配層であったから職業は軽蔑されていた、と歴史で習ったことがあるが)
なぜこんなに変わってしまったのだろう。無職が尊敬されていた時代の考え方とか背景とかなにか資料が手に入ればいいのだが、なかなかそういったことを記した資料なんか目につかない。
推測するにたぶん明治という時代は貧富の格差がある程度肯定されていた時代だったのだと思う。現在のように平等政策ではなく、金持ちはとことん金持ちになれた時代だったとどこかで読んだふうな気がする。
したがって働かなくとも食える金持ちが続出したのだろう。そういう金持ちの無職はとうぜん現代のカネのない無職と違って、憧れの的となったことだろう。
しかし時代は変わり、累進課税のように金持ちから儲けた分だけ税金をとるような平等政策がはじまると、とてつもない金持ちは減り、金持ちになるモチベーションも削りとられてしまったのだろう。
「国民総動員」のような戦時下の意識形態も、「働かざる者食うべからず」といって存続しつづけているから、無職は軽蔑か、憐れみの目で見られるようになったのだろう。
職業が軽蔑から尊敬へ、無職が尊敬から軽蔑へと時代は変わってきたということである。現代のわれわれはそんなことをほとんど知らないし、たぶん職業の軽蔑視を見たくないから、ことさらいまと違った価値観があったことを表に出そうとしないのだろう。
私としては時代背景や考え方は異なるようになるかもしれないが、ふたたび無職が尊敬される時代になってほしいものだ。人間の生き方として、人生として、現在のように生涯を職業のみに拘束される人生はあまりにも卑小で、矮小だと思う。井戸の中の人生みたいだ。
人生として、人間の栄誉ある生き方として、無職が高揚されてほしいものだ。生活とかカネのことを現実的に考えれば、そんな非現実的なことなんかとても言っていられないかもしれないが、人生として、人間として考えるのなら、職業のみに拘束されない人生というものはとてつもなくすばらしく、可能性のあるものに見えるのだが、どう思われるだろうか。
「総力戦体制」は終わっていない 00/9/15.
戦争はいまもまったく終わっていない。ずっとつづいている。この社会は近代の総力戦によってかたちづくられたものであり、いまもその体制を根強く維持しつづけている。この社会はいまもなお「戦時体制」なのである。
われわれは「戦争は悪いものだ」「二度としてはならない」といった教育をうけて、戦争にたいする深く、強い嫌悪感と憎悪をもっている。
しかしこの社会は表面上戦争中ではない生産と消費のすがたをとっているが、それらは戦争のアナロジーにすぎなく、かつ戦争の別形態にしかすぎない。生産は戦争とコインの表裏である。
われわれは戦争の下準備を着々と進めているにすぎない。または仮想的な戦争をくりひろげている真っ最中である。
そしてわれわれの人生は戦争に捧げられ、戦争に従事させられているというわけである。平和時においては人殺しではなく、生産というかたちをとっている違いはあるが。われわれの人生は戦争の道具として捧げられているのである。
バタイユや栗本慎一郎によると、戦争中は平和時の禁止や抑圧、退屈さといったものがいっせいにとりはらわれるわけだから、人類はその快楽のために平和時に生産や労働の「禁欲」に身をひたしているというわけだ。快楽は禁欲すればするほど大きくなるものである。
戦争の「快楽」なんてわれわれには信じがたい話だ。戦争のイメージには徹底的に「悪」や「殺人」の最高悪のラベルがほうりこまれているからだ。
だがカイヨワの『聖なるものの社会学』(ちくま学芸文庫)を読んではじめて実感したのだが、戦争には平和時にはない、快楽や崇高なもの、聖なるものが味わえる瞬間があるそうだ。この本を読んで、戦争はほんとうに宗教的な法悦だと感じられた。
戦争というのは「祭り」なのである。日常において禁止されていたもの、日常においてのわずらわしさ、こまごまとした日常のつまらないささいこと、生活の苦労や心配、退屈、そういったものがいっぺんに吹き消され、禁止がいっさいとりはらわれるのである。強烈な熱狂や陶酔を誘うというものだ。
もしこの社会がそのようなシステムで構築されているとするのなら、こういうあり方は早急に見直さなければならない。戦争の魅力や陶酔にひきよせられないようなしくみを早急につくりださなければならない。さもないと禁欲者は戦争の快楽へと無意識になだれ打つに違いないのだ。
社会の「総力戦体制」というシステムを日常のレベルから打ち崩してゆくこと。総力戦体制はわれわれの日常の、たとえば労働や企業、家族のあり方、日々の過ごし方、といったあらゆることに浸透し、制度づけているものだと考えられる。こういう基底的で日常的なことから再検査してゆかないことにはおそらく人類は戦争の法悦へとまた流れ込むことだろう。
「総力戦」と「国民国家」について考える 00/9/16.
現在も総力戦はつづいている。経済や生産というかたちをとっているが、これは国家間の戦争にほかならない。そしてわれわれの人生や労働、生き方といったものも、かなりの比重において総力戦に捧げられていると考えられる。
終戦の時点によって「総力戦」は終わったのではない。経済としていまなお継続していることは、現在の経済システムの起源は「1940年代体制」であると学者の間でいわれているように、コンセンサスを得ている。
私は自分の人生が労働や企業や国家に捧げられるような生き方をしたくない。そういう観点からも、総力戦と国民国家というものを問うことは、ひじょうに重要なことだと思う。
むかしの戦争は武士や貴族などの専門家集団のみの闘いだった。関ヶ原の合戦などに百姓は弁当をひろげて観戦していたというくらいだから、戦争は一般の民衆にとってカヤの外の話だった。
それが近代の総力戦の時代になって、人々は国家のために命を捧げ、国家のために人々を大量に殺戮するようになった。なにが決定的に違うようになったのか。民衆は「国民」になったのである。国家と命運をともにするようになったのである。
人々が国家に命を捧げるようになったのは、民主主義や人権、社会保障、経済政策を国家から与えられるようになったからだ。国家からたくさんの捧げものをもらい、その見返りとして人々は国家に命や人生、労働を捧げるようになったのである。
フランス革命やデモクラシー、人権の獲得などは人々を「国民」としてひきあげ、総力戦に駆り立てるためにぜひとも必要な契機だったのである。こう考えると人権の獲得は人類の輝かしい進歩というよりか、国家間戦争の洗脳と道具化する機会にすぎなかったということになる。
日本人はさきの戦争において、戦争を放棄したはずである。しかし総力戦や国民国家の心性は根強く、ときには経済的な最高位を狙う位置までのぼりつめるほど、深く根底まで染み込んでいるのは、意外と人々の意識にはのぼらない。
戦争を放棄するということは、総力戦のシステムまでも放棄するということであり、国民総動員の経済まで放棄することではないのか。われわれ個々人の心性において、なんらかのジャンルで世界のトップをめざすこと、そういった心性をまったく解体することが、ほんとうの意味での戦争放棄の完成にはならないだろうか。
われわれの生活のささいなこと、労働や生産、消費、家庭、そういったすみずみにまで総力戦のシステムや価値観、序列順位は浸透しているはずである。こういった社会的価値観を根底まで洗い直さないことには、おそらく総力戦――戦争の機会はこんごずっとつづくことだろうし、われわれは人生を、生涯を、これまでどおり国家に捧げ尽くさなければならないだろう。
日本人はその心性と社会の価値観において、戦争システムをてんで放棄していない。
「総力戦」と「優劣価値」の恐怖 00/9/19.
いま、総力戦とか国民国家というキーワードに興味がある。こんにちの経済至上主義をうみだしたのは戦前あるいは戦時中にはじまった総力戦によるものだと考えられるからだ。
しかし軍事的な総力戦が、一般民衆の経済至上主義の意識にどうつながってくるのかということがわからない。なぜ一般の人たちは総力戦に奉仕するメンタリティをもちつづけているのだろうか。総力戦の価値観は一般の人たちにどのように浸透しているのだろうか。
国家同士の総力戦というのは、日常のレベルにひきおとしてみると、隣りに勝ったとか負けたとかの価値観と通底している。こういう「勝ち負け」の価値観は、すこし広がると自分が属する企業の利益ランキングとかシェアランキング、地域の勝ち負けにまで敷衍され、そして大きく広がれば国家同士の競争にまでつながってゆく。ここには個人の自我がそれらの対象に同一化する心理メカニズムがはたらいている。
要は大から小まで人は優劣価値を競っているというわけだ。その価値観があるかぎり、人は隣近所の優劣を競い合い、隣国との戦争に明け暮れるのだろう。
ただ国家が総力戦に邁進するのは勝ち負けのレベルの話だけではない。経済恐慌や景気後退、他国からの侵略や支配という恐怖もあるから、国家はぜひとも経済的にも軍事的にも優越のシンボルを必要とするというわけだ。
はじめに恐怖ありきだ。そして恐怖は勝利や優越を志向する。日本の近代国家化が西洋列強の植民地支配の恐怖からたちあげられたのはわかりやすい例だ。ヨーロッパの近代化もイスラムの脅威であったのだろう。
劣等の恐怖や生存競争の恐怖が人々を駆り立てる。恐怖からたちあがったそれはどこまでいっても切りがない。優越や勝利で鎧や楯で身体を飾りつけようとするのだが、相手も負けてはおらず、恐怖はどこまでいってもやむことはない。ついには大量殺戮へとみちびかれる。競争相手が存在しなければ、恐怖は存在しなくなると思うのはとうぜんの帰結だ。
恐怖というのは幽霊の恐怖と変わりがない。実体のない恐怖なのに逃げつづけている当人にとってはそれは実物のものにしか思えない。
近代の歴史というのは「優劣の病」だったのだろうか。小は学歴競争や貧富競争、大は国家間競争と、われわれの社会や世界は優劣価値にすべて浸食されている。
国家総力戦は日常の個々人の優劣競争の拡大版であり、また代替物である。国家に自我が同一視されるメカニズムは、選挙権とか日本語、国土、福祉政策などさまざまなものの洗脳によるものだろう。
戦後の日本人は経済的な優劣基準を選択し、あるいはみずから選びとってきた。軍事的な戦争は放棄しても、心性としては同じ総力戦の価値観を生き、または背負い込まされてきた。
総力戦の価値観を敗戦によって問うことができなかったのは日本のひじょうに残念な失敗だったと私は思う。どんな対象や手段をとろうとも、国家の総力戦に奉仕させられる個人が幸福になるとはとても思われないからだ。
経済であれ、軍事であれ、国家総力戦のメカニズムを解体することがいちばん重要なことではないかと思う。国家のくびきから解放されるとき、われわれはもうすこし自由に好きな人生を選択できるのではないかと思う。
戦争の日常化 00/9/21.
戦争は終わったのではなく、日常生活や産業システムがすべて戦争のためにシステムづけられている。日常や産業システムが「戦争化」してしまっているのだ。
産業は戦時になれば最大限活用されるシステムに適合しているし、人々は選挙権や社会保障、人権もろもろを与えられ、国家と運命をともにするメンタリティを組み込まれている。
ぎゃくにいえば、現在の産業システムやわれわれの労働力というのは、戦争においてはじめてそのもてる力を最大限に発揮できるのである。いまはかりに生活用品や消費に捧げられているわれわれの活動は、戦時になれば、たちまち戦争機械としてフルパワーの能力と機能に転嫁するのである。
この社会は戦争のための産業システムであり、われわれは戦争のために労働機械化された国民軍隊なのである。
このシステムは第二次世界大戦で終わったのではなく、ますますその精緻さと能力機能を増している。国家の戦争化は近代のはじまりからとどまりようがないようである。
人々が選挙権を与えられたり、国民になったり、社会保障を与えられたりしてきたのは、国民の軍隊として、能動的に戦地におもむく兵力として、国民すべてを最大限に活用するためのシステムにしかすぎない。
国民が教育を与えられたり、労働者として保護されているのは、国民兵力の増強のためである。近代はすべてを戦争化するための歩みにしかすぎなかったといえるのである。
近代の国家間の戦争はその影響力やパワーがあまりに大きすぎたために、われわれの生や産業、政治のすべてを「戦争化」しなければならなかった。戦争に国民の全機能を集中しなければ、戦争に勝つことも、防衛することも不可能だったのである。
われわれはすべてを戦争化された時代に生きている。労働も産業も政治もすべて戦争に集約されている。たとえ表面的には戦争がなかったとしても、好むと好まざるにかかわらず、戦争総動員システムのなかに生きていることを忘れてはならない。
このくびきから逃れる方法なんてあるのだろうか。戦争と国民国家についてもうすこし考えてみるべきだろう。
ご意見ご感想お待ちしております! エッセイに関するご意見ぜひお待ちしております。  ues@leo.interq.or.jp ues@leo.interq.or.jp
まえの断想集「終身愛と有料セックス資本主義」
2000年秋の書評
|TOP|断想集|書評集|プロフィール|リンク|
|