ツブヤキ断想集
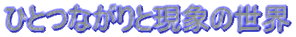
場所と「想像力」 00/5/31.
自転車をこいでいるとき、ふっと気づいた。私はぜんぜん前に進んでいないのではないか、まわりの景色や風景がこちらに向っているだけではないのか、と。
まるでゲームセンターのカーゲームのように座席はぜんぜん動かず、景色が流れているのと同じである。ロード・ランナーに景色がついたのと同じだ。
歩くのも同様で、私は前に進んだり、歩いたりしていると思っているが、ほんとうのところ私は一歩も歩いていないのではないか。景色や場所がこちらに向ってくるだけではないのだろうか。私はちっとも前に「進んで」いないのである。
われわれはよくどこか遠くへ行きたいと思う。ここでないどこかに行けば、心が解き放たれるのではないかと思ったりする。
しかし私は一歩も前に進まない。場所や景色が変わるだけである。「私」はずっとついてくるし、視野の中心に居座りつづけている。
さて私は思いあまって電車にとびのって遠くに行くとする。しかし私は遠くに行ったのではない。場所や景色が変わっただけである。「遠くにきた」という思い、想像が、解放感をもたらすのである。
「遠くにきた」というのは想像力である。「私自身」は一歩も動いていない。場所や景色が変わっただけである。私は「時間」をかけて、「距離」をきたのではない。それは現時点、現在地点からの「想像力」にすぎない。
われわれはどこかに移動するさい、ほとんどを「想像力」で補っている。「遠くにきた」、「どれくらいの距離をきた」とか思うが、それはすべて想像力である。
私は遠くにきたのでもなく、距離を動いたのでもない。場所や景色が変わっただけである。私は一歩も動いていない。視野の中心から私はてんで動いていない。
場所や距離は想像力が補ったものである。私はずっと視野の中心にいる。つまり私の見る世界の中心にいる。想像力だけが距離や遠くという思いを仮構する。その想像力のゆえんによって私は解放感をもたらされる。つまり想像力が解放をもたらすのである。
同じような例として、明日から会社だからいやだなぁと思ったりする。しかし「明日は永遠にこない」。
なぜなら明日とは今日の時点から想像するものでしかないからだ。明日仕事に行くのはいやだなという思いは今日の時点の思いである。想像力である。そして明日という想像物によって、いまの感情が不快なものになる。
つまり明日とは今日のある時点の想像である。いま、思っている時点に明日があるのではない。いま、思っている時点のうえにおいては、明日をじっさいに体験することは絶対にできない。明日をナマに経験した人はこの地球上にだれもいない。なぜなら人は「今日のいま」しか生きることができないからだ。
このことで問題になっているのは明日の仕事が問題なのではなく、いまの気持ちである。「いま」の気持ちが「明日」を思うことによって不快になっている。しかし明日はたんに想像力にしか過ぎない。想像力が私の気持ちを不快なものにするのである。
想像力とは恐ろしい魔物である。われわれはさまざまな日常の体験を想像力で補っている。おそらくかなりの量や部分が想像力で補われていて、われわれは想像力かそうでないかの区別をほとんどしていない。
そして「現実化」された想像力によって、われわれは苦しんだり、悲しんだり、あるいは解放感を与えられたりして、いらぬ苦労や心配を背負い込んでいるのだろう。「想像力」に気をつけろ!ということである。
想像力と無 00/6/1.
われわれの認識はほとんど想像力で補われている。そしてその想像物が想像であることをわれわれは区別しない。ほとんど実体や現実にあるものだと思われている。
自分がどこにいるかという空間認識やどのくらいの距離をきたかという認識もほぼ想像力であるし、いま何時だとか、さっきからどのくらいの時間がたったかという時間認識も想像力で補われている。
われわれの認識のほとんどの空隙は想像力で補われているのである。もしこれがたんに想像や空想にすぎない、虚無である、なんにもないと、この認識補助をすべて捨て去ってしまったら、われわれの認識はどのようになるのだろうか。
私は地図や空間にマッピングされたある地点にいるのではなく、ただ私に見える風景がすべてであり、時間の感覚も時間経過の感覚もなく、ただ「いま」があるだけである。
仮構された想像力というものを疑ってみる必要があるのだろう。これを実体や現実だと思いこんでしまうと、ウソいつわりの世界や虚構、夢うつつの世界との区別ができなくなってしまう。
想像力は映画や小説のフィクションの世界だけではない。われわれの日常の現実認識の多くも想像力によって捉えられている。想像力がなければ、なにひとつ世界を認識できないかもしれない。
言葉や思考というのもすべて「想像力」である。これらはぜんぶ「実体」としてあるものではなく、消してしまえば、なくなってしまう幻影のようなものである。
しかしわれわれは言葉や思考によって捉えたものを「現実」「事実」だと思い込んでいる。これらはすべて一歩引き下がって見るのなら、客観的に見るのなら、すべて「想像」である。
われわれの社会では想像や空想というのはフィクションという狭い世界に閉じ込められているが、事実はわれわれの認識自体のほとんどが想像力によってしか捉えられていないのである。
実体化されていた想像力をとりのぞき、消し去ってしまえば、われわれはどんな世界に対面することになるのだろうか。
想像力の範囲を広めるついでに記憶も想像力に近い、あるいは性質が似ているといえなくもないのではないかと思う。記憶もやはり頭のなかだけの心象や表象であり、実体としてはどこにも存在しないものである。
もしかしてわれわれの知覚――ものを見たり、音を聞いたり、匂いをかいだりといった知覚作用も想像力の一種といえるかもしれない。外界を認識するために外界のありようを捉えようとするのは想像力とはたらきが似ている。知覚も想像力が作為した世界なのだろうか。
想像力の世界を消し去ること、あるいは想像力の区別をすること。そうすれば、「ほんとう」の世界の姿があらわれてくるかもしれない。
目に見えるものは「私の眼」である 00/6/6.
ふつうわれわれは目に見える世界と眼は分けてあるものと思っている。しかし視界は眼がなければ見えないし、眼をつむってしまえば視野は見えなくなる。
視界というのは眼と別個にあるのではなくて、見えている世界も「眼」である、あるいは「眼の一部」であるといえるだろう。眼球なしの視野はありえないし、視界だけがあって眼は空白であるという状態はありえない。
視界というのはこのような意味で「わたしの眼」であるといえるだろう。わたしの肉体の外に離れて、私と別個にあるのではなく、それは「私の眼」である。
エックハルトはいっている。「見るという働きの内では、目即木材つまり、この木材はわたしの目である、と真に言うことができるほどひとつとなる」と。(『エックハルト説教集』岩波文庫)
眼と視界は離れて存在するのではない。一方がなければ片方はなく、両方がそろわなれば眼はちゃんと機能しない。視界は私の外側にあるのではなく、「私の眼」である。
眼と視界はべつべつにあるのではなく、ひとつである。見られている世界はわたしの眼である。ひとつではなく、二つであると分けてしまうから、客観的世界という思い込みがひとり歩きする。
視界がわたしの眼であるといえるように、視界は意識がなければ見えないから「私の心」ともいえる。視界は私の眼や心と離れて見えるものではないからだ。
さあ、視界も「私の眼」である、または「私の心」であるといえるようになったが、見えているモノや光景、人物が、「私」や「私の心」であるというのはにわかには理解しがたい。
肉体や思考、感情とはまた別のありかたを示すからだ。あまりにもよそよそしく、私にとってはまさに不随意であり、大部分がコントロール不能なものである。だからこそ、それが「私」であるという認識は捨てられるともいえる。
しかし視界や環境なしの私がありえないように、それらは私と不可分のものである。視界や環境はかなり「控え目」な私である。
視界と私の眼を分けてしまうことによって起こる過ちは眼や心がつくりだしたものを美醜や好悪といった判別で追いかけ回したり、逃れたりすることである。つまり眼がつくりだしたものを私は追い回し、心がつくりだしたものを心が追い回すことになってしまう。
心は犬が自分のしっぽを追ってぐるぐる回りつづけるような目にあっているということだ。すべては私の眼や心がつくりだした世界であることを知らないから、心がふたつに分裂して心が心を追い回すような目に会ってしまうのである。
私の内で現象する世界や物事はすべてわたしの心がつくりだした虚構や幻想であり、それゆえ「私」であり、「私の心」である。だから過ちに陥らないためになにものにも執着するなと仏教はいってきたのだろう。
心を離れて世界は存在しない 00/6/8.
心を離れて世界は存在しない。心がなければ、世界は見られない。寝ているときには世界はなくなっているし、死んでしまっても同様である。だから世界は心であるといえる。
眼を離れて視界は存在しない。眼がなければ、なにも見えない。だから視界は眼であるといえる。
耳を離れて音は聞こえない。耳がなければ、なにも聞こえない。だから音は私の耳であるといえる。
においや味も同様である。鼻がなければにおいはかげないし、舌がなければ味は感じられない。だからにおいは鼻であるといえるし、味は舌であるといえる。
視界や音、においは私と離れて外部や外側にあると思っているが、じつは眼や耳、鼻と離れてあるのではない。それらの知覚器官がなければ感じられないものであり、外側のものというよりか、いや内側のものであるというか、内とも外ともいえないものである。
私の外側にあるように思えるが、私の内にあるというか、あるいは内とも外ともいえないようなあり方をしている。
われわれは眼や耳を外側から見たかたちで捉えがちであるが、自分自身から見れば、それは視野や音としてあらわれているが、眼や耳と離れてはありえないので眼や耳といえるのである。
私の外側の人物やモノはやはり同様である。私の心や眼を離れて存在しない。私の心や眼といえる。
私の中で現象するすべては「私」や「私の心」であるといえる。私や私の心を離れて存在するわけではないからだ。
しかし他人やモノ、視界や音などは、私の肉体や内側のあり方とはまたべつのありようをしている。「私」とはいいがたいあり方である。
だから私と分けられ、「区別」しやすい。だけど、それらは私の心や眼、耳と離れてあるわけではないので、私や私の心、眼や耳だといえる。私と対象、私と外界といったように分けられるものではない。「ひとつながり」である。
私に知覚される現象のすべては「私」であり、「私の心」であり、または「私」ともいいがたいものである。他人やモノ、風景、音はどうしても「私」とはいえるものではない。しかし「私」や「私の心」を離れてあるわけではないのである。
そういう「分け方」や「区分」を捨ててしまえば、ただ「ひとつながり」の世界だけが残ることになる。
ひとつながりの世界 00/6/10.
仏教では世界はひとつながりである、世界はひとつだという。このことを実感することが悟りだという。
つながりの世界について岡野守也は『唯識のすすめ』(NHKブックス)のなかで、「花」はそれ自身のみであるのではなく、枝や幹、根とつながっていて、水や養分、太陽の光とつながっているからひとつであるという説明をしている。
仏教の縁起をこういう生態的な言葉で説明されると違和感はあるが、ひじょうに理解しやすかった。単体を見てゆくと、この世界につながりのないものはないだろう。
ただそこから実感とか融合するような世界観というのはなかなか出てこないようには思うが。しかし入り口とか気づきの端緒としてはひじょうに興味をひかれるものだった。
われわれは人やモノ、自分と外界といったように、分けられたり、区切られたりしたばらばらの世界に生きている。どう見たってモノはモノ、他人は他人としてばらばらに存在しているように思えるというのがふつうの人の感覚というものだ。
この世界がすべてつながっている、世界はひとつであるという見方にはなかなか飛躍できない。
物質的な説明ではたしかにつながりは理解できるが、実感にはなかなかおよばない。たとえば私のからだは外界の水や空気、食べ物で構成されているし、地球の気候や重力と無関係に存在できるわけがない。
しかしこういう説明は物質的な単体観から抜け出せないし、概念的な理解にとどまってしまうだろう。実感や体感にはおよばないのである。言葉や心象を利用する以上は無理のないことだが。でも理解への糸口に近づける一歩になる。
ところでひとつながりの世界とは私に知覚される世界はすべて私の心と離れてありえない、という意味でのひとつなのか、それとも私と離れた客観的世界でもつながっているという意味でひつとながりなのか、すこし気になった。
もちろんこの世界は私の心を離れてありえないと仏教ではいっているので問題外の疑問なのかもしれないが、心と世界がつながっているという理解だけでいいのだろうか。
世界はひとつながりである、ひとつであるという見方はなかなか気になる。こういう側面に注意深くなって、理解を深めたいと思う。
モノではなく、現象し変化している世界 00/6/12.
われわれは実体としてあるモノや固体としてあるモノ、ばらばらに分離したモノの世界に囲まれていると思っている。まあ日常の感覚ではこれがふつうである。
でもどうやら世界をモノの集まりと捉える見方は誤りのようである。世界は「現象」や「変化」の集まりだと捉えたほうがより実状に近いようである。
現象や変化があきらかに現れる代表的なものは雲や風や煙、火、雨、水、といったものである。これらは一瞬に現れ、また一時的にすぐ変化し、形を変えてゆくものである。じつのところ世界のおおよそのものはこのようなあり方をしている。
ところがわれわれのまわりにある環境というのは、持続的にずっと同じ形やモノとして存在するものに多く囲まれている。たとえば道路や家、机やイス、服やかばん、また人間や私もそうである。
現象や変化しつづけているようには見えない。ただ長期的には崩れたり、はがれたり、錆びたり、破れたり、壊れたりして、変化をこうむらないものはない。という意味でこれらも現象や変化しているものだと捉えることができるだろう。
われわれの世界というのは現象や変化のるつぼである。形あるものはやがてその形を変え、生成したものはやがて消えてゆく。世界をこのように捉えるほうが実状に近く、またはるかに苦悩や苦痛をひきずらない認識をもてるはずである。(無常観に感傷的にならなければ)
固定的なモノに囲まれた世界観にわれわれが捉えられるのは、ある現象を同一のモノ、ほかから切り離された一体のモノと捉えるほうが生物としては生きやすかったという理由があげられるだろう。
現象や変化を一回きりのもの、二度とないもの、同一でないものと見なしてしまえば、生きることが容易ならざるものになるのはとうぜんのことである。
ただし、それが行き過ぎるのも問題である。それによって人間は「固定的なもの」、「変化しないもの」、「永遠なもの」、といったものを求めてしまうがゆえにこの現象・変化の世界の苦悩に引き裂かれてしまうのである。
言葉はまたその固定化に多大な貢献をなした。現象・変化しているものにたいしても「名詞」を冠することによってその「実体化」や「継続化」を印象づけてしまう。たとえば、「こぶし」、「いなずま」、「波」「うず」「騒音」などは一時的なものだが、あたかも継続的なモノがありそうな印象を与えてしまう。
また変化や現象は雷や風、いなずま、雨などがそうであるようにたくさんの要因、現象がつながってあらわれている。言葉はそこからあたかも「固体」であるかのようにまわりの現象からそれを切り離してしまうのである。
この世界のいかなる物体やモノも変化しないものはない。たとえ短期的・中期的には変化しないものであっても、変化は見えないところに侵蝕し、確実に変化をもたらしている。
この世界のありようは瞬間的な現象がいちばん如実にあらわしていると捉えたほうがよいようである。物体や人間というのはそのヴァリエーションのひとつのあらわれである。
「私」という人間も一個の継続した固体とあるというよりか、さまざまな現象や変化のあらわれだと捉えたほうがよいようである。歳をとったり、気分が違っていたりして、変わらない自分はいない。
人間の関係や人生の状態、社会のありよう、といったものも変わらないものはなにもひとつとしてない。永続的・固定的なありかたを求めようとするのは、この現象・変化の世界ではおよそお門違いというものであり、苦悩や悲痛をもたらすのみである。
一回きり、二度とないもの、同一でないもの、といったこの現象世界の側面に注意深くなることが必要のようである。
「現象する世界」とそれを押しとどめるもの 00/6/13.
この世界は固定したもの、変わらない同じもので構成されているというよりか、一時的で二度とないもの、同一でないものの現象が生起する世界であると見るほうが実状に近いようである。
音というのはその代表的なものだ。音は一時的で二度とないもので、一度聞いたものをそっくり同じに聞くことはできない。この世界はそういった現象によって構成されている。
動くものに注目してみても、そのことがよくわかる。雲や風、歩く人、走る車、そういったものを見ると過去の姿、過去にあった場所を二度と再現することもできないし、とどめることもできず、去ってゆくものである。
人間や自分というものもそうである。かつての幼少期の私と大人の私は違うし、さっきの私の気分といまの私の気分は同一のものではない。いまの私の興味や関心はさっきのものとはまったく同一であるとはいいがたい。
人との関係もそうである。友情や愛情、親子や家族の関係、といったもので変わらないものはない。
こういう一時的、変化する世界に住んでいる以上、われわれもこういう現象性に身をまかせたほうがよいのだが、どうも人間はこの流れに抵抗するのが習い性のようである。
変わらない幸福やいつまでもつづく平穏、ヒビの入らない人間関係といったものを求める。変わらないものはないのにそういった固定的・永続的なものを求めてしまうがゆえに苦悩や悲痛の叫び声をあげる。
われわれの頭の中はその典型である。終わってしまい、二度と帰ってこない過去に限って、われわれは何度も何度も思い出し、あれこれ考え、悩み悲しみ怒るのである。
一時的で二度と帰ってこない現象の世界なのに、その一度きりの現象をすんなりと、こだわりなく、流すことができないのである。そのためにわれわれは苦悩し悲哀するのである。
まわりの聞こえるなにげない音をとりもどそうとしたり、もう一度聞こうとする人はそういないが、そういう不可能な試みを、人々はえてして愛着があり、願ってやまない幸福や平穏の領域になると、是が非でもおこなってしまうのである。
音や動くもののようにわれわれの人生や経験というのは一時的なものであり、二度と同じものでないと見なしたほうが、この世界では苦悩しなくてすむというものである。
音や動くもの、流れるものといったものはわれわれの人生の手本ということができる。「風のように、雲のように、水のよう」に、とどまることなく、流れてゆけばいいのである。
▼新規更新分
人の感情を害することを恐れること 00/6/14.
さいきん歯医者に通っているのだが、ほとんどが欠けている歯の抜歯を断るのをなかなかいいだせなかった。そこの歯医者は抜歯をあたりまえと考えていて、抜かない努力などそもそも念頭にすらないところだったので、いいにくかったのである。(そもそも患者の意見など聞く気もないのもあったが)
いってみたら案の定、その歯医者さんは憮然としていた。治療方針うんぬんとか医者と患者関係のことより、私はその人の感情を害したことがいちばん気かがりだった。
私というのは人の感情を害することをもっとも怖れ、ひたすらそうならないように人との衝突や感情の波風を荒立てることを避けている。人のマイナス感情を極端に恐れているのである。
そのために自分が主張しなければならないことや意見の相違を押しとどめたり、物事のとり決めを相手側にゆずったりすることが多々ある。
まあ意見やとり決めは自分がゆずればなんの問題もないからいいけど、他人のマイナス感情の発生を極端に恐れる性質というのは問題である。いちど発生すれば、とりつく島もないと思ってそこにいたるまでの予防策にかなりの心身をついやすのである。
まあ私の人格というのはおおよそその予防線上に形成されたものと、おおげさにいえばいってよいだろう。「他人の感情を害さないための自分」ともいえるかもしれない。
感情を害さないように人に気配りをしようとすると、まったく際限がなくなる。どこまでもどこまでも他人の顔色や気分や、考えていること、思っていることを注意深く、繊細に配慮しなければならなくなる。
そもそも自分と関係のないことで他人が不機嫌になっていたとしても、私は自分がその人の感情を害したような気分、もしくは責任があると思うようになってしまうのである。でもわかるわけなどないのである。
どこからか他人の感情の配慮を捨てる線引きが必要なようである。感情の配慮など際限がなく、他人の感情に全責任を負うというのはまるで不可能である。他人の感情は他人のものであり、上機嫌不機嫌はその人の責任にある。
配慮し過ぎるのは問題である。どこで捨てなければならない。さもないと不機嫌さの感情で他人に操作されることになってしまうし、いうべきこと、いわなければならないことも、感情を害することを恐れていえなくなってしまう。
世の中には人の感情を害しても、断固としていわなければならないこと、いうべきことというのはあるはずである。そのときには他人の感情はあまり配慮すべきはないだろうし、関係の崩壊にも気を配るべきではないのだろう。
*
ところで私のように他人の感情を害することを極端に恐れる人間がいるいっぽう、反対側には他人の感情を害して喜んだり、困らせたりしてうれしがる人がいる。いじめである。また性格の悪い人やストーカーというのもそうだろう。
たぶん相補的に存在しているのだろう。主題は他人の感情である。際限なき配慮の裏側には他人の感情への配慮放棄と責任を自分で負わせるという構造がある。
「感情はだれの責任か」ということが根底にある問題なのだろう。いやな気分になったのは「他人のせい」だと見なす認識の社会では、人は際限なく他人の感情に配慮をおこなわなければならなくなる。その反対に感情の責任を他人に転嫁できない、自分に封じ込めてしまういじめがあるというわけだ。
認知療法や東洋思想がいっているように感情は自分の思考や説明スタイルがつくりだしたもので、他人に責任はないと見なす考え方がひろく社会いっぱんに浸透する必要があるのかもしれない。
「いつわりのリアリティ」 00/6/15.
われわれが毎日考えたり、思ったりすることは、「いつわりのリアリティ」である。これは「現実」にあるのではないし、実際にあるわけでもない。
あくまでも「心象」や「言語」が創造した「絵空事」にしか過ぎない。
しかしそれが「現実感」をもつようになるのは、頭で考えたり思ったりしたことに感情や気分がついてくるからである。怒りや悲しみが起こるから、「現実」のように思ってしまう。
感情をもよわせるのは、思考や過去の心象や解釈である。思考というのはもちろん実体としてはどこにも存在しないものであるし、過去というのは過ぎてしまえば、いっさい存在しなくなってしまうものである。
いずれも実体としてはどこにも存在しないものである。そして感情というのはどこにも存在しない、「虚構の産物」によって生み出されるものなのである。
われわれの「リアリティ」というのは、まったくどこにも存在しないものによって生み出されるのである。すでに過ぎ去り、言葉や思考という頭の中だけにあるものに創出されるのである。これはまったく「いつわりのリアリティ」である。
小説や映画というのはまったくどこにも存在しない虚構の産物であるが、われわれはこの虚構のリアリティにしっかりと感動したり、怒ったり、悲しんだりする。
日常の経験もこれとひとつも変わらない。しかし日常の物語はすべて自分が、言葉や解釈によって「創作」して、「物語」っているわけである。人はそういう「解釈主体」である自分という「語り手」をふだん意識していないだけなのである。
心象や思考というのは、自分が意図したわけではないのに、頭の中につぎつぎとわきあがってくる。その心象や思考のままに考えたり、思ったりすることを乗せてゆくと、「いつわりのリアリティ」の「リアルさ」と「迫力」はどんどん増してゆき、怒ったり悲しんだりの悲喜劇にふりまわされることになる。
「いつわりのリアリティ」にだまされないためには、心象や思考を「絵空事」だと相手にしないことである。虚構や思考を軽蔑すればいい。
そういう習慣を長くつづけると、心は静まってきて、「いつわりのリアリティ」や思考の饗宴というのはだいぶ遠景にしりぞいてゆく。思考のバカ騒ぎも収まってゆく。
おそらくこういう静かな心のほうがよい状態なのだろう。「いつわり」の「まやかし」の騒がしさは遠くに去ったのだから。
「鳥」が鳴くのではなく、「鳴く音」があるだけである 00/6/17.
鎌田茂雄『華厳の思想』(講談社学術文庫)にこういう一節がある。
「「ホトトギス鳴く」というのは、ホトトギスがいて鳴くという動詞がつくのではない。鳴くという現実があって主語としてホトトギスがあとからつく。絶対の現実は「鳴く」というところにある。ギャーッと鳴いた、それが絶対の現実で、それを分解するとホトトギスが出てくる」
「竹が裂けたのではなく、裂けたという絶対現実の世界がある。そのあとで概念で組み立てると、「竹が裂けた」となる。裂けたというところだけが真の現実で、それを言葉でもって媒介すると主語の「竹が」生まれて、「裂けた」という述語が加わっていく」
われわれは鳥の鳴き声を聞くと瞬時に「鳥が鳴いている」と思う。しかし「鳥」というのはあとでつけたした言葉や説明である。鳴き声だけがわれわれには聞こえている。
われわれは音を瞬時に聞き「分ける」。言葉や記憶、心象が一瞬にして、音の原因や発生源を出してくる。
あまりにも自明に音の主語を思い浮かべるが、ほんとうのところは、われわれには「音」が聞こえるだけである。「鳥」だと見なす心の作用は、その音自体にはない。
想像力や記憶、言葉がそれを補っているわけだが、それも一瞬に判断・分別できるわけだが、実際に聞いているのは「ただ」の音だけである。
われわれの心の作用というのは、驚くほど巧妙である。判断や分別していることすら気づかせずにナマの現実を遮ってしまう。瞬時に音の「主語」をわけもなく推察している。
雨音にしろ、車の音、電車の音、風の音など、われわれはすぐその音がなんの音かわかる。でもわれわれに聞こえているのは、なんの音か分別する前の音だけである。
そういう音を聞いたとき、宇宙世界が破れ、悟りが開けるということである。う〜ん、それにしてもわれわれの「分別心」というのはとてつもなく素早いのは感嘆ものである。
聞き分けたり、分別することが、絶対現実の世界を遮る「想像力」=「絵空事」であるというのはなかなか気づけないであろう事実である。
仏教の森でつんのめり! 00/6/18.
数多くある仏教思想のなかで、いまのところ私が興味のあるのはやはり、理論的な唯識や華厳といったものである。心理や世界観についての理論的な言説に興味がある。
でも仏教書というのは、だいたい本屋にならんでいるのは一般的な道徳とか生き方が前面に出された本が多い。こういう本というのはどうも理屈っぽい私の趣向にあわない。
おもな経典とかもなかなか手に入りにくい。全集とか高い本になり勝ちだったり、書店では見つけにくかったりする。岩波文庫では何冊かはおもな経典があるが、現代語訳がなかったりして読めなかったりする。
仏教の理論的なことを学ぼうとしても、読みたいテクストが手に入りにくいのである。しかも私が知りたいと思うテーマ一つにしぼった本というのもなかなか見つけにくい。入り口と先につづく通路が、せっかく興味があっても、つづかないのである。
経典についても、はじめはなかなか記憶に残らなかったが、だんだんと著者がだれだとか、どの学問の本かもわかりだしてきたのだけど、その当の本に当たれないというのはひじょうに残念だ。
日本の仏教というのは理屈っぽいことより、念仏や坐禅によって悟ろうとする単純な方に流れてきたそうである。それがいまでは寺めぐりだとか仏像を拝むだけだとか、道徳的な諭しといった、私にはあまり感心しない仏教のイメージができあがっていったのだろう。
仏教というのは掘り起こせば、心理学的にも哲学的にもズコイことをいっていると思う。ただそういう本がなかなか手に入りにくいし、たしかに理論的なことを学ぼうにもよけいな言説がたくさん費やされているし、これじゃあ観光・葬式産業になるか、そっぽを向かれるしかないよ。
日本人の知的レベルは上がったはずだし、心理学とか哲学に興味をもつ人も増えてきたはずだから、理論的な仏教も復興されていいはずなのにと思うのだけど。多くの人が流れていた戦後の経済信仰も終わったことだし。
でもその前に日本人には宗教アレルギーがことさら強い。私だって数年前までは宗教なんて大キライだったし、親が念仏なんか唱えだしたりしたらやめさせていた。さらにオウム真理教の事件は宗教アレルギーにさらに拍車をかけたことだし。
ほんとうのところ日本人というのは宗教アレルギーではなく、知的探求心の禁止や抑制がいっぱんの人たちに浸透しているのではないかと勘ぐられる。知ろうとする好奇心がだれかに禁止されているみたいである。アニメやオタクが嫌われる偏狭さと同様である。
まあいろいろ障害はあるけれど、私の気まぐれな興味がつづくかぎり仏教の森を散策してみたいと思っている。仏教の世界はあまりにも広大で歴史的にもとてつもなく長い時間をへているので、私が知っているのはほんのわずかなことだけだ。
お寺とお経と仏像と 00/6/19.
お寺をめぐったり、仏像を拝んだりする意味が私にはさっぱりわからない。たんなる場所とか建築物だとか木の像くらいにしか思えない。どうして一般の人たちはそういう意味のわからない行為とか信仰をもつことができるのだろうか。
お経にしても、漢文なんて意味もわからないものを読んだり、並べたりして、なんの意味があるというのか。『般若心経』にしても漢文だったら、たしかにいかめしく、荘厳な感じがするが、意味がわからなかったらなんの役にもたたないじゃないか。現代語訳で読んでみてはじめてその内容には驚かされた。
仏教というのはちゃんとした現代語で読んでみると、ひじょうに内容の深い、意味のある、論理的・心理学的・哲学的なことを語っているものである。
だけどそういう書物は漢文や古文であらわされ、一般の人たちの目にはとどかないところにしまわれ、かれらは意味のわからない外国語のお経を聞かされ、建築物や木の像をありがただって拝んだり、ながめたりしているだけだ。
なんでこんな転倒した世界ができあがっているのだろう。学ぶべきは経典の内容や意味であるはずなのに外国語でそれは読まれ、木の建物や像をありがたがって拝んでいる。
私は大阪に住んでいるから仏教名所には比較的かんたんに行くことができる。高野山にしろ、四天王寺にしろ、比叡山とか東大寺とかには一度は行っている。さっぱり意味はわからない。木の家とか人形を見てきて、さあなんだったのかなと思うくらいだ。
こういう状況になったのは、日本仏教の念仏、浄土、禅などの単純化のせいなのか、それとも一般の人たちの知的レベルが低かったせいか、あるいは西洋知識に押されてこうなったのだろうか。
まあ建物とか像をありがたがるのはあまりいい傾向だとは思えない。経典が読まれないのは人々がそこまで深刻な悩みをかかえていない、そこそこ幸せだったと捉えることもできる。
私のように理論的・心理的に仏教を知りたいものにとってはちょっと不満だし、経典がちゃんと読めるかたちで手に入るのが理想的であるが、まったくそういう道が閉ざされているわけではないし、探せば見つかるようだからまあいいとしよう。
ご意見、ご感想お待ちしております。
 ues@leo.interq.or.jp ues@leo.interq.or.jp
前の断想集「虚構の自己論」
00年夏の書評「自己と境界―私とは何か―仏教」
|TOP|断想集|書評集|プロフィール|リンク|
|