2001年初夏の書評集
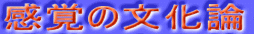 ほか ほか
▼2001/4/22.
マーシャル・マクルーハン『人間拡張の原理 メディアの理解』  竹内書店新社 64. 1442e(古本) 竹内書店新社 64. 1442e(古本)
ずっと前から読みたかったメディア論の古典だが、現在入手できる版では高すぎて手が出せなかったのだが、100円の古本でみつけた。ラッキー!
この本の中でいちばん感銘した二点は、メディアや道具は人間の身体の拡張であることと、印刷文化が画一化や規格化の大量生産をうみだしたということである。
断片化された感覚の延長であるメディアやそれによってうみだされた認識の偏り、全体性からの疎外などの指摘は、ひじょうに頭の混乱をもたらす新しい衝撃であり、もっと深く理解したいと思わせたのだが、そのテーマの本はあまりないか、高すぎるかのどちらかだ。突出した名著であるのはまちがいない。
エドワード・ホール『かくれた次元』 みすず書房 66. 1700e(古本)
なんの本かわからないが、なぜなら動物学、知覚論、比較文化とかいろいろな分野が語られているからだが、おもに文化のなかの空間や距離のとりかたといったものが語られているようだ。
言語文化によって知覚世界が異なるように、文化によって空間や距離の感覚も違ってくるということだ。日本人にとってアメリカ人は近づき過ぎるが、アラブ人はもっとひどいとかいう比較文化の話はおもしろい。言葉以外の五感や身体感覚の知見には学ぶべき、銘記しておくべき箇所も多くあった。
西田幾太郎『善の研究』 岩波文庫 1911/1. 600e
しまった、しまった、わからないかなと思っていたら、問題の立て方はある程度興味が魅かれたかもしれないが、わからないというか、言葉が古くて堅すぎてあまり理解しようとも思えなかった。日本初の独創的哲学者であるということで、私も著者が歩いたという京都の哲学の道を歩いたこともあるが、まあそれ以上の「縁」はなかったということで。。。
コリン・ウィルソン『至高体験 自己実現のための心理学』 河出文庫 72. 1200e
コリン・ウィルソンのことだからもっと怪しい、やばい領域のことまで語ってくれると思っていたのだが、フロイト、マスローなどメイン・ストリームの話で終始していて、てんで刺激的でも挑発的でもなかったのが残念だ。
72年という時点ではまだニューエイジとか禅、トランスパーソナル心理学の運動は興隆していなかったということか。それにしてもコリン・ウィルソンは粘着質の文体だなぁ。
コンスタンス・クラッセン『バラの香りにはじまる感覚の力』  工作舎 93. 2200e(古本) 工作舎 93. 2200e(古本)
視覚以外の感覚のコスモロジーを探るという点では、革命的な書物ではないかと思う。視覚偏重に気づいたら、まずはほかの五感の世界を探らなければならない。人間は物理的世界を見ているのではなく、文化に規定された世界を見ているにすぎないのである。そういう意図にはこの本はぴったりで、一字一句もらしたくない本である。
西洋近代は活字・印刷文化による視覚世界の支配や偏重をおおいに蒙ってきた。その世界の外部に出るためには、人間にほんらい備わっているはずの感覚の力をもう一度思い出す必要がある。人間にははたしてどんな鋭敏で卓越した感覚の世界が備わっていたのだろうか。
狼に育てられた野生児の感覚世界、においによる階層差別、他集団の区別、メキシコ原住民の熱によるコスモロジー、東南アジア原住民の匂いの宇宙観、アマゾン原住民の色彩の世界観など、おもに用いられる感覚の違いによって世界はどのように変わるか。
感覚というのは世界のありようや文化の秩序をがらりと変えてしまうものである。言語や活字文化などのメディアによって現代人はその知覚世界をどんなに狭められ、歪められているか計り知れない。貶められた感覚世界をとりもどすためにぜひとも読みたい一冊である。
山下柚美『五感喪失』 文藝春秋 99/11. 1619e(古本)
著者が五感に関心をもったのは、死に面した人が生きている証しを五感に求めたからだという。音、形、匂い、質感、そういったものに生きる実感や証しが潜んでいることを著者はかれに感じたのである。しかしわれわれはどうか? 情報に浸かり、身体や感覚で感じることにまったく鈍感になっている、それが問題意識の出発点である。
においを消す清潔志向の女性やSMショー、手触り、味覚、耳の快楽などの現場が語られてゆく。まあ、それなりの参考になるかもしれないが、しかし、私は現場のルポや行為よりその意味や理由を知りたいタチなので、どうもルポにはいまいち興味が魅かれない。それにしてもルポの文体ってどうしてこう現場の人の言葉や会ったことを、証拠のように記してゆかなければならないのだろう? 好きな文体ではないな。
山岸美穂・山岸健『音の風景とは何か サウンドスケープの社会誌』 NHKブックス 99/6. 920e
音の世界をとりもどす試みというか、こういう感性の社会学の研究がすすんでいるというのは意外である。いろいろな音の風景や学者の説がとりあげられていて、ひじょうに参考になる本だが、でもなんだかつかみどころがない読後感だけが残るな。
「母が生きていたころ、隣の部屋の母が立てるもの音を、『いいな』、と思ったものだ。何気ない片付けの音、着物を着かえているらしい音、よみ物の頁をめくる音、今も私の耳の底に残っている、なつかしい音である」
「暗闇が訪れるにつれて、昼間、耳に触れなかったような微妙な音が生き生きと体験されることがある。夜の静寂において、昼夜の音の表情において体験される世界の微妙な様相に気づくことによって、私たちは自分自身の生存を深く自覚することができるのではないだろうか」
こういう耳を澄ます経験というものが、この世界にたいする敬虔な気持ちや郷愁、憧憬といったものをたまらなく引き立てるものである。私たちはこういう音の風景という世界や地図、価値といったものをもう一度顧みるべきではないだろうか。
それにしてもモースが聞き耳をたてた明治初期の音風景というものを一度は聴いてみたいな。花売りの「死に瀕した牝鶏の鳴き声そのまま」の声や、あぶくの液を売っていた男は奇妙極まる叫び声をあげていたというし、盲目の按摩の甲高い笛の「哀れっぽい調子」、どんな仕事をするにも歌っていたらしい日本人の唄なんて聴いてみたいものだ。人間の声や行為自体がメディアだったのである。
松榮堂広報室『香りの手帖』 福武文庫 86/8. 620e(古本)
まあ、香りについての歴史や文化や科学、遊び、作法などの雑学アンソロジーである。福武文庫ってもうやめてしまったのかな。
堀切和雅『「ゼロ成長」幸福論』 角川oneテーマ21 01/4. 571e
タイトルがいい。いっていることには全面的に賛同する。「脱競争主義」「日本人は生活が薄い」「年収二百万でも負け組ではない」「つくられたみじめさ」「選択肢のない、可能性のない人生」「景気がすべてを癒す思考からの脱却」「経済化されすぎた人生」といった内容が身近なまわりの人たちを中心に語られている。でも一読したら終わりという本であるという気がしないでもない。
『Z-KAN/フリーターってどうよ?』 増進会出版社 00/11. 800e
フリーター特集号の雑誌である。山田太一、森永卓郎、橋爪大三郎、小谷野敦などの文章が寄せられている。佐高信などからの会社中心社会の批判が抜け落ちている。フリーターっていうのはやっぱりこれまでのサラリーマン社会のつらさから生まれてきたもので、その土壌を無視してはフリーターは語れないと思う。
森永卓郎の「勝ち組なんかやめておけ」がいちばんおもしろく、有効であったと思う。もうこれからみんなビンボーになるんだから、サラブレットをめざさず、ビンボーでもいいから好きなことをして生きろ、と主張している。人生の三大不良債権、配偶者、子ども、家はこれからもつなともいっている。
すっぱりと言い切っているのがこの人のとても好感のもてるところだけど、人生そこまで割り切れるか、未練や不安が残るのではないか、この姿勢で会社とうまくやれるか、人生設計はどうなるのか、と旧来の人生モードから考えてしまう。責任はだれがとるのかと思ってしまうが、やっぱり貧困と苦労は自分だけで背負えということか。
小谷野敦の学者や浪人、芸術家などの哀れな貧困の人生行路もなかなかおもしろかった。「世間からトンズラするためのBOOK MAP」には隠遁者たちの本が紹介されているが、東洋的隠遁って現代にどういうふうにもってこれるものなんだろうか。青テントのホームレスからの派生?、アウトドアの進化形?、バックパッカーの定着先?、これらに高尚な精神世界や芸術が付加されないと「上がり」にはなれないみたいである。
マジョリー・F・ヴァーガス『非言語コミュニケーション』 新潮選書 87. 1050e(古本)
感覚の世界観を探っているうちにこういう動作や表情のことばの研究に迷いこんでしまった。近いような気もするし、同じことを語っているかもしれないし、全然別の話かもしれない。でも「ことば以外のことば」に注目するということは、やはり感覚の世界観のことをいっているのであり、言語以外に注目したということで、言語中心主義から逃れているともいえるのだろう。
この本ではボディメッセージ、動作と表情、目の使い方、周辺言語、沈黙、触れ合い、空間と距離、時間感覚、色彩などが注目されている。まあ、どんな動作や行いにもメッセージや意味が込められているということであり、無意識にそれをおこなったり、読みとっていたりすることを意識化・言語化する試みがここでおこなわれているわけだ。
多田道太郎『しぐさの日本文化』 角川文庫 72/7. 260e(古本)
脱臼させられるというか、不意を突かれるというか、唖然とさせられる本である。ほんのささいな何気ないしぐさや動作にこれほどまでの意味や内容が込められていたなんて思いもしないものである。
ものまねに模倣と同一をよしとする価値観を見、へだたりに地位差を見つけ、握手に服従の発展形式を、お茶やたばこに他人と会うことのしんどさ苦しさを、失恋の唄に傷の同情を、咳払いに神道の祓いを見出している。ほんのささいなしぐさにこれほどまでの意味や起源、歴史がこめられているというのは、不意打ちを食らった気分だ。
また嗅覚が貶められたのは分節化がむずかしく、視覚や聴覚は分節化・明晰化が可能であったから尊重されてきたことがのべられている。触れることも分節化がむずかしく、心の触れ合いは性に局限化され、触覚や嗅覚はエッチで動物的なこととして貶められようになったと指摘されている。こういう感覚比率の変遷や差別化というのは、人間の生の実感や充実感、世界観と深くかかわりがあるので、深く追究する必要があると思う。
川本三郎『都市の感受性』 ちくま文庫 84/3. 440e(古本)
よい、よい。文芸評論ってけっこう社会学なんだな。
70年代以降、若者がおとなしくなったのは60年代の反抗が日常化してしまい、いまさら騒ぎ立てる必要がなくなったからで、歴史上はじめて「若者」が誕生したということである。そして権威の失墜は文化が勉強から「遊び」の対象に変化したことに関わりがあるという。
島田雅彦の演技することの苦痛や、村上春樹のカッコよさは熱い自己主張でなく、醒めたニヒリズムを体現しているからだという説明や、自閉の快楽に満足する若者、山田太一の都市郊外論など、ところどころに光る一般的な見解をそっくり覆す意見にはたいへん楽しませてもらった。
人間社会の「新しいこと」は初めは「病気」とか「脱落」「異常」だとかのマイナス面のレッテルを貼られ勝ちになるが、ほんとうのところそこには「快楽」や「満足」、「充足」などがあると見るべきである。古い頭にとって新しいことはたえず「不安」であるが、そこに「よさ」を見出さないことには次の時代を乗り切れない。
ご意見ご感想お待ちしております!  ues@leo.interq.or.jp ues@leo.interq.or.jp
テーマに沿ったエッセイ集 視覚の帝国、嗅触覚の蔑視 01/4/18.
2001年春の書評「物語を読む―童話心理学」
|TOP|断想集|書評集|プロフィール|リンク|
|